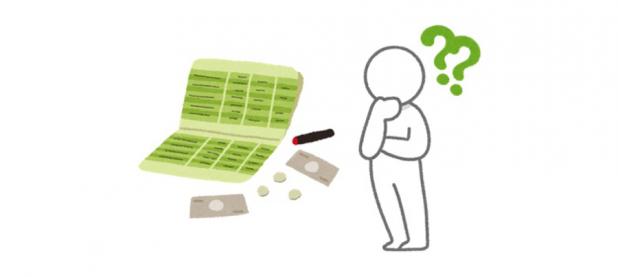生前贈与した分を親が預かる(子の意向で)も名義預金でしょうか ?贈与契約書と借用書を揃えても?
お世話になります。相続税の節税について税理士の先生方からご助言を賜れれば幸いです。自分の早死に対策として、子どもに年110万以下での生前贈与の提案をしたところ、「使い込みが怖いので、預かってほしい」と言われました。私としては構わないのですが、この場合でも名義預金になるのでしょうか?例えば、こちらが名義預金を反証できるよう"贈与契約書"と"借用書"?を揃えておけば、疑われても脱税でないことを立証できるでしょうか?
現状考えているのは、
①年110万円以下の生前贈与(相続時精算課税方式):"贈与契約書"→②同額を親(私)が預かる:"借用書"(無利子で10年期限)→10年経ったら返してまた借りるを繰り返す→③私が他界したら生前贈与分は非課税で子どもの手元に返る
ですが、どうでしょうか。加えて何点か質問したいですが
・質問1…この場合だと実質資金移動の必要が無いので、書面だけを交わし続けるだけで生前贈与を進められるのでしょうか?実質的に無意味でも、形だけでも銀行口座間での送金実績を作るべきなのでしょうか?
・質問2…税務署から名義預金を疑われ、こちらが反証として用意していた信憑書類(?)を出した後についてですが、税務署はこれらが無効であるなどの反証ができない限りは脱税認定ができないのですか?それとも「最初から名義預金する気だったに違いない」といった言いがかり的な理屈で脱税認定できる強大な権限があるのですか?(この程度の金額で税務調査がわざわざ…という点はいったん無視してでお願いしたいと思います)
・質問3…確認ですが、相続時精算課税方式だと(私の例での)生前贈与できた分は私の他界後には無税で子どもに返り、暦年課税方式だった場合は7年遡及分の生前贈与は全額相続税対象となる。で合っていますか?
・質問4…"預かる"契約書ですが「借用書」で正しいでしょうか?何かもっと適切なものがあればご教授いただきたいです。
・質問5…契約書は電子契約(電子署名?)とやらが費用安そうなので自作してみようかと考えていますが、いざとなった時の信憑性は信頼に足るものでしょうか?費用かけてアナログで作るべきでしょうか?
ご回答は全て網羅的でなくても構いませんし、私の個々の質問以前の段階でおかしな点があればご指摘いただければ大変ありがたく思います。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

贈与とは、「あるものをやります。もらいます。」という契約です(口頭でも可)。
ご質問から察するに、一旦息子さんにお金を渡し、それをあなたが息子さんから借りるということであっていますでしょうか。
それは、書類云々の前の話で贈与契約は成立していないと思われます。
なお、脱税については事実認定のことになりますし、税務署長の判断となりますので、ここではお答えできません。

竹中公剛
できれば、111万円を贈与して、贈与契約書・申告書を税務署に出してください。
110万円以下にするので、心配をすることになります。
そうすれば、名義預金になることはないと考えます。
考えてください。
【土谷先生】ご回答ありがとうございました。はい、その通りでして、親→子(贈与)してから子→親(預ける:貸す)を同じ年の内に完結させるので考えています。これは「贈与が成立してから賃借している(親の預金が子どもの債権に変わった的な)ことになるのではと考えましたが、間違いでしょうか?そもそも贈与が成立していませんか?
【竹中先生】ご回答ありがとうございました。相続時精算課税方式を選ぶなら申告自体は110万でもしなければだな、というつもりではいましたが、あえて少額でも贈与税払う方が良さそうなのでしょうか。さらにケチな質問で恐縮ですが、それは例えば110万と10円(\1,100,010-)を贈与して贈与税を1円だけ(?)納めるのでも効果は一緒でしょうか?
思いのほかに質問詰め込んでしまい失敗だったかと反省していたので、ご回答いただけただけで大変ありがたく感謝申し上げます。もしよろしければ、合わせて教えていただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
申し訳ありません。
竹中の意見は的外れでした。
本当に申し訳ありません。

実質的な判断となりますので、贈与とはみなされないと考えられます。
あれから思い切って税務署に電話してみたところ、「(預ける)条件付き贈与契約書の一枚で済む」(税務署)と、「贈与になってない」(電話センター)との回答で、混乱してしまいました。
ところで私も間違いがあったようで、相続時精算課税で110万以下の贈与は申告不要(←改定後の贈与)だそうですね。しかも金銭のみ(不動産などでない)の贈与は印紙も不要なんですね。。(AIに騙されまくりました。。)
もし思うところあればコメントいただけたら幸いですが、無くても大丈夫で(もうこの線は諦めようかと思い始めて…いま)す。税理士の先生直々にご回答くださり誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年07月16日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。