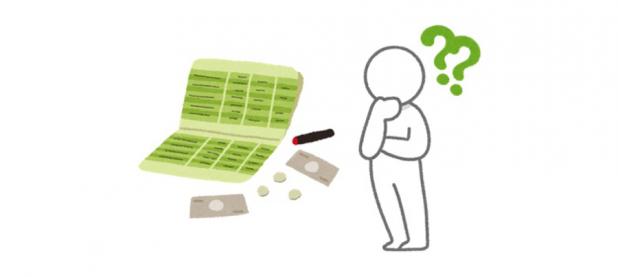不動産の親族間取引について
上記質問をさせてください。
親の持つ不動産を生前から買い取っていくことを考えています。
親個人が所有する不動産を、子の経営する会社で買い取る場合で質問です。
例えば築30年ほどの木造アパートを買い取る場合、耐用年数を過ぎた物件として路線価での土地価のみでの取引を行う事は、所謂「社会通念上適切な価格」として矛盾するのでしょうか。
理屈で考えると問題はなさそうではあるのですが、実際にこの価格設定方法で、贈与対象となってしまった事例などはありますか?
税理士の回答

相続税法第7条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす旨規定しています。そして、「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」(平成元年3月29日付直評5、直資2-204の国税庁長官通達。以下「本件個別通達」という。)の第1項本文は、土地及び家屋のうち、個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する旨定めています。この「著しく低い価額」の解釈については、その対価に経済的合理性がないことが明らかな場合をいうものと解されており、その判定は、当該財産の価格形成に関する諸要素を勘案して、社会通念に従い、時価と当該譲渡の対価との開差が著しいか否かによって行うこととなります。もっとも、所得税法施行令169条のように基準がないため取引上の指針がない状況であり、例えば土地については相続税路線価評価が必ずしも是認されるわけでもありません。ところで、建物については、固定資産評価基準に従って算定された固定資産税価格が適正な時価と認めた裁決があります(国税不服審判所平成24年8月31日。建物の固定資産税評価額は、固定資産評価基準に基づき、木造家屋及び木造家屋以外の家屋の区分に従い、各個の家屋について評点数を付設し、当該評点数に評点1点当たりの価額を乗じて求める方法によるものとされ、各個の家屋の評点数については、当該家屋の再建築費評点数を基礎とし、これに家屋の損耗の状況による減点を行って付設し、家屋の状況に応じ必要があるものについては、更に家屋の需給事情による減点を行うものとされていますが、このような固定資産評価基準が定める家屋の評価方法は、特段の事情のない限り、適正な時価と認めることができるとされました。)。ちなみに、建物の固定資産税評価額は再建築価格の20%まで下がり、その後は据え置かれますので、評価額が0となることは基本的にありません。いずれにしても更正処分を受けないためには、譲渡にあたっては、事前に不動産鑑定を取得した方が望ましいといえます。
ご丁寧にありがとうございます。
昨日追加質問を書き込んだはずだったのですが、うまく書き込めていなかったので再度投稿させていただきます。
親子間の売買なので、「一定の法的根拠に準じた」価格での取引というのは前提として、お互い、できるだけ安く売買したいという思いはあります。
根拠に関しても、路線価であったり、固定資産税評価額であったり、不動産鑑定士による鑑定額であったりとその間にもある程度の乖離があるところが難しいと思います。
木造30年 ある程度綺麗に使われていて、入居もしっかりとしているアパートを売買する場合
おそらくは路線価による評価額が最も安い価格になるのでは?と考えています。
その上で、上記物件を路線価のみ、例えば1500万で買い取り、税務調査時に「それは2000万の価値がある」と判断された場合。2000万-1500万の500万分が贈与対象になるという認識でよろしいでしょうか。
そうなった場合の総支出は、1500万+500万の贈与税分になると思います。
不動産鑑定からの売買をした場合、不動産鑑定評価額が1800万だったとして(上記条件であれば不動産鑑定士評価額の方が路線価より高くなると考えました)、不動産鑑定料金も合わせると、2000万近い出費になってしまいます。
一定の根拠を持つ、路線価での売買を行った上で、お咎めなしなら良し、調査が入って、贈与分は支払ったとしてもそれほど乖離があるはずもないので、その場合は贈与対象分の税を支払う。というスタンスで問題ないでしょうか?

まず前提としまして、上記通達制定の趣旨は、「最近における土地、家屋等の不動産の通常の取引価額と相続税評価額との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の公平を図るため、所要の措置を講じるもの」でありますので、通達は、相続税評価額(例えば、土地についての相続税路線価)での取引を許容しておらず、むしろそのような取引を牽制しております。もっとも贈与税を課されるのは、「著しく低い価額の対価」(相続税法7条)の場合ですので、あくまで相続税路線価による評価が、当該要件に該当するかどうかを検討することになります。これについて、東京地判平成19.8.23判例タイムズ1264号184頁は、「相続税評価額は,土地を取引するに当たり一つの指標となり得る金額であるというべきであり,これと同水準の価額を基準として土地の譲渡の対価を取り決めることに理由がないものということはできず,少なくとも,そのようにして定められた対価をもって経済合理性のないことが明らかな対価ということはできないというべきである。」「相続税評価額と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として土地の譲渡が行われた場合は,原則として「著しく低い価額」の対価による譲渡ということはできず,例外として,何らかの事情により当該土地の相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており,それが明らかであると認められる場合に限って,「著しく低い価額」の対価による譲渡になり得ると解すべきである。もっとも,その例外の場合でも,さらに,当該対価と時価との開差が著しいか否かを個別に検討する必要があることはいうまでもない。」としています。実務的にはこれを根拠に相続税路線価に基づく評価を譲渡対価にしているケースも見受けられますが、一つの下級審の事例判断であり、また上記の通り、通達上の扱いとは異なりますので、課税リスクは常にあり得ます。よって推奨できるという方法ではありません。なお、上記東京地判を参考に路線価を用いる注意点としては、①路線価の価格時点は1月1日ですので、路線価を用いる場合でも取引時点における時点修正が必要です。これは不動産鑑定士による査定等が必要になります。②上記東京地判を前提にしても例外的に贈与税の課税がされることがあります。仮に贈与とされた場合の「当該財産の時価」(相続税法7条)は、課税庁が不動産鑑定を取得した上で課税してくる可能性があります(上記東京地判もそうです。)ので、事後的に贈与とみなされる差額(当該時価と譲渡対価との乖離)について事前に予見できません。また、③上記通達2(注)では、「その取引における対価の額が当該取引に係る土地等又は家屋等の取得価額を下回る場合には、当該土地等又は家屋等の価額が下落したことなど合理的な理由があると認められるときを除き、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるものとする。」とされていますので、取得価額の把握も必要になります。さらに、④贈与とみなされた場合は、贈与税に加え、無申告加算税等の処分が賦課される可能性がありますので、単純に贈与税相当額の加算では済みません。当然ながら課税庁が路線価取引を特段問題にしないという場合もありますが、いずれにしても、上記①ないし④を考慮しつつ、路線価で評価するのかどうかをご判断した方がよろしいでしょう。
判例まで丁寧に説明していただきありがとうございます。
上記リスク等をしっかり考慮して、価格設定を行おうと思います。
全くの余談ですが
同水準の価額を基準として土地の譲渡の対価を取り決めることに理由がないものということはできず,少なくとも,そのようにして定められた対価をもって経済合理性のないことが明らかな対価ということはできないというべきである
判例の文面ですが、ものすごく難解な日本語に感じてしまいました。
税理士の皆さんはなれていらっしゃると思いますが、しばらく文章を解読するのに時間がかかってしまいました。

確かに判例の言い回しは難しいですね。またなにかあればご投稿ください。
本投稿は、2021年02月01日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。