相続税申告上の「訴訟中の権利」の価額について
実際の相続税の申告で、「訴訟上の権利」を評価されたり、或いは、税務調査に関与された方のご経験や訴訟上の権利の評価の考え方や状況をご教示いただければ有難いです。
当方の状況は次の通りです。
自宅及び別棟の商業施設の計2棟を新築したのですが建築、設計・監理の不具合があり、工務店・設計・監理者に対して東京地裁に損害賠償請求の訴えを起こしました。その後、第一回期日前に父が病気で亡くなりました。
相続税の申告に際して、訴訟中の権利の評価として、税理士から以下の通達しか依拠すべきものが無いとして、申告方法が提示されています。
財産評価基本通達210(訴訟中の権利) 訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。
(申告方法)
当初申告においては損害賠償請求権を相続財産に計上せず、申告後に訴訟の判決が確定した時点で自ら修正申告・納税を行う方法です。留意事項は増加税額分について、納付期限である日の翌日から自主修正までの期間(最長1年)について延滞税の負担が生じる点です。
そもそも、相続時の時価が財産評価額となるべきであり、通達もそのように記載と理解できます。しかし、相続時には裁判の第一回期日も開かれていませんし、相続時の評価は、誰もできないし、第三者に転売もできないから、相続時申告上で、ゼロ評価とせざるを得ないと思われます。相続後は、訴訟継続も、取り下げも、和解も、控訴も、調査費用を掛けた調査の実施も、相続人の裁量であり、その結果、判決、和解で被告から入金があるかもしれません。それにもかかわらず、上記申告方法は、訴訟確定時の金額を申告時に遡るといった方法で、その結果、延滞税まで支払いということです。
税理士の回答
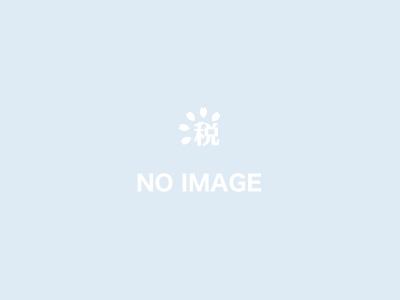
安島秀樹
損害賠償請求額を権利の価額にしたらどうですか。延滞税はかからなくなると思います。
本投稿は、2020年07月24日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






















