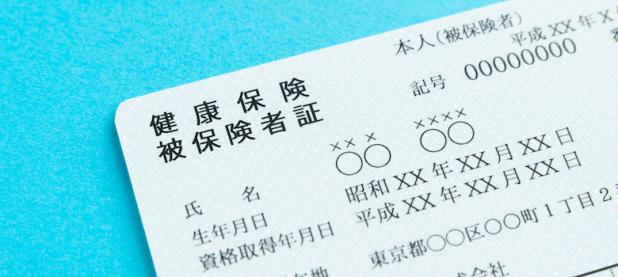リフォームに要した費用の会計処理について
現在サラリーマンをしておりますが、副業として不動産経営の準備を進めており、中古の戸建てを購入しました。
この戸建てをリフォーム(現在進行中。10月末までに完了予定)したうえで、11月から賃貸に出す予定です。
リフォームはDIYで進めており、ホームセンターで資材等を購入しているのですが、この資材等に掛かった費用について、どのように会計処理すればいいでしょうか?
注意点等もあればあわせて教えていただけると幸いです。
税理士の回答

リフォームにかかった費用は、建物の取得価額に加算する形で建物勘定に計上します。具体的には、購入したもともとの建物の価額とリフォームに要した資材費などを合算して、その合計額を建物の取得価額として扱います。この取得価額は今後の固定資産台帳に記載され、減価償却の対象となります。
不動産賃貸業が開始されると、その建物に対して減価償却を行う必要があります。減価償却は、建物の取得価額を耐用年数にわたって按分して費用として計上する方法です。戸建ての場合、法定耐用年数は木造建築なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年など建物の構造によって異なります。
中古の場合、耐用年数はもっと短くなります。
中古不動産の耐用年数は、以下の計算式で求めます:
残存耐用年数 =(法定耐用年数 - 経過年数) × 0.2 + 経過年数の2分の1
例:築20年の鉄筋コンクリート造りの住居の場合
法定耐用年数 47年 - 経過年数 20年 = 残存耐用年数
残存耐用年数 =(47年 - 20年)× 0.2 + 20年 × 0.5 = 14年
例:築15年の木造建物の場合
法定耐用年数 22年 - 経過年数 15年 = 残存耐用年数
残存耐用年数 =(22年 - 15年)× 0.2 + 15年 × 0.5 = 10年
リフォームに使った資材の中で、その価値が明らかに1年間に満たないと判断されるものや工具などの消耗品費は、取得した年度の経費として処理します。しかし、大部分のリフォーム費用は資本的支出と見なされることが多いです。
ありがとうございます。
追加で2点教えてください。
・賃貸を開始するまでの間は、リフォームにかかった各費用を建物として計上→賃貸を開始後、建物に計上した合計額を元に減価償却を行う、という理解であってますでしょうか?
・リフォームすることによって耐用年数に影響は有りませんでしょうか?(耐用年数が伸びるなど)

賃貸開始までの間の費用処理について
はい、おっしゃる通りです。賃貸開始までの間にリフォームにかかった費用は、資本的支出として建物の取得価額に加算します。そして、賃貸を開始後は、この取得価額を基に減価償却を行います。これはリフォームが建物の価値を増加させるため、資本的支出として処理されるからです。
具体的には、リフォームに要した費用は建物の勘定科目に計上し、その合計額を取得価額として減価償却を行います。取得価額は建物の耐用年数に基づき、法定耐用年数に従って減価償却が行われます。
リフォームによる耐用年数への影響について
リフォームやリノベーションを行った場合でも、法定耐用年数に影響はありません。つまり、リフォームをしても法定耐用年数がリセットされたり延長されたりすることはありません。
リフォームが大規模な補強工事であっても、建物自体の既存の法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。ただし、リフォーム費用自体は新たな資本的支出として、それに応じた耐用年数(通常は建物の残存年数)で減価償却されます。
本投稿は、2024年09月10日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。