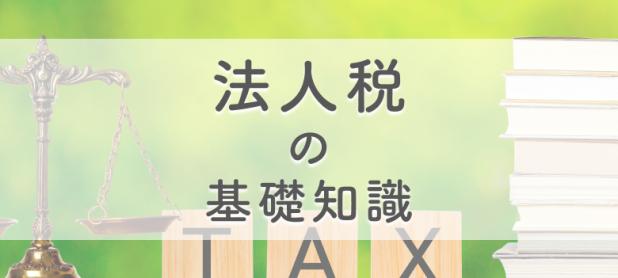電子取引における電子データの保存について(交付側)
令和4年1月1日以降、電子取引で授受した電子データは、受領した側で電子データで保存することが義務となるのは分かりました。
交付した側も電子データで保存することが義務となるのでしょうか?
交付した側も義務となる場合、書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信した場合、書面と電子データのどちらを保存するのでしょうか?
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この法律に関しては、QAを中心に、現在、研究中ですが、私が確認している限り、QAでは、交付者側における、電子取引情報の保存には触れていないので、その必要性はないと考えています。
一方、令和5年10月以降に施行予定の、消費税のインボイス制度においては、交付者側も、電子インボイスを発行した場合には、その保存を求めているので、その時には、この法律には基づきませんが、消費税法に基づき、電子保存する時代が来るものと思われます。
金平先生ご回答ありがとうございます。
電子取引を行った場合、電子データを保存する義務があるのは受領した側であり、
書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信=電子取引に該当しますが、交付した側は電子データを保存する義務はなく、原則どおり、書面での保存。ただし、電帳法4②を適用していれば、電子データで保存することが可能。(改正されて税務署への事前承認が不要)と、いうことですね。
大変勉強になります。
確かに、仰る通り、そのルートもありますね。
ただし、自社作成で保存義務があるのは、写しがある場合、とされているので、写しがなければ、保存義務がない、とも読めます。
一方、インボイス制度施行以降は、電子インボイスは、保存しなければならなくなります。
国税庁が公開している「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のサンプルをみると、第5条「取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、保存サーバ内に△△年間保存する」とあります。
やはり、交付(提供)した側も電子データで保存する必要があるのではないでしょうか?
また、自己が一貫して電子計算機で作成した書類の写しを電帳法4②を適用して電子データで保存している場合、電子取引(電帳法7)でも保存すると、二重保存にならないでしょうか?
「作成(電帳法4②)と「交付(電帳法7)」は、別個で保存すべきなのでしょうか?
すみませんが、来年施行で義務化されるのは、電子取引の方で、そちらを優先的に調べているので、一貫電子計算の方までは、まだ、理解が及んでいないです。
また、規定のサンプルについても、そのような文言があることは、今、初めて認識しましたが、それは、あくまでもサンプルなので、それが、法律に基づく内容なのかどうかまでは確認できていないので、現時点では回答できません。
申し分けないです。
私の認識誤りでした。
電子取引の方のQA上も、明確に記載されていました。
つまり、電子取引の定義の中の、取引情報の定義に、おいて、交付する、という文言があり、電子取引情報のみで、請求書等を提供する場合には、交付者側でも、7条に基づき、電子的保存が必要と読むことができます。
電子的に請求書を送っているクライアントが少なく、受ける立場のことばかり考えており、全く意識できておらず、恐縮ですが、いい気づきを頂き、ありがとうございます。
根拠条文の違いにより、別個保存のご質問もありましたが、個人的には、それはないのではないかと思いました。
まず、7条の電子取引に該当する場合は、データとして保存が義務です。
該当する取引情報は、例外なく、7条に基づくルールに従い、電子保存が必要です。
一方、4条②は、電子保存は、義務ではなく、紙との選択となります。
そして、電子保存(COM保存を除く)の場合の保存のルールは、OA帳簿書類関係版の、問7の通りですが、書類の場合の要件は、7条保存ルールよりも甘いと読めます。
つまり、7条ルール保存をしていれば、4条②の保存ルールは、当然のように充たすのであって、別々に保存を義務付けるものではないのではないか、と考えました。
いかがでしょうか?
国税局電話相談センターに問い合せてみました。
(税理士の先生方は問い合せが出来なかったと思いますので)
令和4年1月1日以降に電子取引を行った場合、交付する側も受領する側も電子データで保存するのが義務となる。とのことです。
また、交付する側の話となりますが、同じ取引情報の物であっても「作成」と「交付」は別個で保存する必要がある。とのことです。
【例】
請求書を書面で出力し、控えとして保存(※)。
その書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信した場合どうなるのか?
(※)控えを電帳法4②の適用を受けて電子データで保存していても同じです。
控えを作成した記録として書面を保存。交付した記録として電子データを保存。
同じ取引情報の物であっても目的が異なるため、別個で保存する。ようです。
申し訳ありません。上記の文章は誤りです。
国税局電話相談センターに問い合せてみました。
(税理士の先生方は問い合せが出来なかったと思いますので)
令和4年1月1日以降に電子取引を行った場合、交付する側も受領する側も電子データで保存するのが義務となる。とのことです。
また、交付する側の話となりますが、同じ取引情報の物であっても「作成」と「交付」は別個で保存する必要がある。とのことです。
【Q】
請求書を書面で出力し、控えとして保存。
その書面を電子データ(PDFファイル)に変換し、電子メールで送信した場合どうなるのか?
【A】
・控えを作成した記録として書面を保存。
(電帳法4②を適用している場合は電子データを保存)
・交付した記録として電子データを保存。
同じ取引情報の物であっても目的が異なるため、別個で保存する。
電子取引情報の交付側も7条として電子保存する件は、すでに訂正済みですが、その後のことは、法律が違うからそのような結論になることは理解もできますが、現実的ではないなとは感じましたし、負担が少なくなるような運用方法を検討する必要があると思いました。
ただ、既に、上記のご回答を受けられているので、一定の結論を得られたようなので、ここでの議論はやめておきます。
お手数おかけしました。
訂正ありがとうございます。
ちなみに、訂正後の文章を読んで思ったことは、印刷した控えを、データ化され、取引相手には、そのデータ化された請求書をデータのみで渡される、という質問だったので、そのような回答になった可能性もあるのではないか、とも考えました。
なお、4②は、電子計算機でデータとして作成した書類関係の保存の法律であって、紙からデータ化されたものは、4②の対象ではないのかと思いました。
自社が発行するものを書面に印刷して、自社の控えとしているのなら、作成した証として書面を保存し、取引先への交付を電子で行ったときは、交付した証として電子データも保存。
同じ取引情報を保存することになるが、保存の目的が違うため、二重保存とはならない。という回答でした。
交付を電子で行った後、書面を廃棄してても電子データも保存しているはずだから確認できる。と保険を掛けているのかな、と思いました。
国税庁のQ&Aは受領した側のことしか載っていないため、交付する側のQ&Aも載せて欲しい。とは伝えましたが、
電子取引のデータ保存の義務化は、負担でしかありません・・・。
個人的に思うは、紙で一旦、出力されるので、そのような回答になるのだと思います。
一方、請求書について、パソコンで作成されると思いますが、それを、データとして、直接、データとして送信すれば、紙の控え、という概念はなくなるので、控え作成と、送付、という議論には分かれないのかと思います。
また、先ほども、記述した通り、紙で出力したものに、何か手作業を加えたものを、PDFなどデータ化した場合には、そのデータ自体は、書類控え、としてオリジナルデータではないので、4②の議論ではなくなると思います。
そうなると、スキャン関係が関係してくるのかもしれませんが、スキャン関係は、未確認なので、これから研究してみます。
それにしても、おっしゃる通り、わかりづらいし、面倒だし、現場や実務を知らない役人が、よくこんな法律を作ったなと思います。
金平先生ありがとうございます。
国税局電話相談センターの担当者の「控え作成」と「送付」は別個に保存する。という回答を踏まえると下記になるのかな、と思いました。
①控えを書面、送付を電子 → 交付側は書面と電子の両方を保存。
※書面を手書き修正した場合、交付側は手書きした書面を保存またはスキャン保存。また、送付を電子で行った場合は電子も保存。
②控えをデータ、送付を電子 → 交付側はデータと電子の両方を保存。
③控えを保存していない、送付を電子 → 交付側は電子のみを保存。
う~ん、何が正解なのか疑問点だらけですね。
交付側の対応について引続き情報収集したいと思います。
本投稿は、2021年09月02日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。