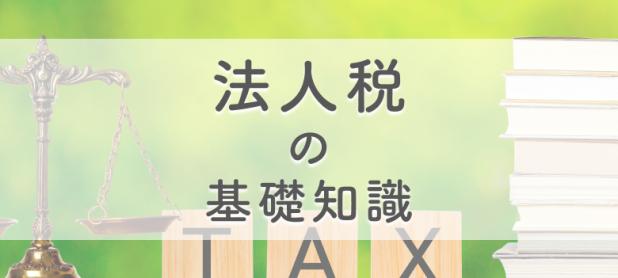生産緑地の納税猶予
生産緑地で地主が納税猶予を受けていたと思われますが、亡くなった後相続人が何年も納税猶予を申請していなかったみたいです。
しかし固定資産税の金額は今までと同額しかこなかった為、その金額を払い続けていたらしいのですが、納税猶予申請していないと本来の違う税額となるのでしょうか?
亡くなってから3年程度経っていますが今からでも申請は出来るのでしょうか?
回答お待ちしております。
税理士の回答

竹中公剛
しかし固定資産税の金額は今までと同額しかこなかった為、その金額を払い続けていたらしいのですが、納税猶予申請していないと本来の違う税額となるのでしょうか?
亡くなってから3年程度経っていますが今からでも申請は出来るのでしょうか?
おはようございます。
納税猶予は、税務署で・・・の問題です。
下記参照してください。
固定資産税は・・・役場です。
問題ありません。
心配なら・・・役場に・・・匿名でも構いません。
聞いてください。
宜しくお願い致します。
猶予を受けていた人がなくなった時点で・・・猶予を受けていた税額は・・・免除されます。
No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
[平成31年4月1日現在法令等]
1 特例のあらまし
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページのホーム画面「関連サイト」の「路線価図・評価倍率表」で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
◎ 免除される場合
(1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
(2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※ 特定貸付け等を行っていない相続人に限ります。

境内生
今回は相続税と固定資産税をわけてご理解ください。先代は農地の相続税課税において納税猶予制度を選択されていたものと考えられます。納税猶予というのは農地について払うべき相続税を猶予している状態です。今回、お亡くなりになったことによって相続税は免除となりました。恐らくその時に免除手続きが行われていると考えられます。土地の登記簿謄本の乙欄で担保設定が外れていれば免除されています。すでに亡くなってから3年を経過したということですから当時、相続税申告の手続きが必要であればその時に納税猶予を受けるか否かという論議がされていますので相続税の申告義務はない状態の財産額だったと考えられます。
次に固定資産税ですが当時と同じ金額が継続されている状態ということですから生産緑地の継続を選択されたということかと考えます。既に生産緑地を選択されていますので特に手続きはありません。念のため農業委員会にご確認ください。結論として納税猶予の手続きは今からすることもありませんし、税額が変わることもありません。
ご回答ありがとうございます。
納税猶予は農家を継続することで相続税を安くしてもらう制度。
生産緑地は、野菜を栽培することで固定資産税を安くしてもらえる制度ということがわかりました。
わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月20日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。