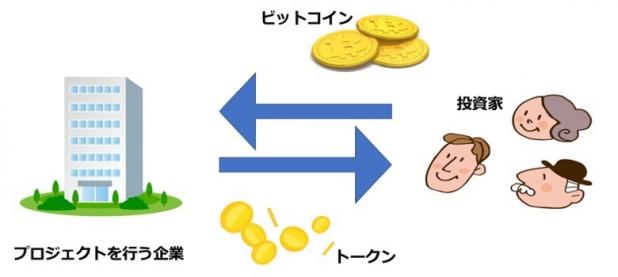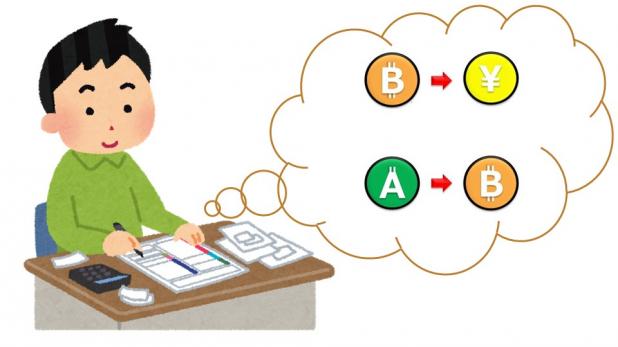暗号資産の売却益と米国株売却に係る為替差損の相殺につきまして
暗号資産で売却益が出ていましたが、一方でドル建てで米国株を売却しましたところ、ドル建てで利益は出たものの、いま円高でこのドルを円に変えると為替差損が生じる見込みです。(米国株購入当時は円貨決済でドル当たり150円でしたが、いまドル当たり143円ぐらいになっているようです)そこで次の3つの疑問が生じました。ご回答いただけますと幸いです
① 仮にドルを円に変えて為替差損が発生した場合、確定申告で先述の暗号資産の売却益と損益通算できるのでしょうか。(どちらも雑所得になるとネットで見ましたが…)
② ①の場合で米国株の売却益(為替差損除く部分)は分離課税で申告できるのでしょうか。また、その際、米国株の売買に伴う支払手数料は雑所得と分離課税のどちらからも差し引くことができるのでしょうか。
③ 仮にドルを円に変えずドルのまま保有した場合、為替差損は考慮せずドル単位の差額を取り、それに年末時点でのドル円価格を乗じて確定申告することになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
①について
共に「雑所得(総合課税)」ですので、「雑所得」内で損益通算できます。
②について
米国株式であっても、国内株式と同様「申告分離課税」です。また、「売買」に伴う支払手数料は「譲渡所得」の経費です。「為替差益」の経費にはなりません。ちなみに、「為替差損」は課税対象外です。
③について
ドルのままであれば「為替差損益」は発生しません。また、個人の場合は、期末換算は行いません(法人のみの規定です)。よって、取得時のレートで評価することになります。
ありがとうございます。
③は取得時、つまり今回で言うとドルあたり150円で計算するのですね。
一度、ドルで売ってそのドルで…
①別の米国株を買ってそれをまたドルで売った場合
②別の米国株を買ってそれを円で売った場合
③年末にもう少し円安(円高)になったタイミングでドルを円に変えた場合
①は変わらずドル当たり150円で評価することになるのでしょうか?
②は最初に米国株を取得した時のドル建て評価額−別の米国株を売る際のドル建て評価額に150円を乗ずることになるのでしょうか?
③は最初に米国株を取得した時のドル建て評価額−その米国株を売る際のドル建て評価額に150円を乗じた金額が譲渡所得に、円に変えたタイミングで為替差損益を計算して雑所得(雑損失)になるということになるのでしょうか?また、この場合、それぞれの支払手数料は譲渡所得と雑所得からそれぞれ差し引くことになるのでしょうか?(雑損失の場合、支払手数料を暗号資産の売却益と損益通算することはできないのでしょうか?)

土師弘之
上記③は、ドルを持っている場合の話ではないのでしょうか。ドル貨を持っているだけではそのドル貨の評価は買った時のレートでしか計算できないため、取得時のレートで計算するという意味です。
貨幣であるドル貨とドル建表示の米国株は全く別のものであるのですが、同じものと理解していないでしょうか。このため、2回目の質問に以下のような矛盾が生じています。
・「一度ドルで売ってそのドルで」・・・一度ドルを売ったら手にはいるのはドル貨以外です。
・①②・・・米国株はドル建であるはずですので、円建では売れません。当然ドル建で売ることになります。
・「②は最初に米国株を取得した時の評価額-別の米国株を売る際のドル建て評価額」・・・最初に取得した米国株(例えば、マイクロソフト株)を売却した場合にはその売却した米国株(マイクロソフト株)の売価からその取得価額を差し引いたのが「譲渡利益」です、別の米国株(例えば、マクドナルド株)の売却価額から差し引くのではありません。
すみません、実はsbi証券を使っていまして、米国株を購入する際や売る際に円貨決済とドル貨決済のどちらかを選べるのです。私は当初、ドルを持っていなかったので米国株を円貨決済で買ってドル建てで所有しております。(その当時のレートがドル当たり150円でした)
③は米国株を売る際に上記のうち、ドル貨決済を選択してドルで売った場合を指しております。sbi口座内にドルで預り金が表示され、そのドルで別の米国株をドル貨決済で購入することができる仕組みになっております。
具体的に例示しますと、例えば日本円で150万円分、円貨決済でマイクロソフト株を買ったとします。当時のレートはドル当たり150円で考えると評価額は1万ドルとなります。(以下、支払手数料は考慮しません。また、取引はすべて年内に完結するものとします)
その後、上記のマイクロソフト株の評価額が2万ドルになった時に、当時のレートはドル当たり100円だと、円貨決済で売ると2万ドル×100で200万円で結果的には50万円儲かったことになりますが、この内訳としては
譲渡所得
(2万ドル−1万ドル)×150円=150万円
為替差損益
(100円−150円)×2万ドル=−100万円
となるかと思います。一方で、円貨決済ではなくドル貨決済で売ると2万ドル手に入り、すぐその2万ドルでマクドナルド株を購入し、そのマクドナルド株の評価額が1万ドルになって円貨決済で売った場合、当時のレートがドル当たり200円だとすると200万円が手に入り、結果、50万円の利益になりますが、この内訳としては
譲渡所得
(1万ドル−1万ドル)×150円=0円
為替差損益
(200円−150円)×1万ドル=50万円
そして、マクドナルド株を買わず、2万ドルをレートがドル当たり150円になるまで保有して売った場合、300万円が手に入り、結果として150万円儲かったことになりますがこの内訳としては
譲渡所得
(2万ドル−1万ドル)×150円=150万円
為替差損益
(150円−150円)×2万ドル=0円
となるという認識でよろしかったでしょうか。

土師弘之
マイクロソフト株の話でいうと、
譲渡所得
(100円×2万ドル)-(150円✕1万ドル)=50万円
※売却時のドルレートは100円です
※ドル建の取引なので「為替差損益」は生じません。
となります。
同様に、
譲渡所得
(150円✕2万ドル)-(150円✕1万ドル)=150万円
※ドル建の取引なので「為替差損益」は生じません。
となります。
「通貨の交換」が生じていないので、「為替換算」(円で評価すること)だけの問題です。
「為替差損益」が生じるのは「通貨の交換」(ドルが円に変わったとかなど)があった場合です。同一通貨ので取引は「通貨の交換」ではありませんので、原則として「為替差損益」は生じません。「原則として」とは例外があることを言います。例外は後で説明します。
つまり、ドル建と円建の取引があった場合及びドル建取引でも取引商品が異なった場合(マイクロソフト株を売却してマクドナルド株を買った場合など)に初めて「為替差損益」が生じます。
「例外である」ドル建取引なのに「為替差損益」が生じる場合とは、
「マイクロソフト株を売却してマクドナルド株を購入した」ということは、「マイクロソフト株を売却してマクドナルド株を買う段階で、売却により得たドルを円貨に交換し、その円からマクドナルド株を買うに必要なドルに交換してマクドナルド株を購入したとする」という処理をすることになっているからです。
このような「外貨建取引基準」があるため、例外として「為替差損益」が発生する場合があります。
よく分かりました。追加質問にもご回答いただき大変ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月24日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。