措置法35条の2(1,000万円の特別控除)申告書記載方法及び適用にあたって
平成21年に取得した土地の譲渡に関する1,000万円特別控除に関し質問がございます。質問にあたっての前提は以下の通りです。
1. 平成21年に居住用財産であるマンション(建物及び土地)を5,000万円で購入
2. 消費税額から建物及び土地に購入代金を夫々3,000万円及び2,000万円按分
3. 平成31年にマンションを6,000万円で売却。売却額は一括しかわからず、建物及び土地それぞれの金額は区分されていない
4. 売却時までの建物に係る減価償却費は300万円である
5. 措置法35条の2(1,000万円の特別控除)適用の要件は満たしている
6. 居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除の適用は受けない
上記を前提とした場合、措置法35条の2の適用を受ける際の確定申告書への記載方法及び売却時における土地に対する売却額の按分方法について質問がございます。
質問1. 確定申告書への記載方法
1,000万円の特別控除を受けるには「譲渡所得の内訳書」というものを提出する必要があるかと思いますが、そのうち項目4「譲渡所得金額の計算をします。」という箇所には、建物及び土地夫々につき1行ずつ使用するのか(合計2行)、それとも一括で1行のみ使用するのかどちらになるのでしょうか。今回の特別控除が土地にのみ関連し、建物には関連しないためどちらなのかと思いました。
質問2. 売却額の按分方法
建物と土地を一括譲渡した場合で、建物代金が区分されていないときは、建物代金を合理的な方法で算定することが必要になるかと思います。また、土地の代金はここで算定する建物代金を使用し間接的に算定することができるかと思います。
タックスアンサーNO.6301では、合理的な算定方法として「土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分」を示しております。
ここで質問なのですが、ここでいう、「土地、建物の原価」を求める際に建物の再調達原価を使用することは許容されるでしょうか。また、される場合には、再調達原価は具体的にどのように算定すればよろしいでしょうか。
例えば、建物取得額から減価償却費を控除したものを再調達原価としてみなして問題ないでしょうか(結果として今回のケースであれば、譲渡益1,000万円のほとんどは土地に係るものになるかと思います)。
税理士の回答
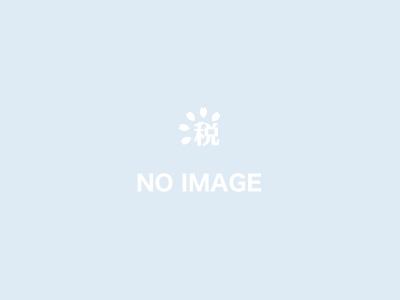
安島秀樹
譲渡所得の内訳書というのは不動産を売買した人がだれでも作成する普通の書類なので一括1行で書いて、1000万円の控除があるなら、特例適用条文のところに租税特別措置法35条の2と書いて、Dの特別控除額に1000万と書いておけばいいみたいです。
建物の原価というのは普通取得費を分けるときに使うものだと思うのですが、売却額を分けるのに使ってもいいのかなと思います。建物の標準的な建築価額表というのをみんな使うのですが、平成27年までのデータしかありません。土地代から類推するやり方とかもあるので、他に使える方法でやったらどうでしょう。
さっそくご確認頂きどうもありがとうございます。
1点目についてですが、例えば、一括で控除前の譲渡所得が1,000万円あるとして、
その内400万円が建物に帰属するもので、600万円が土地に帰属するものである場合には、
Cの差引金額には1,000万円と記載し、Dの特別控除額には控除できる600万円のみ記載することになりそうでしょうか。
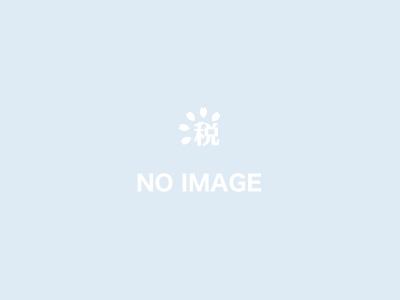
安島秀樹
はい普通そういう書き方をする表になっています。
ご連絡頂きどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年11月10日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




















