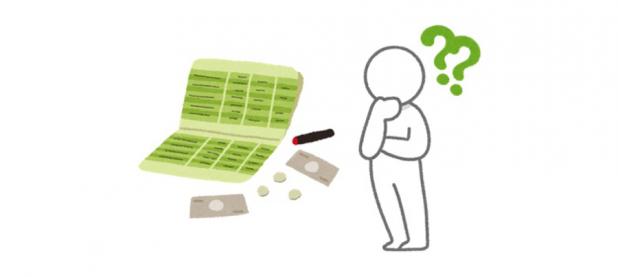3級の精神障害者です。制度を活用し相続税の節税対策したいです。
3級の精神障害者です。
両親とも存命ですが遺産相続するときに備えて、相続時精算課税制度、障害者特定贈与信託などを活用して相続税の節税を考えています。
両親の主な資産は土地と現金で下記のような状況です。
■土地
名義:父(77歳)
面積:約340m2
固定資産税納税通知書の価格欄の金額:1億1800万円
不動産会社による実勢価格の見積額:3億円
活用状況:約100m2分に妹宅が建っており、残り約240m2は駐車場会社に貸し時間貸し駐車場となっている。(駐車場会社から賃料を得ている。年額840万円。)
■現金
名義:母(77歳)
金額:約4000万円
父、母はそれぞれ別の高齢者住宅に賃貸で入居。賃料や生活費は、年金と土地の賃料収入から賄っている。
兄弟は私と妹の2人。妹(36歳)は持ち家で夫と子2人の4人家族、私(40歳)は賃貸マンション暮らしで妻と子1人の3人家族。
両親は、私と妹に公平に遺産相続させたいとの意向。
相続税に障害者控除があることは存じております。また、父と母どちらが先に亡くなるかにもよるかと思いますが、今の関心事としては、余計なことは何もせず現状維持で相続した方がいいのか、何か生前対策を行った方が良いのか知りたいです。生前対策する・しないで、どのくらいの金額差がでそうかも目安を知りたいです。
障害者控除などとは関係なくなりますが、孫を養子にして法定相続人を増やすような方法や、駐車場にしている土地に賃貸マンションを建てる方法は心理的にハードルが高いため考えていません。
年間110万円まで非課税の暦年贈与は既に行なっております。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
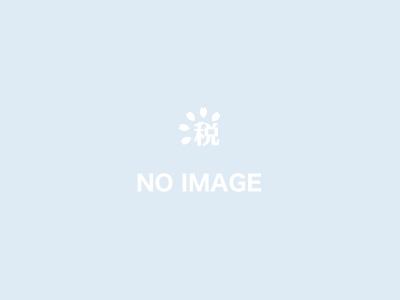
ご相談内容は、相続税がどのくらいかかるのか、相続対策はあるのかということですね。
今回の説明から判断できることは、お父様が亡くなった場合相続税の基礎控除額が、3,000万円+600万円×法定相続人の数(妻と子2名で3名)で4,800万円であることと相続財産が不動産(土地340㎡と現金4,000万円ただし妻名義)であることです。
土地の評価は、路線価方式と倍率方式の二通りありますが、本件土地は固定資産税評価額が1億1800万円とのことですので、路線価方式で評価することになると思われます。
国税庁ホームページ路線価で検索していただくと、財産評価基準書令和5年分路線価等についての「2(注)1令和5年分までの路線価等を掲載」より確認してください。
日本地図→所在地の県をクリックすると、市町村名・大字により所在地が確認出来まして、道路に金額が記載されています。この金額が相続税の1㎡当たりの評価額になり、面積を乗じていただければ財産価額が出ます。初めての方ですと難しいと思われますので、税務署資産課税部門相続担当に相談されるとよろしいかと思います。
固定資産税納税通知書の価格が、1㎡当たり347,000円ですので路線価は40万円前後かと思われますが、市の評価なのでわかりません。
つぎに、利用状況ですが100㎡は妹さんの自宅敷地ということですので、自用地評価が妥当か?(無償使用と思われますが、賃貸借かどうか等の検討が必要)と思われます。
残りの240㎡については、駐車場会社に年額840万円で貸されているとのことですので、賃借権を控除して評価することになります。賃貸借契約書を確認してください。契約残年数が必要になります。こちらも契約書を持参し、相続担当に相談していただければ説明してもらえます。
次に、現金4,000万円です。母名義と記載されていますので、預貯金ということですか?お母様は働いていたのでしょうか?それとも、地代収入の中から蓄積されたものでしょうか?蓄積の経緯を確認してください。それを基に、判断することになると思われます。
相続対策等についてはこれらを判断してから検討された方が良いと思われます。
(参考)
仮に、相続人妻と子二人の場合
財産が2億(葬式費用控除後)で借入金等が無い場合、基礎控除額は4,800万円ですので(2億-4,800万円で)1億5,200万円が相続対象金額となり、この額を法定相続分を乗じまして計算します。
1億5,200万円÷1/2=7,600万円(税率1億以下30%-700万円)で1,580万円、1億5,200万円÷1/4=3,800万円(税率5千万以下20%-200万円)で560万円(×2名分)で、相続税総額は2,700万円となります。
配偶者が半分を相続いたしますと、配偶者の相続税は全額軽減されます。ただし、配偶者に相続税が発生した場合、死亡時の財産に相続税がかかることになります。
1億の財産があった場合、基礎控除額は4,200万円ですので(1億-4,200万で)5,800万円が相続対象金額となり法定相続分を乗じます。
5,800万円×1/2=2,900万円(税率15%-50万円=385万円で2名ですので、770万円となります。
配偶者が相続した場合1,350万円が軽減されましたので、1,350万-770万で580万円軽減されています。
ただし、この分割が可能かどうかはわかりません。相続人の分割協議によりますので、あくまで法律上の説明となります。
詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
いくつかご指摘いただいた確認事項ですが、まず路線価は50万円前後でした。ただ、角地で路線価の異なる道路2本と接しているため、詳細な計算はしておりません。
そして、妹の自宅敷地は使用貸借契約ですが地代が妹から親に支払われています。金額は不明なのですが、相場程度の地代を支払っていると思われます。
駐車場会社との賃貸借契約書はすぐに確認が難しく、契約残年数はわかりませんが、2〜3年契約で更新していく形になっていると思われます。
記載の4,000万円は母の預貯金です。これも母の記憶が定かでなく正確にはわかりませんか、以前母が所有していたマンションの売却代金2000万円と、地代収入の中からの蓄積2000万円ほどかと思われます。
相続時精算課税制度や、障害者特定贈与信託の活用は見当違いでしょうか?
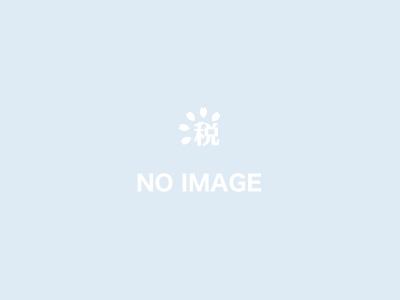
2路線の場合の評価
路線価(奥行価格補正率を乗じた後の価格)の高い路線を正面路線とし、側方路線(正面路線以外の路線)の価額に側方路線影響加算率(普通商業地区0.08普通住宅地区0.03)を乗じて計算した価額の合計額で計算します。
妹さんの自宅敷地の評価
借地権とは、借地借家法に規定する建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃貸借をいいます。したがって、建物の所有を目的とする使用貸借は該当しません。
貸されている土地の評価
賃借権の評価は、地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受があるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなど)と、それ以外の賃借権に分かれます。
賃借権の残存期間に応じ次の掲げる割合を乗じて計算した金額
地上権に準ずる権利として評価する賃借権
①5年以下 5% ②5年を超え10年以下 10% ③10年を超え15年以下 15% ④15年を超えるもの 20%
それ以外の賃借権
上記割合の1/2を乗じて計算した金額
4,000万円の預金について
お母様名義の預金4,000万円の実質所有者は、ご両親様お二人でそれぞれ2,000万円であるということになります。
特例等について
相続時精算課税制度は、相続の時に、贈与で貰った財産を贈与時の価額で、相続財産に加算して相続税の申告をする法律です。
土地の贈与の場合、贈与時より相続の時点で値上がりしていれば良いですが、下がっていれば損しますよね。現金も使っていればありませんのでどうでしょうか?
特定障害者が信託受益権を取得した場合の非課税制度について
信託銀行とよく相談してご理解されて判断してください。
本投稿は、2023年08月24日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。