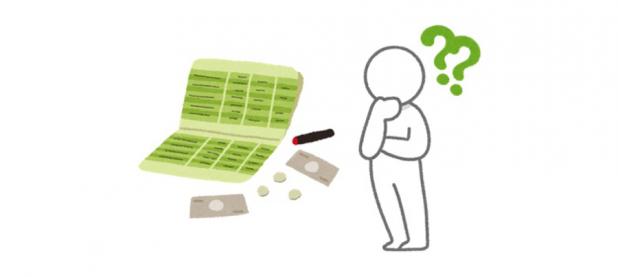遺贈することになりました。
はじめまして。どうしていいのか分からないので教えてください。
今回、私の父が長年交流のある方から遺贈するつもりです。といわれ、
現に公証役場に出向き公正証書まで作成してきました。
その方には法定相続人もおらず、国に持っていかれるくらいなら…。と。
遺産は約5000万円ほど、あと残された建物と土地。つまり全財産を遺贈すると
話してもらえたそうです。
とてもありがたい話ではあると思うのですが、そうなると相当の相続税を払わないと
いけなくなると思います。
もちろん頂いたものなので相続税を払うのは当然なのですが、
そのまま指をくわえているだけでは何の対策にもならないので、
少しでも節税出来たらと考えております。
相手方もこちらを全部信用しているのでどのようにしてもらっても構わないと
話しております。今のうちに預金を動かしてもよいとも・・・。
そこで、私は遺贈を受ける息子ですが、妻と子供が3人おります。
今から、贈与税の非課税枠を適用して年間110万円それぞれに振り込みをしておけば
少しでも贈与税が少なくなると考えておりますが、駄目でしょうか?
素人考えで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
また、他にも何かいい方法があれば教えていただけると助かります。
突然空から降ってきたような話で気が動転しております。よろしくお願いします。
税理士の回答

法定相続人がいらっしゃらない場合の相続税の限界税率(最も高い部分の税率)は、
・財産総額が5000万円の場合:15%
・財産総額が7000万円の場合:20%
・財産総額が9000万円の場合:30%
というように、財産総額が増えるごとに税率も高くなる超過累進税率となっています。
さらに、お父様が遺贈で財産を取得された場合には、お父様が負担する相続税は通常に計算する相続税の「2割増し」となってしまいます。
したがって、ご相談者様がおっしゃる生前贈与は相続税の節税対策としては非常に有効です。
遺贈で財産を受け取る方(受遺者)に関しては、相続開始前3年間の贈与は相続財産に戻されてしまいますが、受遺者以外の方への贈与はその後の相続税には一切影響いたしません。
受遺者の方への贈与でありましても、3年経過すれば相続財産に加算する必要はありませんので、受遺者であるお父様を含めて、ご相談者様・奥様・子供さんといった多くの方々に、早めに贈与して頂くことは効果的と考えます。
また、相続税の負担(税率)が上記のように想定されますので、贈与する金額も非課税枠の110万円でなく、お一人当たり200万円とか300万円といったようなスケールで考えて頂いても宜しいと思います。
・贈与額がお一人200万円の場合の贈与税:9万円(実質負担率4.5%)
・贈与額がお一人300万円の場合の贈与税:19万円(実質負担率6.3%)
また、贈与は贈与する人の「あげる」という意思表示と、贈与される人の「もらう」という受諾が必要になりますので、贈与して頂く場合には次の点に注意してください。
・贈与する都度、贈与契約書を作成してください。(受贈者が未成年の場合には親権者であるご両親の合意がある内容の贈与契約書を作成してください。)できれば、その贈与契約書に公証役場にて確定日付を押して頂くと望ましいです。
・贈与する金銭は口座振込等で金銭の移動が分かるようにしてください。
・贈与で振込して頂いた預金通帳は受贈者の方々が管理支配してください。
・贈与税が発生する場合には、贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告納税を行ってください。
以上、よろしくお願いします。
返答内容をうかがって本当にびっくりしました。こんなに丁寧に教えてくれるなんて…。
これからどのように動いていけばいいのかが理解でき、自信がわいてくると同時に明るい気持ちになれました。ありがとうございました。
先生の仰る様にやっていこうと思っておりますが、確認したいことがあります。
私や、嫁、子供に仮に200万ずつ贈与をして、税金を納める前提で、これは我が家の所得に
カウントされるのでしょうか?これによって保険料や住民税が増加してくるものなのか?
それも含めてそのまま遺贈を受けるよりは徳にはなるとは思うのですが、子供手当などの
公的な支援まで止まってしまうことを考えると、110万円までにして申告をしないほうが
徳になることもあるのでしょうか?教えていただけないでしょうか?

ご連絡ありがとうございました。
贈与された財産に課させる税金は贈与税だけになります。
贈与された金銭等はそもそも「所得」にはなりませんので、仮に110万円を超えた贈与であったとしましても所得税も住民税も社会保険料も課税の対象にはなりません。そして扶養親族等から外れることもありません。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年07月18日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。