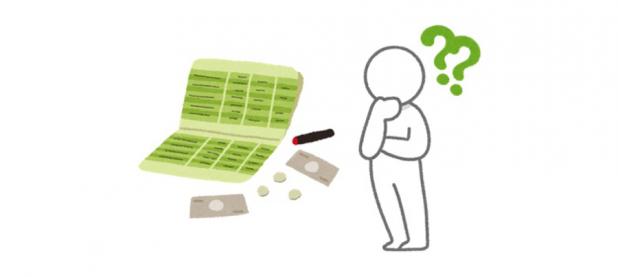相続時精算課税制度を利用した場合の相続発生時の持ち戻しについて
毎年100万円程度の資産を息子に生前贈与したいと思っています。暦年贈与の場合、毎年100万円を10年間贈与すれば相続発生時の7年前までの分は相続財産として持ち戻さなければならないと聞いていますが、相続時精算課税制度を利用すれば相続発生時に1円も持ち戻さなくてもいいということになるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
少し誤解をされていらっしゃるかも知れないと思いました。
相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。相続税を計算するとき、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、全て足し戻して相続税を計算することになります。
ただし、令和5年度税制改正大綱において、相続時精算課税制度も改正が入りました。
これによって、令和6年1月以降の相続時精算課税制度では、基礎控除110万円が創設され、基礎控除110万円以下の贈与財産は持ち戻されないことになりました。この部分は贈与税の申告も不要とされております。
上記参考になれば幸いです。
さっそくのご回答、ありがとうございました。60歳以上の親が18歳以上の子供への贈与となりますが、相続時精算課税制度を今年から利用すれば、今年から毎年110万円以下の額を10年間にわたって生前贈与(計1100万円以下)しても、毎年の贈与額が基礎控除以下なので、相続発生時には一切持ち戻しの必要はないということでよろしいでしょうか? それとも、基礎控除の110万円だけが持ち戻しの必要がなく、残りの990万円分は持ち戻さなければならないということなのでしょうか?
相続時精算課税制度は、累積2,500万円までの贈与が非課税となり、この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできなくなります。
>>相続時精算課税制度を今年から利用すれば、今年から毎年110万円以下の額を10年間にわたって生前贈与(計1100万円以下)しても、毎年の贈与額が基礎控除以下なので、相続発生時には一切持ち戻しの必要はないということでよろしいでしょうか?
→そのとおりです。
基礎控除額と同額の110万円を10年間贈与した後に相続を迎えた場合、暦年贈与は770万円を持ち戻しますが、相続時精算課税制度は持ち戻す額はありません。つまり、基礎控除額以下での贈与であれば確実に相続時精算課税制度の方が節税効果があることになります。
>>それとも、基礎控除の110万円だけが持ち戻しの必要がなく、残りの990万円分は持ち戻さなければならないということなのでしょうか?
→「毎年110万円以下」ですので、贈与が10年間続くのであれば、基礎控除110万円の10年分について、持ち戻しの必要がなくなります。
上記参考になれば幸いです。
さっそくの、ご丁寧なご回答をありがとうございました。おかげさまで、本当によく理解することができました。感謝いたしますとともに、今後ともご活躍されますことをお祈りいたしております。
本投稿は、2024年03月30日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。