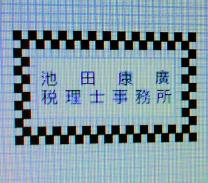遺産相続分配の節税対策
父が亡くなり母・私(長女)・弟の3人が相続人です。
遺言書なし、10月に相続税の申告をしなければなりません。
総額で6200万(土地建物1400万・現金4800万)を分配しますが
第二相続の事も考慮した場合、①~④どれが一番節税できますか。
(生前父が希望していた為、土地はいずれ弟名義にします)
母100%にすると今は相続税0円だけど第二相続の時に大変だと聞いた為
もし今いくらかの相続税を支払っても第二相続で相続税が少ない方が良いと私と弟で判断しました。母に説明する為の資料を作成する予定ですので宜しくお願いします。
①母100%
②母50%、私25%、弟25%
③母 土地建物1400万+現金2000万
私 現金1800万円
弟 現金1000万円
④母 現金3000万円
私 現金1600万円
弟 土地建物1400万円+現金200万円
税理士の回答
お考えのとおり、二次相続を考慮して分割することは、重要なことです。
全額をお母様が相続すれば配偶者税額軽減により今回の相続税はかかりませんが、二次相続では法定相続人が3人から2人になり基礎控除額が減るとともにお母様の元々の財産も加わることで税率が高くなるかもしれませんので、一般的には①以外がよいです。
ただし、お母様の元々の財産、小規模宅地の特例の適否などが不明ですので、最適な分割案を提示することはできません。
遺産分割協議はあくまでも相続人間で行いますが、是非、遺産分割協議のアドバイスも受けられる税理士に相続税申告書作成を依頼してください。
ご回答ありがとうございます。
中田先生、お手数をお掛けしますが最適な分割案をご提示願えませんでしょうか。
母の財産は30万円位、小規模宅地の特例「特定居住用宅地」適応有になります。
④に関しては母次第ですが【配偶者居住権】も考えております。(今、弟名義にして数年後に同居するにあたって自分が一緒に住んで良いのかと不安になっている様子)
ある程度、相続税に関して知っておいた方が税理士さんの依頼をする場合でも言われたまま手続きが進むのが少し不安がある為こうして分からないなりに質問させて頂いております。
遺産相続が初めての事でネット検索しても情報があり過ぎて困惑しております。
第1次相続で財産全部をお母さんが取得し、代償分割でお母さんからご兄弟に現金2400万円ずつを渡す旨の分割協議書を作成し、この内容で相続税の申告しますが、代償分割による現金は支払わないようにします。ご兄弟は実際財産を取得しないのに、相続税を課税されるのは納得できないかもしれませんが、第2次相続の時に未払金として4800万円を債務計上することにより、第2次相続に係る相続税を小規模宅地の課税価格の特例を併用することにより軽減することができます。
一次、二次相続で誰が土地を相続するのか、評価額がいくらなのかが不明のため小規模宅地の特例をどう適用していいのかわかりません。
またお母様の財産額も少額のため、これらを考慮せずに①②について下記のとおり回答します。
①一次相続配偶者の税額軽減により相続税額なし、二次相続合計相続税額200万円
②一次相続合計相続税額70万円、二次相続相続財産額が基礎控除額以下のため申告納税不要
このように①ではないほうがよいということになります。
再度申し上げますが、詳細は相続税申告を依頼する税理士にシミュレーションしてもらってください。
税理士に言われたまま手続が進むような税理士に依頼しないようにすべきです。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂き、弟と検討してみます。
ありがとうございました。
申し訳ございませんが、前回の回答を訂正します。
お尋ねの設例について、納付すべき税額を計算したところ、①第1次相続 母0円 第2次相続 私100万円 弟100万円 ⓶第1次相続 母0円 私35万円 弟35万円 第2次相続 母の遺産額が基礎控除額4200万円未満につき非課税 ③第1次相続 母0円 私406,000円 弟226,800円
第2次相続 母の遺産額が基礎控除額4200万円未満につき非課税・・・と
なります。前回の回答は第2次相続の相続税が課税となる場合に有効です。
申し訳ありませんでした。なお、税額計算については、小規模宅地の課税の特例は反映させていません。また、第2次相続の遺産額はお母さんの第1自相続での取得額としています。
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
前回の回答の方法は節税でなく、脱税と判断される恐れがないとも言えませんので、適用にあたっては十分ご検討いただきますようお願いいたします。
承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年08月08日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。