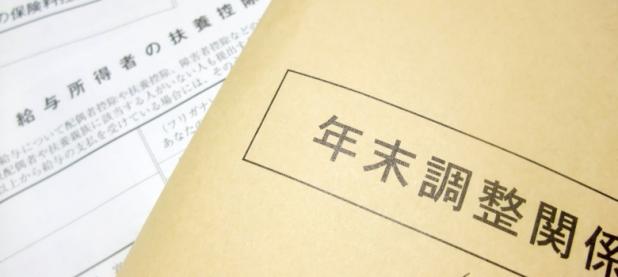R1年扶養控除等申告書を提出しているのに、年末調整をしてもらえません。なぜでしょうか?
お世話になります。
標題の件、R1年扶養控除等申告書を提出しているのに、年末調整をしてもらえません。
私は、A社で2018/12/31まで正社員で働いていました。
その後、2019/1/1から、パート:甲欄で勤務していました。
しかし、2019/10/1から、他の会社(B社)での勤務を開始し、B社がメインの勤務先となりました。
2019/10/1時、B社に、R1年扶養控除等申告書を提出しました。
その場合、B社で年末調整をしていただき、その源泉と、A社の源泉で、確定申告をするものと思っていました。
しかし、B社の人事課から、「A社の源泉がないので、年末調整できません。確定申告してください。」と言われました。
これは正しいのでしょうか?
A社の源泉が間に合わないのはわかっています、どの道確定申告が必要であるということもわかっているのですが、なぜB社で年末調整してくださらないのでしょうか。
また、A社では、今もパートとして勤務しているのですが、2019/1/1の時点で提出したR1年扶養控除等申告書が、そのまま生きているようで、源泉が甲欄で計算されています。
なので、このあと受け取るA社の源泉は、甲欄で作成されてしまうと思います。
上記の状況の場合、私はどうしたらよろしいのでしょうか?
ご教示いただきたくご相談させていただきます。
お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

結論から申しますとB社では、A社分給与を加味した年末調整はできません。B社分の年末調整済みの源泉徴収票とA社分の源泉徴収票とを合算して確定申告をすることになります。
年末調整とは給与所得者に対する年間所得と税額を確定・精算する制度ではありますが、これは勤務先企業が行うことを前提にその企業が把握できる情報のみでしかできません。また、同時に複数の勤務先がある場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1ヶ所しか提出できないことになっています。従って、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出された勤務先しか年末調整は出来ず、かつ、自社で支給した給与分についてしか年末調整の対象にはなりません。考えてみれば当然のことですが、他社の情報などわかるはずもなく、年末ギリギリに賞与が出るなどのこともあります。(退職者の前職分とは異なります)
また、A社分の源泉徴収の件ですが、上記に記したとおり「給与所得者の扶養控除等申告書」は1ヶ所しか提出できませんので、2019/10/1時点でA社には甲欄適用者ではなくなった旨の届出をしておく必要があったことになります。
以上、誤解なきようご理解ください。
福田先生
お世話になって居ります。
早速のご回答ありがとうございます。
そうすると、B社は私の年末調整を行う必要があるということですよね?
B社人事課からは、「A社源泉がないとできない」と言われましたが、それは理由にならないということですものね?
それから、A社ですが、2019/10/1時点で、契約内容の変更に伴い、甲欄適用者ではなく、乙欄適用者になりました。
しかし、A社の人事課からは何も言われていません。
私が何かしないといけないのですか?
契約内容変更も、給与計算も行っている人事課が、乙欄に変更するべきではないのですか?
誤解がありましたらすみません、A社の対応も、B社の対応も不安が残ります・・。

前回の回答について一部誤った部分がありましたので訂正させていただきます。
建前上は、B社の年末調整は、B社が支給した給与とそれ以前に主たる給与として支給されたA社の1月1日から9月30日までの給与が対象になります。それゆえ、B社は「年末調整ができません」と言っているものと思います。
従って、A社は10月1日時点において甲欄適用者から乙欄適用者に変更した時点で1月1日から9月30日までの給与について甲欄適用の源泉徴収票を発行し、質問者様に配布する必要があったということになります。また、別途10月1日から12月31日までの給与について乙欄適用の源泉徴収票を発行し、質問者様はこちらの源泉徴収票とB社の源泉徴収票で確定申告をすることになります。
たぶん、A社の給与担当者が乙欄適用への切り替えをしていない可能性がありますので、念のため指摘された方がよいと思われます。
最後に、A社が上記のような対応をなされなかった場合には、たぶんA社発行の源泉徴収票は1月1日から12月31日までの甲欄適用のものになると思われますので、B社の年末調整未了の源泉徴収票とあわせて確定申告をすれば最終的には精算されることになります。なお、来年分については乙欄適用にしてもらわないといつまでも解決しません。
以上、ご理解ください。
本投稿は、2019年11月21日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。