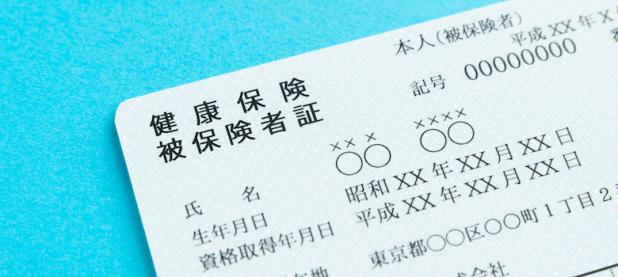勘定科目について
医療法人経理の超初心者です。
手術で使う鉗子等の医療用具の勘定科目について、業界的な面も含めて教えてください。
製品説明等に耐用期間1年または20〜30症例
と言ったものが多く消耗品で処理していますが、
昨今の物価高騰や円安の影響等もあり、10万以上の物も散見されます。
10万以上でも消耗品で大丈夫なのか?
耐用期間1年と言えど、使用頻度によっては2年くらい持つケースもあるようで、世間の病院さまはどのようにされてるのか、お助けください。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

医療法人の経理において、手術用鉗子などの医療用具をどのように処理するかは、以下のような基準や判断が関係します。
1. 消耗品か固定資産かの判断基準
消耗品費として処理する場合
以下の条件に該当する場合、消耗品として処理されるのが一般的です。
- 耐用年数が1年未満である場合
- 購入金額が10万円未満である場合(小額資産として即時費用化)
ただし、医療業界では「使用症例数」での耐用が明記されることが多く、製品説明書等に「20〜30症例」と書かれている場合は、実質的に短期間での消耗が前提とされるため、金額が10万円を超えていても消耗品費で処理することが多いです。
固定資産として計上する場合
- 金額が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の場合は、原則として固定資産として計上し、法定耐用年数に基づき減価償却を行います。
- 医療用具の耐用年数については「医療機器」に該当するものは法律上定められた年数が適用されますが、使用頻度が低いものや2年以上使用されるケースでは固定資産として処理する選択肢も検討できます。
2. 実務的な運用方法
10万円以上の高額医療用具について
以下の点を検討してください
1. 法人内の会計方針
- 例えば、「消耗品費として処理できる金額の上限」を10万円に固定する法人もあれば、柔軟に運用する法人もあります。
- 会計監査が入る場合は、監査法人に確認して一貫性を保つ必要があります。
2. 耐用年数と使用実態の評価
- 製品が「使用頻度によって2年以上持つことが明らか」なら、固定資産計上が望ましいと考えられます。
- 一方、使用頻度が高く1年未満で消耗することが見込まれる場合は、10万円を超えていても消耗品費として処理するケースもあります。
円安・物価高騰の影響に対する考慮
医療用具の単価が高騰しても、業界の慣例や税務上の判断基準を優先します。
- 監査法人の見解や税務調査の際の扱いも考慮して、処理を決定することが重要です。
親身にご教示くださり感謝申し上げます。
大変お勉強になります!
頂いたアドバイスを実務に反映させていただきます。
本投稿は、2024年12月04日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。