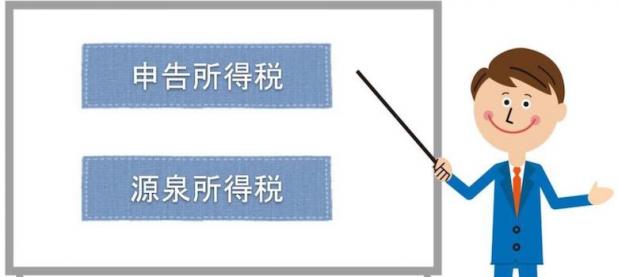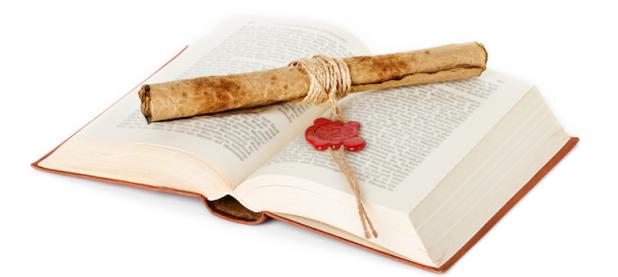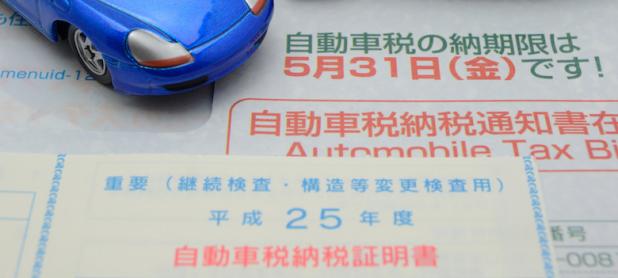宅地と畑を合わせて売却した場合の「居住用財産を譲渡した場合の3000万の特別控除」の適用について
市街化区域にある自宅敷地の半分は宅地、半分は畑として農業委員会に登録して家庭菜園に利用しています。宅地と畑は隣接して一体となっております。宅地部分には築50年ほどの木造家屋が建っておりますが、土地(妻)と家屋(夫)で名義人が違います。
畑は宅地に転用の上で、売却して売却益が出た場合に、「居住用財産を譲渡した場合の3000万の特別控除」は、畑からの転用部分には適用されないと思うのですが、控除額はどのように計算されるのでしょうか。
敷地の半分が宅地だとすると、半分の1500万しか控除されないと考えるのでしょうか。
築50年の木造家屋は償却期間を過ぎていると思うのですが、控除額の計算上、どのような扱いになるのでしょうか。
税理士の回答
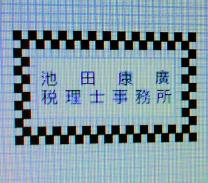
池田康廣
建物が築50年ということは、宅地・畑の所有期間はそれ以上と思います。
そうすると、計算は譲渡価額-取得費(譲渡価額×5%)-譲渡費用=譲渡益(譲渡所得金額)となりますが、この譲渡所得金額を居住用部分と非居住用部分に按分し、この場合は半分ずつに区分します。つまり、この譲渡益(譲渡所得金額)の半分の金額が居住用財産の譲渡として3,000万円の特別控除の対象となります。
回答ありがとうございます。
家屋・宅地・畑(宅地に転用)をまとめて売却した場合、特別控除は、家屋→宅地の順で適用されて、畑には適用がないと思うのですが、その場合の控除額の按分は、固定資産税評価額等の比率で案分されて控除されるのでしょうか。
木造家屋の耐用年数は過ぎているはずですが固定資産税評価額は残っているため、夫所有の家屋部分も譲渡所得の按分に入り、まず夫の譲渡所得が先に控除され、残りが宅地部分の譲渡所得から控除されるとの理解で正しいですか。
畑からの転用部分の譲渡所得に使える税額控除の制度は、何も無いのでしょうか。
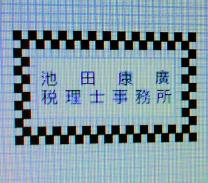
池田康廣
〇 売買契約で宅地・畑(宅地見込地)・家屋それぞれの金額を決めていれば、それによります。固定資産税評価額は市町村が固定資産税を課税するための評価額ですので、時価とはかけ離れていますので、按分の基準とはなりません。売買価額が決定された根拠を売主・買主で協議する必要があります。
〇 居住用財産の特例は原則は建物を対象とした特例であり、控除しきれない場合に宅地部分から控除します。
〇 譲渡直前まで畑として利用しているのであれば、農業委員会などのあっせんによる場合の800万円の特別控除や優良宅地造成に係る税額の特例などがありますが、それぞれ適用要件が定められており、ご質問の内容からみると適用可能な特例はご質問の居住用財産の譲渡に係る特別控除の特例以外にないと思われます。
本投稿は、2023年10月01日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。