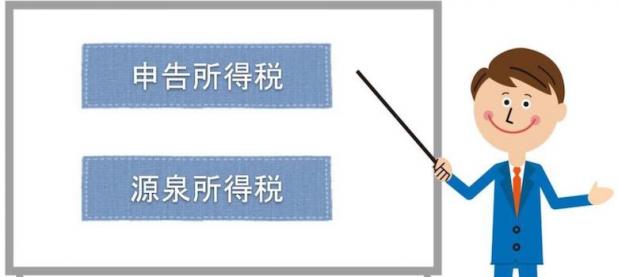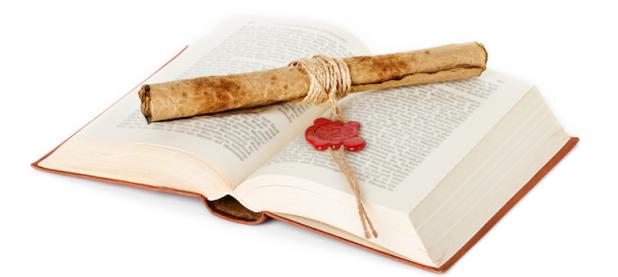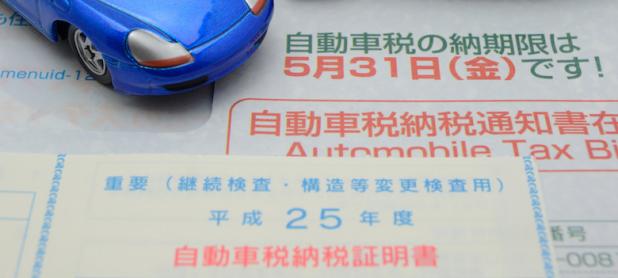転職翌月の支給賞与における所得税計算につきまして
よろしくお願いいたします。
私は会社員で今年11月に転職入社し、12月に2か月在籍分(11月12月)の賞与が支給されました。
賞与の所得税率は「前月の給与額から社会保険料を控除した額」が適用されますが、11月は入社月であり社会保険料が控除されていないため給与額全額に対しての税率が適用=結果的に高い所得税率が適用されています。つまり、所得税が高くなり手取りが数万円レベルで減っています。
11月に控除されていない社会保険料は結局12月で控除されるため、「社会保険料が控除されない所得税率が適用された賞与」は、どこかで調整されるものかと思ったのですが(されてほしい)、これは一般の会社員の場合年末調整でされるものでしょうか。それとも、個別に確定申告なりの対応が必要なものでしょうか。
または、賞与前月に入社する者は被らないといけない損害だったりしますでしょうか。
夏、冬の賞与で発生し得るため、レアケースではないと思ったのですが。
税理士の回答

米森まつ美
転職された会社(現職)に、転職前の会社の源泉徴収票を提出することで、今回11月分(12月に控除された分)の社会保険料も含め、また、賞与から徴収された源泉所得税についても、年末調整により清算されますので、多く保険料や所得税を「被る」(負担、損害?)ことにはなりません。
現職に、前職の源泉徴収票を提出できなかった場合などは年末調整ができませんので確定申告で所得税などの精算を行います。
現職では給与の収入の他、貴方が負担した社会保険料や賞与などで徴収された源泉所得税額が記載された「源泉徴収票」が発行されますので、前職の源泉徴収票の給与所得と併せて確定申告を行うことにより所得税等を清算しますので、年末調整と同様に余計に所得税などを負担することはない、つまり「損害」は発生しないと考えます。
米森先生、ご回答ありがとうございます。
※国税庁におられたんですね、心強いです。
前職の源泉徴収票は、現職での年末調整向けに提出・会社のシステムに登録しました。
いったん安心しつつ、年末調整結果=12月の給与明細?を待ってみることにします。
前職のそれなりの額の冬賞与もらわないで10月末に退職→現職で在職2か月換算の多少?の賞与をもらった(だけど所得税がかなり源泉徴収されてしまっている)ので、それなりに戻ってくる、はず。
※ただ「賞与で社会保険を引いた前月の給与で計算するところを引かないで税率計算したから、年末に修正する」のような細かい修正?を、本当に給与担当がやってくれるのかは心配ではあります。。。何か、簡単な計算ソフトでもあるのでしょうか?
ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
年末調整のソフトは国税庁hp上でも提供しています。
↓
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
ただし、私は(多くの会計事務所もそうだと思います)自己の契約している会計ソフトを使用しているため、国税庁提供のソフトの使い勝手はよくわかりません。
なお、当然年末調整は「手計算」で行うこともできます。
手順としては以下のとおりです。
この手順なども「年末調整のしかた」のパンフレットを参考に進めると良いでしょう
(源泉徴収簿を活用します)
国税庁HPから掲載箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
1 収入金額の集計
前職の給与の合計額 + 現職の給与の額 =給与所得の収入金額
⇒パンフレットP51-59の「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて「給与所得の金額」を出します。
2 社会保険料の集計
前職で引かれた社会保険料(源泉徴収票に記載があります) + 現職で引かれた社会保険料の額 = 控除対象となる社会保険料
3 源泉徴収された所得税(源泉所得税)の集計
前職で源泉徴収された所得税 + 現職で源泉徴収された所得税 = 年末調整により清算される源泉所得税
4 所得控除額の計算と集計
「2」の社会保険料の他、「保険料控除申告書」で計算した生命保険料控除や損害保険料
扶養控除申告書に記載された扶養者の人数等によ扶養控除額や障碍者控除
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書により計算された、基礎控除や配偶者(特別)控除額
これらを集計します。
※ これらの「所得控除」の計算が一番大変と思います。
5 課税所得金額の算出
「1」で計算した給与所得金額 - 「4」の所得控除額 = 課所得金額 を算出
6 年税額の算出
「5」の課税所得金額に税率を掛け、「年調所得税額(定額減税前の所得税額)」を算出
年調所得税額 - 年調減税額(定額減税額) = 年調減税額控除後の年調所得税額
この税額がプラスの時には、102.15%を掛けた金額が「年調年税額」になります。
マイナスの時は 年調年税額は0円となります。
(定額減税の残りがある場合は、令和7年中の市区町村の給付金の計算の基になります)
7 源泉所得税額と年税額との清算
「6」の年調年税額と「3」の源泉所得税額との差額を算出し、源泉所得税額が多い場合には還付(年末調整超過額)になります。
本投稿は、2024年12月12日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。