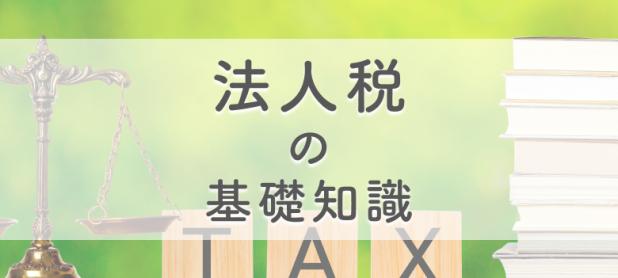認可地縁団体が寄付を受ける場合にかかる税金について
認可地縁団体が、個人から、現金(土地等の不動産でなく金銭のかたち)で寄付(2000万円)を受けることになった場合にかかる税金について教えてください。
寄付を受ける認可地縁団体では、税法上の収益事業は実施しておりません。
認可地縁団体にかかる法人税については、「公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税」と認識しております。
上記のケースのように収益事業を行っていない認可地縁団体が現金2,000万円の寄付を受けた場合、
①法人税(国税)…(収益事業を行っていないので)非課税
②法人地方税 …(収益事業を行っていないので)均等割のみ課税、申請による減免措置等がある
となると考えてよろしいのでしょうか?
当方、地縁による団体(町内会等)に寄付の申し出があり、双方に税金等の負担が発生しない方法を模索しているところです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

人格なき社団として社団としての実態の現状を踏まえて、
社団としての実態が無い、個人に過ぎない、とされれば、その代表の個人の方のものに。当然、その方が贈与税申告を期限内にする必要があります。
法人の場合は、受贈益が生じるのでその期のみ、法人税、法人事業税、均等割り等の負担が生じるのが原則。ただ、実態として収益活動は無い。
考え方として、これが無税で良ければ、贈与、相続の租税回避ができるため、理屈は様々ですが、税の負担は必ず生じます。これを避ける、といったアプローチは現実的には極めて困難かと存じます。しばらくしてから、不意の税負担等生じる恐れがあり、その際、手元現金が無かった場合は、構成員が負担するのか、どうか、といった極めてシリアスな事態も想定されますので、避けてはいかがでしょうか。
例外的に公益性が組織として担保されている公益社団法人、自治体等への寄付の場合以外は。

ご質問のとおりで、問題ないと思います。
認可地縁団体は、地方自治法の規定の認可により、法人化が認められていますので、寄付を受けた現金は、その団体の資産となります。

認可地縁団体は、法人格を有するのですね。この点は確認が遅れ、失礼いたしました。
ただ、そもそも総有となっているものを所有することは想定されていても、その後、多額の寄付を受けることは想定していないのかと存じます。
公益法人等においても非課税贈与とされるためには、組織体制等も求められ、初めて適用されるものですので、文書回答を求めてはいかがでしょうか?
趣旨に立ち返ると、改めて、税務上のリスクのある処理かと存じます。課税されないのはおかしいですから。
相田先生、富樫先生、回答をありがとうございました。
いただいた回答を踏まえまして、素人ながらさらに掘り下げてみたところ、法人税でほぼ非課税の取扱をされても、贈与税で課税されるようであることがわかりました。(相続税法第66条 人格のない社団又は財団等に対する課税 が、これにあたるかと。)
これによると、認可を受けていない地縁による団体であれば(人格のない社団ですから)、一般的な贈与税を課税されることになりますが、
同条第4項によると「持分の定めのない法人」について「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」以外(=相続税又は贈与税の負担の減少がおよそ考えられない善意の第三者からの贈与等(寄附)の場合)には、贈与税は課税されないと読み取ることができるかと考えました。
とすると、認可地縁団体が「持分の定めのない法人」の要件を満たし、且つ(相続税法施行令第33条第3項に基づき)「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」以外のケースであれば、非課税となると考えてよろしいのでしょうか?
素人考えでは、自らが帰属する地区のために役立ててほしい、という意図での寄付金(寄付によって町内会から自身が特別な利益を得ようという意図はないもの)は善意の第三者からのものにあたるのではないかと感じており、留意しなければならない点は多分にあるものの、うまく取りはからえないものかと思っております。
再度の質問で恐縮ですが、専門の先生から見たご意見を頂戴できれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
基本的な考え方は問題ないと思います。
認可地縁団体は、認可されていることから、相続税・贈与税の負担が不当に減少はないと思います。
逆に過去は、法人化されないために、個人名義の資産が相続で問題になったことを考えれば、意図的な脱税目的でなければ、問題はないと思います。

基本的なスタンスとして、誰かに迷惑をかけることは出来ない。
ここからスタートすべきかとは存じます。
将来、贈与税の負担が生じる恐れがある。であれば、よりリスクの少ない別のアプローチを検討されてはいかがでしょうか。

その上で、合致する条文はありませんが、私の想定する事象は以下です。
資産家Aが認可地縁団体に1億寄付した。
認可地縁団体で子息Bが理事を務め、Bが代表を務めるC会社に業務板託した。受託料は1億。
であれば、租税回避ができます。
これは極論ですが、程度の差はあれ、地縁団体であり、管理責任者を設けて、何時、幾ら、何のためにといった説明資料を整理、保管していくというのも現実的では無く、もっと緩やかな組織運営となるのかとは存じます。
それらの処理をするのであれば、弁護士の方に信託し、受託者となっていただく。寄付を受けた目的に即して支出が生じた際には、受託者の方が管理、記録した上で支出する。
といったことをされ、租税回避には当たらない。聞かれた時には説明できる状態にしておけば、リスクは許容範囲内と言えるのかとは存じます。であれば贈与税の時効は6年。6年間は贈与とされた場合の税負担額(無申告加算税、延滞税等含めて)は手元に残しておく。
それ以降は、時効ですので、実害が生じることはありません。
よって、税務署に文書で事前回答を得ておく。これで回答を得た運用体制、手法を取るのが安全かとは存じます。
これらの問い合わせには、、最寄りの税理士の方に書面を作成いただけば宜しいのかと存じます。安心料です。
本投稿は、2018年07月18日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。