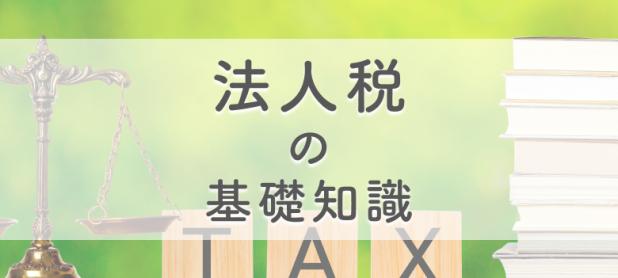固定資産税の延滞金 二分の一免除について
固定資産税の延滞金についてご相談です。
父(死亡)が生前に固定資産税を滞納していたため、自宅と土地は差押えとなっています。地方に一人で暮らしている母が自分の年金から少しずつ返済し、元金は0になりましたが延滞税が200万程度残っています。
そこで質問ですが、地方税法第15条の9第4項に「地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。」とありますが、母が支払いしている延滞金の免除は可能でしょうか。
本来はきちんと返済すべきですが、母は高齢でかつ要介護状態となり、預貯金もほとんどないため今後も返済を続けていくことが非常に厳しい状況であり、別居している子供たちも支払能力がありません。
少しでも遅延金を減額する方法がありましたら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安達幸男
ご質問の場合、本税(元金)が完納になった現時点では、自宅と土地が差押がされていた期間に対応する延滞税については、その2分の1を免除することは可能です。この場合、差押えをしていた事実があれば、結果として本税が完納になっていることが前提ですが、その差押をしていた期間に対応する延滞税を免除することになります。本税(元金)について、誰が支払っていたかは、全く関係ありません。
ただし、自宅及び土地の差押をしていただけではだめで、その財産の評価額が税金分を十分に充足(カバー)していたと判断できることが条件になります。例えば、自宅及び土地の評価は、2000万円で、税金に優先する銀行の抵当権が1500万円設定されていたケースでは、税金にあてることができる金額は500万円となりますので、税金の額(元金及び延滞税の合計金額をいいます)が、300万円であれば充足していたこととなり免除可能となりますが、逆に、800万円であれば充足していなかったということになり免除不可となります。
なお、条文上は、「免除することができる」となっていますが、要件に該当するケースでは、必ず免除することになっています(要件に該当するのであれば、必ず免除しなければならないということであり、市町村役場に免除するかどうかの裁量はないという意味です。)。
以上のとおり、問題となるのは、自宅及び土地の評価額がいくらであり、税金(本税及び延滞税の合計額)を充足していてかどうかという点です。ただし、あなたが不動産鑑定士に評価を依頼する必要はありませんので、役所に対して、この規定による延滞税免除のお願いの相談をするということになります(役所に評価額と充足の判断を促すということ)。
このほか方法として、免除した残りの延滞税をどうしたらよいかという点ですが、一つ目は、父の相続人が全員相続放棄をする方法があります(相続放棄をすると税金を支払わなくてもよいことになります)。ただし、相続放棄をすると、自宅を相続できないというデメリットがありますし、相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要がありますので、注意してください。
二つ目として、相続放棄をしないということであれば、相続人に父の税金が引き継がれます。この場合、詳しい状況は分かりませんが、各相続人には財産もなく、納税資力もないということであれば、国税徴収法153条の滞納処分の停止という規定(該当すれば納税義務そのものが消滅してなくなります。)もありますので、一度市町村役場に相談して判断を仰いでみてはいかがでしょうか。
丁寧なご回答誠にありがとうございます。
役所担当に相談したところ、こちらがびっくりするほどあっさりと2分の1免除の回答を頂きました。
こちらから相談しないと教えてくれないものなのかとも思いましたが、担当とケンカしても仕方ないので、そのまま受け入れました。
今後は先生が教えて下さったとおり、滞納処分の停止について改めて役所に相談してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年11月29日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。