滞納処分の執行停止の際の財産調査について
滞納処分の執行停止の際に財産調査をされるとききました。
その財産調査の際に自分の家だけでなく、親や兄弟まで連絡がいったり、親の自宅まで捜索が及ぶことはあるのでしょうか?
親族には事情を話していないため、それは避けたいです。
税理士の回答
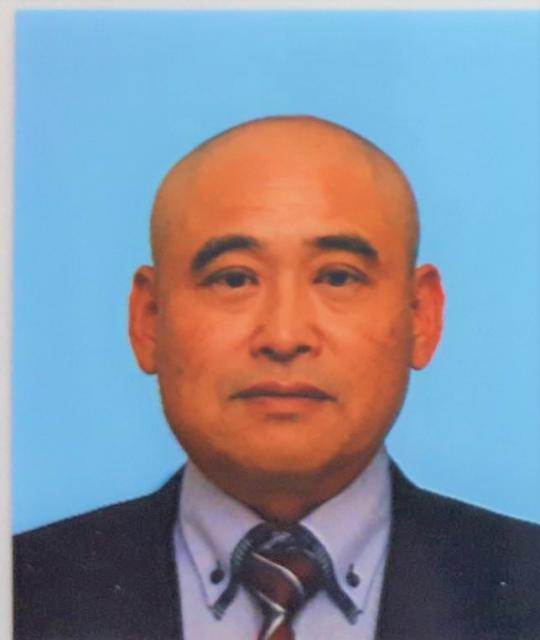
北原雄二
法153条は国税徴収法での納税緩和措置の一つです。その中でも、滞納国税がある者にについて、滞納処分を停止することですから、あらゆる調査を行います。つまり、滞納者(納税者)の家族関係・財産関係(現金・預金・不動産・投資・関係会社等)はすべて細かく調査することとなります。その中で、親族等に財産が一部でも移転していたとすれば当然調査が及ぶでしょう。捜索は条文の構成上財産調査のくくりに入りますので法142条に該当すれば親族に連絡が行き、捜索が及ぶことはあるでしょう。
法142条に該当すれば
どのような条件でしょうか
親族等に財産が一部でも移転していたとすれば当然調査が及ぶでしょう
移転していない場合はどうでしょうか?
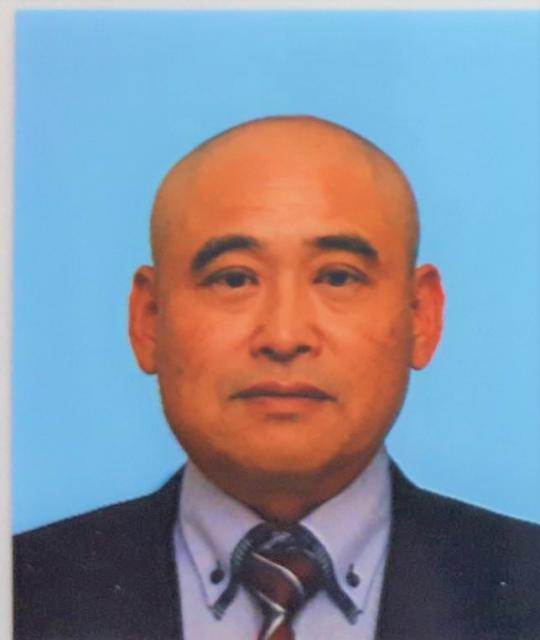
北原雄二
通達を引用すると以下の通りです。参考にしてください。
捜索ができる場合
(滞納処分のため必要があるとき)
1 法第142条の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章《滞納処分》の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、差押財産の引揚げ、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(所持)
2 法第142条第2項の「所持」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的継続及びその主体の意思を問わない(大正3.10.22大判参照)。
(引渡し)
3 法第142条第2項の「引渡をしないとき」とは、滞納者の財産を所持している者が、その財産を現実に引き渡さないときをいい、法第58条第2項《第三者が占有する動産の引渡命令》の規定により引渡命令を受けた者又は第60条第1項《差押動産の保管》の規定により保管する者が引渡しをしないときに限られない。
(相当の理由)
4 法第142条第2項第2号の「相当の理由がある場合」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、財産を所持すると認められる場合等をいう。
捜索ができる物及び場所
(滞納者又は第三者の物)
5 捜索ができる「物」には、滞納者又は3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる金庫、貸金庫、たんす、書箱、かばん、戸棚、長持、封筒等がある。
(注) 貸金庫については、滞納者が銀行等に対して有する貸金庫の内容物の一括引渡請求権を差し押さえることもできる(平成11.11.29最高判参照)。
(滞納者又は第三者の住居その他の場所)
6 捜索ができる「場所」には、滞納者又は3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる住居、事務所、営業所、工場、倉庫等の建物のほか、間借り、宿泊中の旅館の部屋等があり、また、建物の敷地はもちろん、船車の類で通常人が使用し、又は物が蔵置される場所が含まれるものとする。
なお、解散した法人について、清算事務が執られたとみられる清算人の住居は、捜索ができる「場所」に含まれる(昭和45.4.14東京高判参照)。
財産が一部でも移転していたとすれば当然調査が及ぶでしょう。
具体的にどのような場合があるのでしょうか?
親に迷惑をかけたくないのですが、無理なのでしょうか?
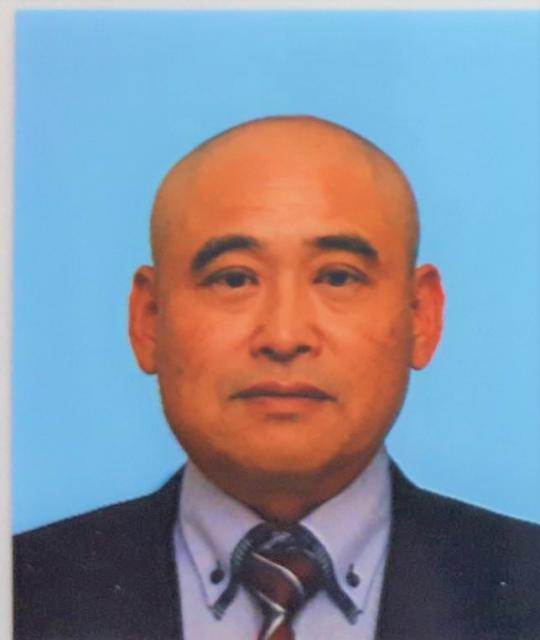
北原雄二
例えば預金が振り込まれた場合、突然現金が入金になった場合、不動産が登記変更になった場合、財産(棚卸資産・車・売掛金・貸付金・保険等)のすべてが考えられます。
本投稿は、2019年12月11日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





















