副業解禁! 副業したらかかる税金の解説&賢く節税する方法

副業解禁が本格的になり、会社員でもフリマアプリや、インターネットを使って副業をする人が増えてきました。そんな副業をする際に気になるのが、副業をしたことで得られる収入に関する税金です。
副業したときの税金の計算や、確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか?
目次
副業の収入も確定申告する必要がある?
副業の所得が年間20万円以上になると確定申告が必要になります。数箇所から所得がある場合は、1箇所あたりの所得ではなく、合計額が基準です。
ポイントは収入の金額ではなく、収入から経費を差し引いた残りである「もうけ」部分が20万円超であるかどうか となります。
確定申告が不要なのは、副業の所得が20万円以下、且つ給与が1か所のみで年末調整されている人です。
よく勘違いされる部分ではありますが、この基準は国税である「所得税」についてのものです。地方税である「住民税」に関しては、所得が20万円以下であれば、確定申告が不要になるという制度はありません。
したがって住民税の確定申告は、所得が20万円以下であってもするようにしましょう。
- 副業サラリーマン必見!いくら稼ぐと確定申告しないといけないの?今のうちに知っておきたい確定申告の基礎知識
- 確定申告が必要な人って?会社員・学生・主婦などケース別に紹介
- 【住民税申告完全ガイド】必要な人や確定申告との違い、計算方法、支払い方法を解説
副業の税金の計算方法
副業の税金の計算手順を簡単にまとめると、次のようになります。
(1)収入 − 経費 = 所得
(2)所得 × 税率 = 税金
日本では、「超累進課税制度」を採用していますので、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなります。
副業には主に「事業所得」と「雑所得」に該当する場合がありますが、いずれの所得の場合でも、基本的な計算方法は変わりません。
副業でできる節税方法
節税方法は、副業が事業所得にあたる場合と、雑所得にあたる場合で異なります。
もし、副業がどの所得に該当するかわからない場合は、税理士や税務署に相談すると良いでしょう。
事業所得の節税方法
まず、副業が事業所得にあたる場合は、青色申告の承認申請書を税務署に提出して、青色申告特別控除を受けることが一番です。
この控除を使えば、最高65万円が控除され、所得を圧縮することができます。つまり、その分税金を安くすることができるのです。
ただし、青色申告には記帳要件というものがあり、会計システムなどを使って、複式簿記にのっとって記帳を行い、貸借対照表(財産状態を表したもの)と損益計算書(経営成績を表したもの)の作成をすることが必要となります。
現在は、クラウド会計システムなどで、記帳を手軽に始めることができ、さらにインターネットバンキングと連携すると、仕訳の入力の手間を大幅に省力化することができます。
また、この青色申告には他にもさまざまな特典があり、赤字を3年間繰り越すことができたり、事業に従事している家族への給与を支給して、経費にしたりすることができます。
雑所得の節税方法
これに対して、副業が雑所得に該当する場合は、青色申告の特典を受けることができません。
そのため、一番の節税方法は、経費に該当するものを正しく、漏れなく集計することになります。これは当たり前のことですが、集計することに慣れていない方も多く、また領収書を捨ててしまっていたりして、漏れなく経費に入れることができていないことが多々あるようです。
集計漏れを減らす方法としては、経費が発生したらその都度集計し、Excelなどにメモしておくことなどが大事です。
なお、経費に該当するかどうかに迷う場合は、次の3つを基準に判断してみましょう。
- 自分で支払うべきものであること
- 事業のために使ったものであること
- 証拠となる領収書やレシートなどの書類を保存していること
1については、自分で支払ったもののみ経費にすることができますので、取引先が支払った接待費の領収書などは経費にすることはできません。また、12月末までに支払いが済んでいなくても、商品を受領していたりサービスを受けている場合には、未払金や前払金などどして経費にいれることができます。
ここでは、2が一番重要で、その経費は事業のために使ったものであるかということです。
ポイントとしては、経費が収入に繋がるものであることを、納税者が説明できることが必要となります。もちろん、プライベートな支出は経費にすることはできません。家族での飲食代や、家庭で使用する消耗品などは事業に関係ないため、経費にはなりません。
3の証拠となる領収書などの書類には、「いつ、どこに、いくら、なんのために」支払ったものであるかが記載されていなければなりません。また、領収書がもらえない場合には、出金伝票などに「いつ、どこに、いくら、なんのために」という内容を記載しておくと、証拠書類として認められます。
個人事業から法人成り(会社)にしたら税金が安くなる!?
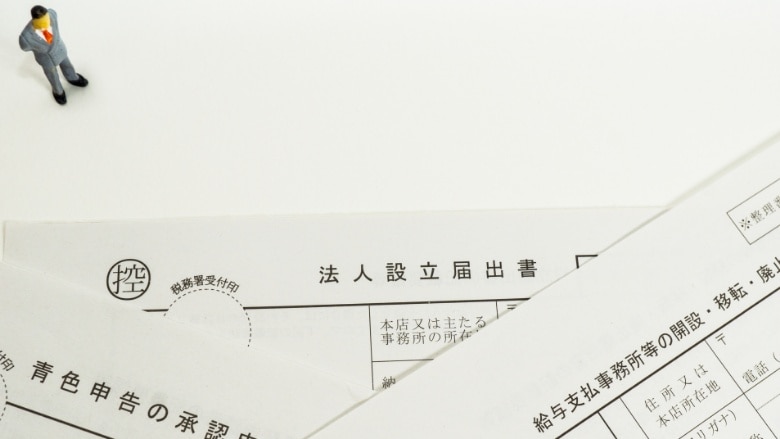
売上が増えてきて、所得が大きくなると、会社を設立することを考える人も多いと思います。会社にすると信用を得られるため、取引がしやすくなることもメリットですが、税金面でもメリットがあります。
会社を設立した場合は、会社と個人は別人格になりますので、会社から社長へ給与を支給することができます。給与は会社にとって経費になり、さらに給与を支給された社長には「給与所得控除」という個人にとっての経費が概算で与えられています。そのため、二重に経費が考慮されている状態になり、所得を圧縮して、税金を安くすることができます。
この他にも、個人事業では経費にできなかった生命保険料が、会社が契約者になった場合は会社の経費にできる場合もあります。また、社長の自宅を社宅扱いとして会社の経費に算入することや、遠方への出張などの場合は、日当を支給して経費にする方法などもあげられます。
さらに、会社の赤字は10年間繰り越すことができ、個人事業の3年より長期間繰り越すことが可能になるといったメリットもあげられます。
法人成りするデメリットもある
ただし、法人にすると税金面でのデメリットもあります。
個人では、赤字の場合は税金を支払う必要はありませんが、法人の場合は赤字でも均等割りという数万円の住民税を支払う必要があります。
そのため、会社の設立は事前にシミュレーションをして、メリットとデメリットをしっかり把握したうえで行うよう心得ておきましょう。税金等のシミュレーションについては、税理士等に相談すると、安心して起業できるはずです。
おわりに
副業は、なかなか上手くいかないことも多いものです。事業案を練りに練って始める方もいると思いますが、副業の成功の秘訣は、ずばり「小さく始めて、何度も試す」ことです。
練った事業計画や、事業モデルでも成功するとは限りません。事業は失敗の積み重ねであり、計画→実行→振り返りのサイクルをしっかりしていくことが大切です。
そして、副業では銀行から融資を受けて投資することも難しいため、事業資金は限られています。そのため、まずは資金をあまり使わずに始めてみること。失敗したり、上手くいかなかったりする場合には、次の方法を試してみるということの繰り返しが必要になります。
また、大企業が参入できないようないわゆる「ニッチ産業」で事業を行うことも大切です。
価格やノウハウで大企業に勝つことは難しいですが、大企業が参入しないような分野なら、個人だからこそできる分野を強みとできるはず。副業で、自分らしい働き方を模索してみてはいかがでしょうか?
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
