空き家の3,000万円特別控除の適用の可否について
両親が亡くなり、相続した不動産を2,900万で売却の予定です。
この際に空き家特別控除は使えますか、その他、節税はありますでしょうか。
1度相談した先で何も節税の適用がないといわれ、相続人それぞれにが高額な譲渡所得税がを納めなければならないと言われました。
売却予定の不動産の状況は下記になります。
1)2020.4月父死亡、2022.1月母死亡
2)両親死亡後、空き家。母死亡後、子で相続。
3)相続人、3人。長女、次女、長男(2019.8月不動産より引越し済)
遺産分割協議書換価分割を目的としていますが、売却便宜の為、相続登記は長男。
4)平成13年に立て替えをしています。(借入金1,400万)
遺産分割協議書作成時に熟考すればよかったのですが、本来は、長男に税金関係を纏めてお願いしたかったところなのです。譲渡所得税が発生する場合は、遺産分割協議書が作成されている以上は、個々が支払いをしなけならないものものでしょうか(元々、長女、次女は均等に遺産を分割してもらう程の意思はなかったので)
知識がなくお恥ずかしいのですが、何卒ご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、譲渡所得税や相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
① あなた自身で、空き家特例の条件は、パソコン等でご覧になりましたか?
② 譲渡所得の特例は、条件がいくつもあり、専門性が強い内容です。
③ 困っているのは分かりますが、一般的な質問ではなく個別性の強い質問です。
④ 条件がちょっとでも違うと特例に該当せずに税金が多額に変わります。非常に答えにくい質問です。
申し訳ございませんが、ここは税理士紹介サイトなので、資産課税関係に強い税理士さんを紹介してもらってください。

補足します。
空家特例は、昭和56年5月31日以前に建築確認がなされた旧耐震建物が前提です。
このため、平成13年の建物は該当しません。
次に自己の居住用の3,000万円について。
お父様の死亡後はお母様1人の登記。
お母様死亡後は、長男単独名義だとすると。
長男は、所有者としては住んでいませんので非該当。
該当しそうな特例は、お母様の相続で相続税がかかったケース。
その場合、相続税の一部を取得費(言い換えると「原価」)に加算できるというものがあります。
これとは別に、相続登記費用も取得費に加算できます。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
空き家控除の適用外であることはわかりました。
他に節税できる手段がないか、節税に強い税理士さんを探してご相談しようと思います。
有り難うございました。
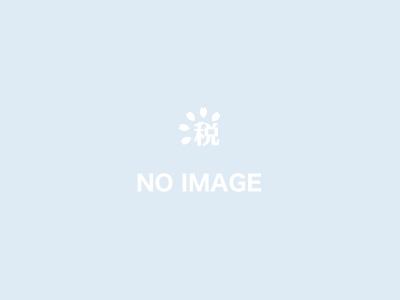
安島秀樹
換価分割を目的として、売却のため、相続登記は長男とあるので、譲渡所得を申告して税金を納めるのは長男だけだと思います。相続人それぞれが譲渡所得税を納めるということはないと思います。長男がまとめて税金を払ったあと、協議書に基づいて残ったお金を分けるということではないでしょうか。

補足します。
換価分割では、3人が申告します。
分割の段階で取り分が決まっているでしょうから、その割合で各人の申告になります。
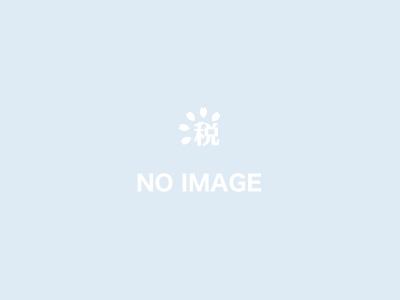
安島秀樹
すいませんでした。鎌田さんのいうとおりやってください。
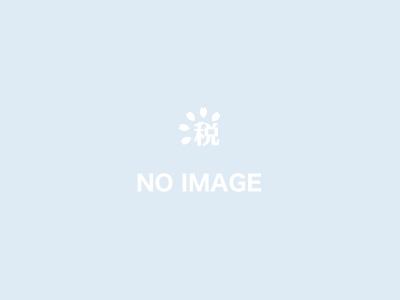
安島秀樹
協議書はいつでも直せるので 換価分割でない代償分割になおせば
うまくいくのではないでしょうか。長男の同意があればですが。

「平成13年建て替え」について、文章を読みそこないました。修繕だと勘違いしましたので、空き家特例が使えるかもという前提で、記載しました。
建物は、平成13年建築ですね。ならば、その時点で該当なしです。
各先生方には、色々とお知恵を頂き本当にありがとうございます。
協議書を修正できれば、それが1番相続人の意向にマッチして売却をできると思うのですが、法務局に提出済の協議書を訂正すると、申告時に贈与税と見なされる部分が発生する恐れがあるとも聞かされ。
いづれにしても、相続登記をお願いした司法書士先生にも相談したいと思います。
ありがとうございました。

この1月まで、税務署で相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりましたが、遺産分割協議書が、適正に作成された後に書き換えますと
それ以後の変更は、贈与の対象になりますので注意が必要です。
ほかの先生がお答えになったことについて、批判的な内容を記載すると「みんなの税務相談ガイドライン」に抵触するので、答えるのを保留していましたが、「更問い」がありましたので、お答えしました。
西野先生、ご教示ありがとうございます。
やはり、贈与の対象になりますね、簡単にはできませんね。元々は、熟考しないまま協議書を作成してしまったことによりますので。協議書通りにすすめるようにします。
ありがとうございました。

最初に前提条件を読み切れずに、お答えしてすいませんでした。
ただ、今後も「何かの特例の適用」については、「要件」については、ご自分で一度目を通して、
「当てはめをしてみる」
そこで、分からないことを相談されるのが、より間違いのない回答を得られるかとは思います。
本投稿は、2022年09月20日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
























