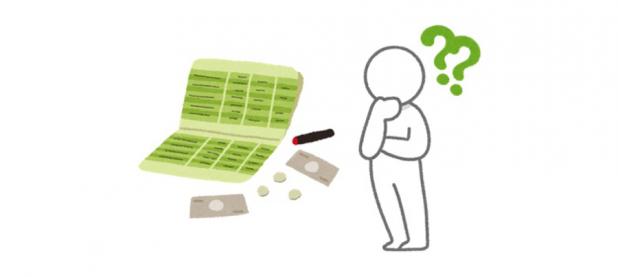節税対策として財産移転
節税対策として生前贈与の財産移転と言う回答がありましたが、相続人は配偶者と子供1人です。相続財産は不動産約1千万預貯金約5千万です合計約6千万、相続税対策方法、その時の相続税はどうなりますか。
税理士の回答
1 現状の相続税(推計)
配偶者が全部を相続した場合は、0円(申告は必要)。
子供が全部を相続すると、180万円の相続税。
配偶者と子供が半分ずつ相続すると、90万円です。
2 節税策
相続税の課税最低限(基礎控除といいます)は、4,200万円です。
3,000万円+600万円×2人。
節税策とは、合法的に相続税を少なくする方法のことです。
現状でも、配偶者は優遇されています。
いわゆる内助の功を考慮した制度で、1/2又は1億6千万円までの相続を無税にできます。
なお、子供さんの相続分を無税にするためには、財産を4,200万円以下にします。
この方策の代表例が生前贈与の活用で、これにより、財産を移転します。
何をどのように贈与するかについては、いくつかあります。
イ 年間110万円の贈与を毎年繰り返す。
ロ 自宅を配偶者に贈与する。
婚姻期間が20年以上であれば、2,110万円まで贈与税がかからない。
ハ 子供や孫の住宅取得を支援する。
ニ 子供や孫の教育資金の一括支援。
なお、生前贈与以外にも方策はあります。
居住用自宅以外の不動産(旧宅)の扱いはどうなりますか。又生前贈与以外の方法とはどういうことでしょうか
1 小規模宅地等の特例
自宅の土地(敷地)の相続では、330㎡まで8割減という特例があります。
相続する方が配偶者は無条件、同居の子供さんでその後居住継続であれば該当します。
例えば、居住用の土地1,000万円ですと、800万円の減額か可能になります。
※この特例は10か月以内の相続・申告が条件になります。
2 旧宅の不動産
賃貸していれば、家屋は70%評価、敷地(専門的には貸家建付地といいます)は
おおむね85%位になります。
空家であれば減額の要素はありません。
3 生前贈与以外
代表的なものは以下のとおりです。
なお、節税策を講じる場合には、専門家(相続税に詳しい税理士)にご相談することがお勧めです。
その際は、当サイト「税理士ドットコム」が無料で紹介してくれますので、検討してみてください。
イ 養子を増やして基礎控除を増やす。
子供さんがいますので、養子の数は1人だけしかカウントされません。
基礎控除が600万円増えます。
※養子は、相続権を主張できることに注意が必要です。
ロ 生命保険の非課税枠の活用
相続人が2人のケースでは、1,000万円の非課税枠があります。
現在加入している生命保険が無い場合、又は非課税枠に満たない場合。
不足額の一時払いに加入することで、預貯金の課税対象額を減らすことができます。
ハ 銀行ローンを組んでアパートを建設
アパートは、上記の貸家と同じで家屋・敷地とも減額されます。
加えて、ローンの残高が債務控除できます。
(注)立地等の十分な検討が必須です。
ローンを組んで建設したアパートが空家では、ローンの返済に窮します。
これでは、本末転倒。節税どころか大問題です。
ニ 非課税財産(墓地、墓石、仏壇など)を購入して、預貯金を減額する。
解りやすい回答有難うございました。毎年110万円の贈与とありましたが。ただ、娘、若しくは配偶者名義に定期的に通帳に110万入れた贈与では税務署では認めず贈与契約書を作らなければ認められないとも、聞きましたがその所はどうなんでしょうか具体的に定期的な贈与の仕方はどうしたらいいですか。
1 贈与とは
贈与というのは契約です。
当事者間の「あげます、もらいます」という合意。
例えば、娘さん名義の通帳を作り、毎年入金する。
これだけでは足りません。
娘さんに「もらったという認識」がまず必要です。
預金するかどうかは娘さんの意思です。
仮に、通帳に入金したケース。
通帳と印鑑とキャッシュカードを娘さんが持って
いることは当然です。
※親御さんが持つと、贈与ではなくて名義借用に。
2 契約書の作成
贈与が成立するのは、当事者の合意だけです。
つまり、契約書は必須ではありません。
契約書のない贈与、口約束の贈与でも有効です。
この場合、
履行(実際にあげる)前はいつでも贈与を取消せます。
※税務対策
口約束も有効ですが、あえて記録を残す場合。
イ 通帳への入金を、振り込みにする。
ロ 契約書を作成する。
ハ 贈与税を申告して、申告者の控えを保存する。
※110万円までは贈与税がかかりません。
しかし、110万円以下の申告もできます。
納付する税金がゼロの申告で、専門的には、
「ゼロ申告」といいます。
ニ あえて、税金を払う。
例えば、111万円を贈与。
千円の贈与税を支払うという方もいます。
これは、ゼロ申告では認められないと考えるからで
すが、そんなことはありません。
更に、200万円、300万円の贈与をする方も。
これは、より多くの財産移転をするためです。
この金額の贈与税は10%。
節税になる相続税の税率の方が高いケースです。
3 注意点
最初の回答で説明を忘れていた注意点があります。
イ 3年以内の贈与加算
例えば、配偶者や娘さんが財産を相続する場合。
死亡日から遡って3年以内の贈与は、相続財産に
加算されますので、節税になりません。
そのため、早期に贈与を始めることも大切です。
ロ 定期金となるケース
定期金とは、定期的に贈与を繰り返すものです。
例えば、今後10年間、毎年110万円をあげま
す、もらいます。
これでは、「10年間の贈与」という1個の契約。
贈与金額は1,100万円(評価としての減額は
ありますが)。
つまり、110万円を超えて贈与税が発生します。
この対策は、
毎年の金額を変える、翌年以降を取決めない。
もちろん、10年間の契約書を作成してはダメです。
ハ 兄弟間のバランス等
子供さんが2人以上の場合。
後々トラブルにならないようにするため、公平に
贈与することも大切です。
更に、子供さんに過度の期待を抱かせないこと。
ニ 親御さんの生活
贈与者や残された配偶者の生活は優先されるべき。
最初から最後までよくわかりました。先生の回答を参考にして節税対策を考えていきます。大変お世話になりました。
参考にしていただければ嬉しいです。
当サイト「税理士ドットコム」で相続税に詳しい税理士を紹介してもらい、より具体的な相談をしてみてください。
旧宅の評価額が貸家であれば減額されると回答ありましたが親戚に無償で貸している場合はどうなるのでしょうか。
旧宅が貸家であれば評価額はどうなるのでしょうか。
減額されるのは、賃貸借の場合です。
無償であれば減額されません。
旧宅を貸家でそれなりの家賃があれば、この時確定申告で不動産収入を申告してそれなりの所得税が付加されるのでしょうか。
家賃は、不動産所得の収入になります。
不動産所得の計算は、
家賃収入+権利金収入-経費=の計算です。
経費としては、固定資産税や減価償却費があげられます。
不動産所得金額+他の所得金額-基礎控除等の所得控除。
残りがあれば所得税、住民税がかかります。
何回もすみません、築45年の旧宅ですが、固定資産税は若干賦課されてますが、減価償却費はゼロでしょうか。
建物の構造が、木造、木造モルタル造であれば、耐用年数経過でゼロとなります。
こまごまと何回も教えて頂き詳しくわかりました。後は私の考えで対応したいと思います。大変お世話になっておりました。
最後になりますが相続時評価額が法定相続人に応じた非課税になると思われた場合でも相続人が相続税の申告はしなければならないのか、しなくてもいいのかそこのところはどうなのでしょうか。
ご質問の趣旨が明確ではありませんが。
例えば、
相続人が2人で、相続税の基礎控除が4,200万円のケース。
相続財産が、4,000万円の場合は申告不要です。
最初の質問では、6,000万円とのことでした。
しかし、
配偶者の内助の功の特例や、
自宅の敷地が100坪まで8割減になる特例があります。
これらの特例を適用することで、4,200万円以下のケースであれば、申告は必須です。
これらの特例は、期限内の申告が条件だからです。
これらの特例を使わないで、4,200万円以下のケースであれば、申告不要です。
節税対策として現在居宅及び同敷地の権利が私1/2配偶者が1/2ですので、結婚して20年経過後の私の権利を今時点で生前贈与しても贈与税申告はせずとも贈与税はは発生せず、今回質問で全体の相続時評価額が4200万円以下であれば相続税の申告が不要と理解してよいのですか。
贈与税の配偶者控除は、申告が条件です。
2,110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
なお、この贈与は、将来相続財産に加算されることはありません。
その上で、4,200万円以下であれば、相続税の申告は不要です。
贈与税の配偶者控除を利用するとすれば税務署に贈与税の申告書とそのほかの必要書類はどういうもなのでしょうか。
添付書類は次のイ~ハが必要です。
イ 贈与を受けた配偶者の戸籍謄本又は抄本
ロ 贈与を受けた配偶者の戸籍の附票の写し
ハ 居住用不動産の取得を証する書類
※イとロは、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの。
※ロの「戸籍の附票」とは、住所の移転状況が記載されている書類で、イと同様に戸籍係で取得します。
※ハは、一般的には登記事項証明書です。
なお、前回の回答を一部補足します。
贈与税の配偶者控除を受けた金額は相続財産に加算されません。
しかし、基礎控除の部分は3年以内であれば加算されることがあります。
(相続しなければ加算されません。)
前回、2,110万円は加算されませんと回答しましたが、正しくは、配偶者控除を適用した金額(2,000万円が限度)が加算されないということです。
相続税の観点からご相談してましたが、贈与税の配偶者控除を受けたときに配偶者に不動産取得税はかからないのでしょうか。かかるのであればどのくらいか。かからないのであればその手続きはどうなりますか。
残念ながら、詳しくないのでお答えできません。
担当の機関や、詳しい方にお尋ねください。
不動産取得税は確か県税と思っていましたので、そちらの担当部局に確認したいと思います。これまで何回となく細々と教えて頂き有難うございました。先生からの教えて頂いたことを参考に私の考えで、私の生前に出来ることは行い相続時に行うことは相続人に教えたいと思います。本当に有難うございました。
参考にしていただければ幸いです。
また何かありましたら、当サイト「税理士ドットコム」をご利用ください。
本投稿は、2019年02月16日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。