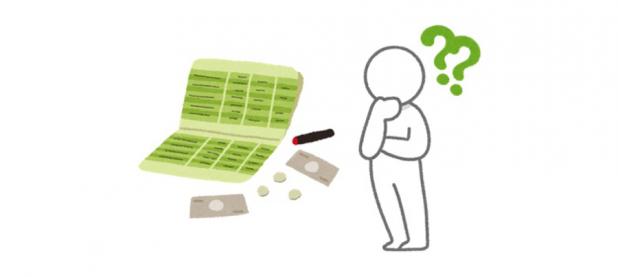未婚の叔母の生命保険と相続について
未婚の叔母85歳が生命保険に加入しており、自身が死亡した際、姪の私(A)に約一億円が支払われる契約となっています。しかし別に公正証書も作成しており、甥(B)に全財産を相続させる。甥(B)が死亡した場合は甥の子(b)に相続させる内容となっています。ただ、全財産とは3000万程度の預貯金と証券です。
①姪の私は一億円を相続手続き無し、無税で受け取れるのでしょうか?
②課税されるのであれば、保険金の受取人を増やし、縁の深かった親族に分散させて節税を考えたいのですが、分散する方法のアドバイスなど頂けないでしょうか?
税理士の回答

①姪の私は一億円を相続手続き無し、無税で受け取れるのでしょうか?
→いいえ。その保険金は相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象になります。相続税の申告が必要です。
②課税されるのであれば、保険金の受取人を増やし、縁の深かった親族に分散させて節税を考えたいのですが、分散する方法のアドバイスなど頂けないでしょうか?
→相続税は被相続人の課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を各財産の取得割合に応じて負担します。
したがって、受取人を分散させても基本的には節税にはなりません。
ただ、推定相続人がどなたか分かりかねますが、死亡保険金については、法定相続人×500万円で計算される非課税枠があり、その非課税枠は法定相続人であれば使えます。
なので、ご相談者様や甥っ子さんが法定相続人でないなら、法定相続人の方を死亡保険金の受取人に入れれば、幾分か節税できます。
また、相続税の基礎控除枠は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、ご相談者様や甥っ子さんが法定相続人でないなら、叔母様の養子になることで、相続税の基礎控除枠が増え、節税になります。
なお、この生命保険金の非課税枠や、相続税の基礎控除枠を計算する際、ご質問の文面から叔母様に実子がいないとして、法定相続人の人数に入れれる養子の数は2人までです。
ただし、相続税法には養子の数の否認規定があり、その養子縁組が明らかな租税回避行為と見られる場合は、法定相続人の数に養子を入れれなくなってしまうことがあります。この否認規定が発動されるのは、過去の事例からすると、推定被相続人が入院していて、もう回復の見込みが無いような中で、本人が役所に行って明らかに手続きができないような場面で養子縁組がされているときです。

補足します。
養子縁組をする事で、基礎控除枠が増えると、先の回答で申し上げましたが、もし仮に、法定相続人に叔母様の兄弟が3人以上いる中で、ご相談者様と甥っ子さんが養子になってしまうと、法定相続人がご相談者様と甥っ子さんの2人になってしまうので、この場合には相続税の基礎控除枠が減少してしまいます。
本投稿は、2021年07月23日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。