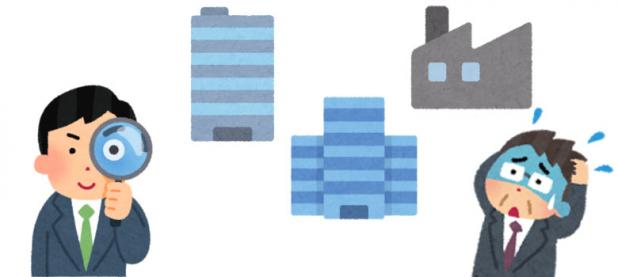レジから出てくる長い領収書について
この頃、スーパーや薬局などのレジなどで、打ち出される領収書は、領収書の後に、
点線部分があって、明細がついていて、その下にクーポンやお知らせなどが書いてあって、とても長いものが多いです。
購入金額は合計5000円ぐらいまでです。
過去の皆様の税務相談読ませていただいて、疑問に思うことがありました。
教えてください。
よろしくお願いします。
過去にこちらにされたご相談で、2021年3月21日に税務調査カテゴリーで、に投稿されていたご相談には、
切り離して領収書部分を保管、帳簿に購入したものを書くという処理でいいのでしょうか?という質問に対して、
松井優貴先生
サンセリテ税理士事務所
大阪府 堺市西区
が、
領収書のみでも、書類の保存としては十分です。
明細を切り離していることを指摘される可能性は少ないと考えます。
と、答えていらっしゃいました。
今でも、このような場合
領収書部分のみの保存で大丈夫ですか?教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

最近話題性の高いインボイス制度に絡めて意見をさせて頂きます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)においては、レシートもインボイスになります。ただしレシートの方は、適格請求書の記載要件を一部簡易にしていることから適格簡易請求書と呼ばれます。適格簡易請求書は、
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
・課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
・税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
以上のとおり5項目の記載要件があります
この要件の内容を網羅したレシート(の一部)であれば、長すぎて不要な部分は省略しても問題はないと考えます。
松井先生の「領収書のみでも、書類の保存としては十分です。明細を切り離していることを指摘される可能性は少ないと考えます。」に賛同させて頂きます。
なお、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の取扱いについても、現行では指針は示されていないかと存じますが、あまり長いレシートでは読取り困難のケースもあり得ますので、同様に考えて良いと思われます。
早速回答いただきありがとうございます。
インボイス制度でのご教授ありがとうございます。
もしよろしければ一例で、教えていただいてもよろしいでしょうか?この場合も切り取って、領収書部分を保管し、それ以外は処分しても大丈夫でしょうか?
例 個人事業主が、薬局で330円の会社用のトイレットペーパーを個人のクレジットカードで買った時
レジから打ち出される領収証には、日付、金額330円、内訳10%対象税込金額 330円 内消費税30円
現金0円、クレジット330円その他0円 薬局の名前 住所(領収書部分に何を買ったかの記載はないです。)
点線
お買上明細(領収書明細と書いてあるところも)
トイレットペーパー 330円 小計330円 内10%対象額330円 内税額30円
点線
クレジット売上票 カード会社〇〇
カード番号 金額 ローマ字でカードの持ち主の名前(ない場合もあり)
となっています。
帳簿には、消耗品費/事業主借 摘要に〇〇薬局 ティッシュ (個人名)カードで購入

適格簡易請求書の記載要件からすると、例示の領収証について保存が必要な部分は、
↓必要な部分
日付<年月日>、金額330円、内訳10%対象税込金額 330円 内消費税30円
<課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額>
現金0円、クレジット330円その他0円
薬局の名前 住所 <事業者の氏名又は名称> <制度導入後は登録番号が付されます>
(領収書部分に何を買ったかの記載はないです。)
点線==============
お買上明細(領収書明細と書いてあるところも)
トイレットペーパー 330円 <課税資産の譲渡等に係る資産の内容>
小計330円 内10%対象額330円 内税額30円
<税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率>
点線==============
↑必要な部分
以下の決済手段等に係る記載内容については省略できると考えます。
(帳簿の管理上は勘定照合のためのフラグとしてあった方がよいかもしれませんが)
クレジット売上票 カード会社〇〇
カード番号 金額 ローマ字でカードの持ち主の名前(ない場合もあり)
電子マネー等の利用事績も同様に不要と考えます。
さらに、レシートにポイント付与の明細の記載がある場合でも、値引き相当との扱いで非課税となりますので保存対象とする必要はないと考えます。
(企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱う)国税庁HPより
つたない例に詳しくご回答をしていただき、ありがとうございます。
すっきり整理されて、とてもよくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月11日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。