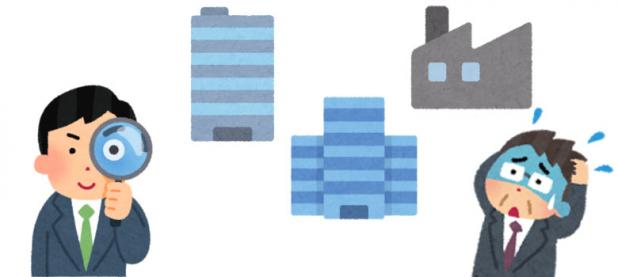生活費・教育費の贈与に関する税務上の確認
以下のような形で母から生活費・教育費の贈与を受けておりますが、税務上問題でしょうか。特に③が気になっております。
①母より、生活費・教育費として、現金10万円~20万円の贈与契約書を締結し、現金を受領
②現金を使用した際は、領収書等の証憑を保存
③自分の口座から振替・振込をした場合、その分は自分のものとする。通帳は証憑を保存
※なお、振替・振込の金額をATMより入金することも考えておりましたが、手間がかかるため、行っておりません。
④現金は数か月で使い切り、使い切ったら再度贈与契約書を締結して同様の流れを繰り返し
⑤生活費・教育費は贈与税の非課税対象と理解しており、年間110万円を超えても問題ないと認識
⑥利用用途は証憑より生活費・教育費と説明可能。
税理士の回答

増井誠剛
今回の①〜⑥のうち、特に③「自分の口座から振替・振込をした場合、その分は自分のものとする」という取り扱いは、税務上のリスクが最も高い部分です。生活費や教育費としての贈与は、民法上「通常必要な範囲内で使用すること」を前提に非課税とされており、資産形成や貯蓄を目的とする場合にはその限りではありません。したがって、振替・振込により自由に使える状態にしていると「生活費・教育費」ではなく「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
一方で、①・②・④のように、支出の都度領収書や明細を保存し、支給と支出が対応していることを説明できるのであれば、生活費・教育費としての性格を維持できると考えられます。ただし、契約書の形式よりも実態が重視されます。特に税務調査では「贈与契約書を作成していても、実質的に本人の自由になる資金であったかどうか」が判断基準になります。
また、⑤にあるように、生活費・教育費は原則として年間110万円を超えても非課税ですが、これはあくまで「生活維持に必要な範囲」に限られます。したがって、資金の一部を貯蓄や投資に回す運用は避け、支出目的と証憑を対応させておくことが重要です。最も安全なのは③を削除し、入金と支出を明確に管理する運用に改めることです。
ご回答ありがとうございます。
①で、贈与契約で受領した現金10万円~20万円を自分の財布等で保管します。
②は、上記①現金より生活費(食事等)を現金で支払います。
③は、生活費(電気代等)を自分の口座より支払い、支払った分の現金を母から受領していた現金で別の自由に使える財布に入れて補填する方法です。
上記②と③のどちらも、通常必要な範囲内で使用していると考えられないでしょうか。
本投稿は、2025年10月29日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。