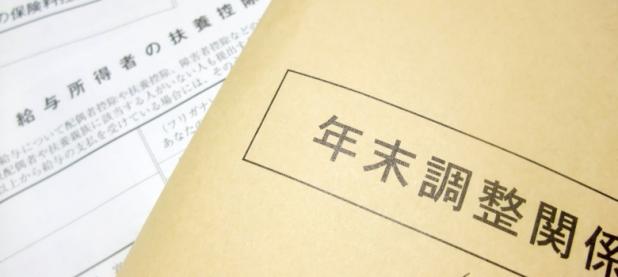配偶者控除について
副業している会社員(育休中)です。
配偶者の年末調整で、私が配偶者控除を受ける予定です。
2023年の給与収入は0円で、副業収入(電子書籍の個人出版)が約30万円あります。
この時、配偶者控除を受けることは可能かと思いますが、質問が2点あります。
1.配偶者控除の「本年中の合計所得金額の見積額」とは、どのように計算すれば良いでしょうか?
年末調整の提出時の時点で、これまでの平均月収(4月副業開始のため4〜9月の月収)で10〜12月分の所得見込みとして計算しても良いのでしょうか?
2.私自身は白色申告で確定申告を予定していますが、配偶者控除の提出時に、年末調整の書類以外で提出が必要なものはありますでしょうか?
(例:私の副業収入を証明する書類など)
税理士の回答

回答します
1 配偶者控除の「本年中の合計所得金額の見積額」とは、どのように計算すれば良いでしょうか?
年末調整の提出時の時点で、これまでの平均月収(4月副業開始のため4〜9月の月収)で10〜12月分の所得見込みとして計算しても良いのでしょうか?
⇒ 年末調整時にはあくまでも「見込み」ですので、ご理解のような計算式でその見込み金額を記載してください。
なお当該「副業」は雑所得に該当すると思いますので、雑所得の金額の算出方法は
収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額 となります。
「必要経費」はその収入を得るための経費になりますので、副業収入にかかる必要経費も見積もるようにしてください。
2 私自身は白色申告で確定申告を予定していますが、配偶者控除の提出時に、年末調整の書類以外で提出が必要なものはありますでしょうか?
⇒ 年末調整時に「副業収入を証明する書類」などの提出義務はありません。会社によっては収支明細書を求めるところもあるそうです。(私見ですがナンセンスだと思います)
ただし、年末調整時にはあくまでも「見積もり」でしたので、年明けに給与所得の方は「源泉徴収票」で、事業や雑所得の方は確定申告書などで、配偶者の方の合計所得金額の確認は必要であると考えます。
会社によりますが、年明けにご主人の会社で確認を求められるかもしれません。
迅速なご回答ありがとうございます!
所得の見積額の計算方法と、副業所得は確定申告書などで金額のみ伝えれば良いこと、2点承知しました。(会社に提出の必要は無いようです)
また、追加で2点ご質問させていただきたいです。
1.
私は副業収入について、
スプレッドシートで売上・経費をまとめた帳簿を作り、事業所得で白色申告予定でした。
白色申告する場合、事業所得と雑所得、どちらのメリットが大きいのでしょうか?
来年は育休が無くなるためどこかで必ず会社に復帰かつ副業は継続予定であること、どちらにせよ帳簿は付けるつもりであること、現時点で開業届・青色申告の予定はないこと、を踏まえてご教示いただきたいです。
2.
今年2023年の所得見込は多くても約40万円なのですが、所得税・住民税の観点で、20万円未満に抑えた方が節税になるのでしょうか?
(現在の副業において、質の高い取引先に依頼すれば経費が高くなり、自然と20万円未満に収まるかと思います)
※もし節税する場合、費用が高くなり手取りが減ることは承知の上で、あくまで支払う税金として、どちらが安くなるか教えていただきたいです。
育児休業給付金はもらっており、育休中のため無職ではなく会社員の扱いかと思いますので、そちらを踏まえてご教示いただければ幸いです。

回答します
1 事業所と雑所得どちらがメリットがあるか
事業所得と雑所得では、事業所得の方がメリット(節税効果)があります。ただし、規模的にもまた、副業としていることからも「雑所得」に該当するのではないかと考えられます。
なお、事業所得は青色申告もできます(青色申告特別控除が最低でも10万円あるため)し、赤字になったときにはその年の他の所得(給与所得)との損益通算や翌年への赤字の繰り越しができます。
2 20万円以下の場合、所得税は「申告不要」とすることができるため、節税になります。
住民税は、所得税が確定申告不要となった場合であっても申告義務があるため、変わりません。
※ 今年、給与収入がない場合は、所得金額が48万円以下であれば所得税の納税額は発生しませんので確定申告義務はありません。
「20万円以下」の規定は給与所得者(給与収入のある人)の規定となるため、大原則として所得税の発生しない合計所得金額が48万円以下であれば確定申告義務はありません。
なお、ご質問の内容が『ご主人の年末調整時の「配偶者控除」』の話から『新たな内容「ご自身の申告について」』のご相談となっていましたので、今後は、新たなご質問の場合は、別途新規に質問とされた方が、多くの税理士の目にとまり、多くのアドバイスをいただけることになりますので、よろしくお願いいたします。
またも迅速なご回答ありがとうございます!
1,2について承知しました。
今後の追加質問については、別途新規の質問として投稿したいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
申し訳ありません。
配偶者控除について1点追加でご質問させていただけないでしょうか…?
育休中ですが、会社の賞与や立て替えていた経費の振り込み等がされており、どちらも給与所得になるかと思います。
そのため、副業の所得が見込み含めて約40万、給与所得が約20万円あるのですが、
副業を含む基礎控除が48万円、給与所得は55万円、合計103万円までは配偶者控除を受けられる認識でお間違いないでしょうか…?

>会社の賞与や立て替えていた経費の振り込み等がされており、どちらも給与所得になるかと思います。
⇒ 育休がいつから始まり、賞与がいつ支払われた額であるか分かりませんので、1点確認してください。
「給与所得が約20万円」なのでしょうか?
その場合、給与収入額は約75万円だったということになります(20万円+55万円(給与所得控除額)=75万円 )
それとも「給与収入金額が約20万円」だったのでしょうか。
【扶養となる基準について】
扶養となる所得基準は「合計所得金額48万円以下」となります。
いわゆる103万円とは、給与所得のみの場合「給与所得控除額が55万円」であることからの目安となります。
なお、基礎控除は「課税所得金額」を算出するための人的控除となりますので、合計所得金額の判断の場合には関係しません。
基礎控除額はご自身の所得税が課税となるか否かの目安となります。、
例えば
合計所得金額48万円 - 基礎控除額48万円 =課税所得金額0円 となりますので、「所得税が課税されませんので申告義務がない」という、先の回答となります。
【合計所得金額】
所得税法では、各所得の性格によりその所得金額の計算方法が異なり、各所得の金額を合計した所得金額が「合計所得金額」とされます。(正確には若干違いますがこのようにお考えください)
〈各所得の計算方法〉
給与所得では
給与収入金額 - 給与所得控除額(最低でも55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)
事業(雑)所得は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 となります。
そこで、
① 給与所得が20万円の場合
給与所得20万円 + 雑所得40万円 = 合計所得金額60万円 となり、扶養から外れます
ただし、配偶者の場合は「配偶者特別控除額」がありますので、合計所得金額95万円までは控除額は同額となります。
② 給与収入金額が20万円の場合
給与所得金額0円 + 雑所得金額40万円 = 合計所得金額40万円 となりますので、扶養(配偶者控除)の対象となります。
国税庁HPから参考に
配偶者特別控除の説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
迅速にご回答いただきありがとうございます!
給与収入が20万円です!大変失礼しました……。
そのため、②のケースとなり、20万円から55万円を引いて、給与所得は0円ですね。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月24日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。