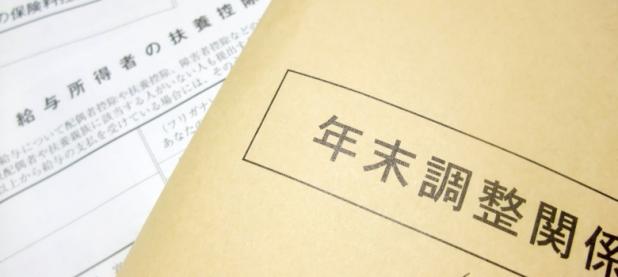年末調整における納付書の書き方について
納期の特例摘要
従業員3名
前半は徴収税額通りに預かり納付20,310円
年末調整したところ、定額減税もあり今回は全員年税額0でした。
また、3人の差引き超過額の合計は前半の納付額と同様20,310円でした。
後半の納付書には
給与等欄の税額は0
本税0
摘要欄:年末調整控除未済額20,310円
と書けば良いのでしょう?
税理士の回答

納付書の記載方法はご理解のとおりとなります。
ただし、「年末調整控除未済額」 ではなく 「年末調整超過額残額」又は「年末調整超過額繰越額」の方が適切と考えます。
繰越した場合は、今後給与の支払時に所得税が出た時に預からず繰越額を減らすということで良いのでしょうか?
また、定額減税があった関係で会社側としては手元に預り金はありません(前半に納付しており後半は定額減税で預かっていないため)が、会社と従業員のどちらかが損していることにはならないのでしょうか?

1 繰越した場合は、今後給与の支払時に所得税が出た時に預からず繰越額を減らすということで良いのでしょうか?
⇒ そのような処理になります。
① 源泉徴収簿の税額欄をご覧ください。
一旦給与の所得税を算出し(算出税額)、そこから繰り越した年末調整の可能額(年末調整による過不足税額)を充当する形で、超過税額がなくなるまで充当していきます。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_03.pdf
② 一旦超過税額を会社が立て替えて「還付」して、翌年以降は本人から所得税を預かり、会社は納税時に還付した金額を充当することもできます。※還付した時は一旦預り金勘定がマイナスになり、給与から源泉を預かったときにマイナス額が減少していきます。
ただし、従業員の給与が少ない場合や退職が見込まれる方がいる時は、次の「③」の方法もあります。
③ 給与額が少なく、2カ月を超えても超過額を充当しきれない場合は、「年末調整の過納額還付請求書」を税務署に提出して、税務署から本人に還付させる方法もあります。
その場合は、源泉徴収簿(全員分・年末調整をした年分(令和6年)と翌年分(令和7年分※))や源泉所得税の納付書の写しなどを添付し、各人の口座番号を記載したものを添付して提出することになります。
なお、会社が代理で一括で受取時は、委任状の添付が必要になります。
※令和7年分は給与の支払前の場合は添付が必要ないはずですが、後日求められることがあります。
なお、審査に時間を要するため、従業員の皆さんには時間がかかる旨お伝えください。
2 定額減税があった関係で会社側としては手元に預り金はありません(前半に納付しており後半は定額減税で預かっていないため)が、会社と従業員のどちらかが損していることにはならないのでしょうか?
⇒ 損をするようなことはありません。
源泉所得税を負担したのは従業員の皆さんになりますので、会社の損にはなりません。
また、定額減税で、年税額が0円になったとき時は「超過額」として翌年の源泉所得税から控除される又は還付が受けられますので従業員の方が損をすることはありません。
仮に先に会社が還付金を立て替えて支払った場合も、納税する際に充当ができますので会社の「損」となることはありません。
なお、定額減税の控除額が残った場合「控除外額」として、市区町村による「調整給付」の計算の根拠になり、令和7年中(あるいは令和6年中)に給付金の支給がありますので、従業員の方々がこの点でも「損」をすることはありません。
本投稿は、2025年01月19日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。