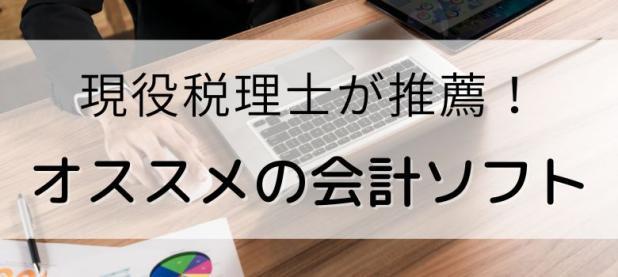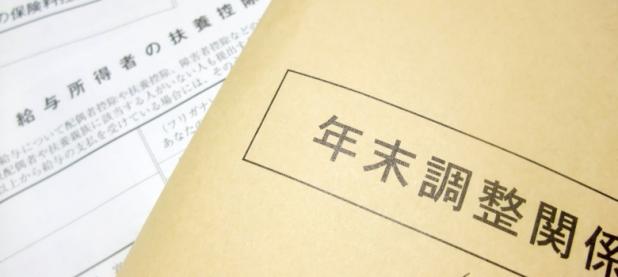消費税の納税がない事業年の税抜経理について
消費税の納税のない年度(免税事業者)の期の帳簿会計入力の税抜経理は、出来ないのでしょうか。問題なく可能なのでしょうか。
消費税の免税事業者の年度に、わざわざ弥生会計やエプソン会計その他を課税事業者という選択●ポチに変更しないと、税抜経理はできませんが、免税事業者を税抜経理することは、経営上や会計上、意義や意味のある行為なのでしょうか。
税理士の回答
免税事業者は税込経理としているのは消費税法上の規定であって、会計上税抜経理をしても問題はないと思いますが、法人税や所得税の所得計算において様々な調整が必要になりますので、現実的には意味のない行為だと思います。
例えば、減価償却資産や棚卸資産は税込に直して減価償却費や期末棚卸高を計算し直さななければならない、中小企業の交際費の損金算入限度額も税込に直して判断し直さなければならない、10万円未満の少額資産や30万円未満の少額減価償却資産の中小特例、一括償却資産の選択は税込に直して判断し直さなければならない等です。
これらを間違えると当然、所得税や法人税の計算を間違えることになります。

1、消費税法上、免税事業者である年度には、税抜経理又は税込経理という考え方はありません。なぜならば、免税事業者の場合には、そもそも消費税自体の存在がないからです。たとえば、課税事業年度において本体価格100円、消費税10円、合計110円の取引(売上)をした場合には、税抜経理の売上高100円、税込経理の売上高110円となります。翌期に免税事業者になり上記と同じ取引をした場合には、取引事実として消費税10円は存在しますが、免税事業者には消費税は存在しなく、売上高110円となります。
2、経理実務上、免税事業者である年度において「いわゆる税抜経理」するというのは、年度間比較を容易にしたいということがあります。免税事業者である年度は、「いわゆる税込経理」になってしまいますので、課税事業年度と比較すると消費税分がそれぞれの数値に上乗せされることになり、単純比較ができないということがあります。なお、免税事業者である年度において「いわゆる税抜経理」をした場合には、決算時に各種の調整が必要になります。
以上、誤解なきようご理解ください。
お二人の先生方、ご回答ありがとうございました。
>現実的には意味のない行為
そもそも消費税自体の存在がない
私は税の素人の経営者ですが、お二人の先生のお言葉と同じことを
何度も2期前3期前に、ぶつけましたが、
結果、設立事業年と2期において税抜経理とされてしまいました。
年度間比較を容易にしたい
おそらくこれを最大重要視したのだと分かりました。そして
>各種の調整
は一切ありませんでした。
私の素人ながらの考えは間違っていなかったことが、改めて分かりました。
第2期において、そもそも税抜税込経理という考え方ではなく、消費税が存在しないと
たとえにありました> 売上高110円
にして2期の、更正の請求や、修正申告ができないか、事業概況書の裏面を再提出できないかを
考えておりました。訂正申告は意味がない?法律にないことも先日、別の先生からお教えいただきました。
第2期に30万円未満の備品がありましたが、これは税込みでも30万円未満でした。
第1期においては固定資産の取得をしており、これが税抜にされ
かつ法定の耐用年数で減価償却費とされております。
1期については、本来、修正申告をしなければならないことが分かりました。
2期は、本来の税込取得の原価価格より小さくなって減価償却費の経理が入力されていますので
2期の減価償却費も変わりようがないようです。
2期の交際費は、税抜で、15表に書かれていますが75万円ぐらいなので
これも変わらないと素人ながら考えました。
やはり2期を税込経理と言いますか
消費税自体の存在がない経理に替え、持続化給付金を申請できないか模索しましたが
無理なのだと分かりました。
ありがとうございました。
蛇足ですが、業績比較を同じ基準でしたいという意図が銀行などの対債権者への説明上の問題であれば、免税事業者の期は税込、課税事業者の期は税抜で決算をしても全く問題になりません。
確かに、消費税が10%の時代、免税で税込の期に消費税分だけ増収したように見えてしまいますが、説明すれば足りることです。
銀行で問題視するのは課税事業者の時に事業年度によって税込や税抜を恣意的に変えて決算方針に一貫性のないことです。
本投稿は、2020年05月17日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。