マイホームマンションを購入三年後に賃貸に出す際の減価償却計算について
どうぞご指導お願いします。
昭和56年築の中古鉄筋コンクリートマンションを2021年1月に購入しました。自分でそのまま住んでいましたが、2024年4月から賃貸に出しました。
建物の価格は8470000円と想定すると、確定申告の際、減価償却できる費用は何を入力すればよいのかの計算がわかりません。どうぞご指導くださいませ。
税理士の回答
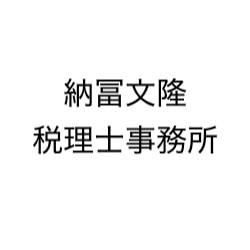
納冨文隆
国税庁ホームページ 中古資産の取得価額を 参照してください。
申し訳ありません。こちらを見たのですが、難しすぎて理解できませんでした。
当方の例を挙げてご説明いただけますと大変助かります。

鎌田浩司
入力するとは、確定申告書作成コーナーなどでの入力ということでしょうか。
ご自身の居住用は「非業務用」、賃貸用は「業務用」といいます。
非業務用と業務用では、耐用年数が異なり(非業務用は業務用の1.5倍)、それに伴い償却率が異なります。
以下の計算は「定額法」です。通常は定額法で大丈夫です。
最初に、非業務用の期間の償却費を算出します。
取得価額は、8,470,000円。耐用年数は70年で償却率は0.015。
経過年数は3年。
(計算式)
8,470,000×0.9×0.015×3=343,035円・・・この金額が償却された金額。
ここからは、業務用の計算。
業務開始時の未償却残高を計算します。
8,470,000ー343,035=8,126,965円
次に業務用の償却。
耐用年数は47年、償却率は0.022です。
8,470,000×0.022=186,340円・・・これが1年間の償却費です。
但し、これは貸付割合が100%の計算ですから、100%でない場合は貸付割合を乗じてください。
貸付が年の中途の場合は、月数按分します。(例)9/12
2024年は4月からなので、186,340×9/12×100%=139,755円
つまり、今年の償却費(経費)は、139,755円。
2024年末の未償却残高は、8,126,965ー139,755=7,987,210円です。
お分かりのとおり、毎年の償却費の計算では未償却残高は関係ありません。
ただし、取得価額847万円の5%になった以降は、1/5づつ償却、最後の1年は1円(備忘価格)残しです。
5%になる際も、残高が5%になるように償却費を調整します。
もっとも、この計算は5%になる42年後でしょう。
大変わかりやすいご説明を感謝いたします。
ご想像の通り、確定申告作成コーナーでの入力をしようとしていての質問になります。
大変恐縮ながら、追加でお聞きしてもよろしいでしょうか。
1.今年24年は途中から賃貸を始めたのと、経費がかさむため、基礎控除48万円をもうけから引くと、バランスがマイナスになりました。ですので、今年は確定申告自体をやらなくていいというりかいでよろしいでしょうか
2.上記の理由から、儲けが出る見込みがあるのは、来年になるので、2025年に確定申告を初めて行うとしたら、不動産取得税を取得時(購入した2021年でそのあと自宅として2024年2月まで使っておりました)に払った40万円の不動産取得税の建物の割合を算定し、購入価格に上乗せして
取得価格として入力してよろしいでしょうか?
3.同じ画面に、前年末未償却残高という項目があります。2025年から始める確定申告のページのこちらの欄には、不動産取得価格に不動産取得税から割り出した建物の値段を上乗せして改めて取得価格を計算し、それを基にして、ご指導いただいたごとくの数式にのっとって計算した2024年度の償却費を取得価格から引いた額を入力する、ということで理解があっていますでしょうか
4.その際、耐用年数を入れる欄があるのですが、こちらは何年と入れたらよいのでしょうか?

鎌田浩司
基礎控除の他にも、社会保険料控除などなどがあり、結果として課税対象が無い、つまりは納税する所得税が無ければ申告不要です。
所得税は強制償却とされますので、申告しない期間についても償却します。
(法人税は任意償却です)
取得時の諸経費を取得価額に入れるかどうかは、非業務用と業務用では扱いが異なります。
今回は非業務用なので、取得価額に加算します。
なお、非業務用に限定すると、
①登記費用(土地建物の固定資産税評価額で按分し建物のみ償却対象)
②不動産取得税(同様に按分か、建物の固定資産税評価額の3%)
③固定資産税相当額~日割りで売主に支払うもの(按分します)
④買入時の仲介手数料や印紙代(〃)
これらを基に、×0.9×0.015×3で計算します。
その後業務用にした訳ですが、当初から業務用であれば、上記の①②はそのまま必要経費に算入、つまり、取得価額に加算しません。
しかし、3年経過後に業務用にしたからといって遡って取得価額から外すということにはならないと思います。
ここのところは、明確な扱いが現状探せませんが、一旦取得価額に加算しますから、そのままで良いと思われます。
つまり、前回の計算で良いと思います。
業務用の減価償却の計算で、訂正があります。
中古資産の耐用年数の計算において、取得時の使用可能期間で計算するか、または、簡便法で計算することができます。
非業務用ではこの計算を行いません。
具体的には、今回は耐用年数47年の内、今年で43年経過になると思います。
この場合は、(47ー43)+43×20%=12.6 端数切捨てで12年とできます。
12年の償却率は、0.084です。
計算式は前回のとおり、
当初の取得価額×0.084です。
(注)10年後くらいで5%になると思われます。
その際は、前回のとおりで、最後は1円残し。
蛇足ですが、取得後にリフォームしていることが考えられます。
その場合は、改めてご質問ください。
修繕と資本的支出の区別、それぞれの金額。
早速の詳細なるご説明を大変感謝いたします。お礼が遅くなり大変申し訳ございません。自分で一度計算してみたのですが、減価償却費の金額思ったより大きく、うれしいのですが、自分の理解または計算が間違ってしまっているか大変不安なのでご意見いただけますと大変幸いです。取得価格にご指摘いただいた経費を足しましたので訂正いたします。
非業務用の期間の償却費
取得価額は 9,138,317 円。耐用年数は70年で償却率は0.015。
経過年数は3年。
(計算式)
9,138,317 ×0.9×0.015×3=370,102円・・・この金額が償却された金額。
業務用の計算
業務開始時の未償却残高を計算します。耐用年数47年の内、今年で43年経過
(47ー43)+43×20%=12.6 12年とします。12年の償却率は、0.084
9,138,317-370,102=8,768,215円
次に業務用の償却, 耐用年数12年、12年の償却率は、0.084
9,138,317 X 0.084=767,619 ・・・これが1年間の償却費です。
貸付が年の中途の場合なので、月数按分します。(例)9/12
2024年は4月からなので、767,619 ×9/12×100%=575,714円
つまり、今年の償却費(経費)は575,714円
2024年末の未償却残高は
業務開始時の未償却残高8,768,215円から
業務用の償却経費 (Apr-Dec)575,714円を引くと、=8,192,501円
という結果になりました。
ここからの理解ですと、2024年に計上できる業務用の一年間償却費は767,619円となり、この先毎年このくらいずつ年間に経費が計上できるということになりましょうか?
そうしますと、家賃は12万円でその他の経費もあるので、控除を加えますと(国民年金、国保、基礎控除など)所得収入がマイナスになります。これはうれしいことなのですが、本当に年間償却費がこんなに引けるのか自分の理解が正しいかどうか非常に不安であります。
ご助言いただけましたら大変幸いです。最後にですが、購入後、自分が住む間、100万円ほど自分で窓のリフォームをしています。リフォーム済みの物件を購入したので、自分で行ったリフォームはこれだけです。このリフォーム代も購入時の仲介手数料などと同様、×0.9×0.015×3 として、建物価格に組み込むことが可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。

鎌田浩司
来年以降毎年、767,619円の償却ができます。
もっとも、未償却残高が9,138,317の5%、456,915に達した後の5年間は、5%の1/5、91,383になります。
100万円のリフォームは資本的支出となります。
これは、新たな取得として、同じ耐用年数での償却になります。
お礼が遅くなり申し訳ございません。ご連絡いただき、大変感謝しております。理解できていないかもしれないので非常に不安です。どうか確認させていただければと存じます。
ご教示いただいた償却方法は、償却方法において、何かの規定があって、未償却残高が建物価格の9,138,317の5%、456,915に達したときは5パーセントの五分の一をかけた額をもって、向こう五年間の償却費となり、この五年間で全部償却する様にする、という仕組みになっているという理解をすればよいでしょうか?
この例でいうと2024年からの償却期間は11年 + 5年で向こう16年間をもって償却が終了することになる、ということでしょうか。
100万円のリフォームについて
“100万円のリフォームは新たな取得として、同じ耐用年数で償却することになる”、とご教示いただきました。これが意味することは、
①-④経費+100万円 ×0.9×0.015×3+ 取得価格=最終的な建物価格として償却し、未償却残高が建物価格の5%に達したら、5パーセントの五分の一をかけた額をもって、向こう五年間の償却費となり、この五年間で全部償却する様にするということでしょうか。
この計算をする際に使う数字で確認させていただきたいことがございます。
①登記費用(土地建物の固定資産税評価額で按分し建物のみ償却対象)
②不動産取得税(同様に按分か、建物の固定資産税評価額の3%)
*③固定資産税相当額~日割りで売主に支払うもの(按分します)
④買入時の仲介手数料や印紙代(〃)
*①” 固定資産税評価額”がどこにあるか調べたのですが、手元にある市から郵送された“固定資産課税資産明細書”によると、”家屋合計評価額”が4,520,199円、”土地合計評価額” 1,645,349,375円、という記載があります。これによると、土地の割合があまりにも大きくなっています。明細書の記載に何かの間違いがあるのでしょうか(市に再確認したほうが良いでしょうか)?
同じ明細書にある、固定資産税相当額(土地)(家屋)との割合は土地が66%で家屋が34%になっています。また、自分が実際に支払った不動産取得税のうち、土地と建物の割合は、土地が58% で192,900 円、建物が42% で 136,900 円でした。さらに、取得価格売買契約書における建物の価格の割合(取得価格)は34%でした。様々な名称があり混乱しております。
①―④で使う全体における、建物価格の割合を調べるためには、どれを使えばよいのでしょうか?
また、②不動産取得税においては、建物用の不動産取得税として支払った額そのものを使ってよいでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
鎌田 先生、
先ほどのメッセージで失念しておりました。実はリフォームとして購入直後、エアコン5台を新規設定した際の部品代と取り付け工事がありました。こちらは36万円ありました。こちらも窓のリフォームと同様に扱っても大丈夫でしょうか?ご指導いただけましたら幸いです。
本投稿は、2024年10月03日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
























