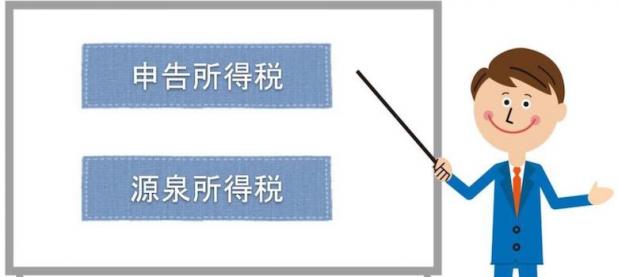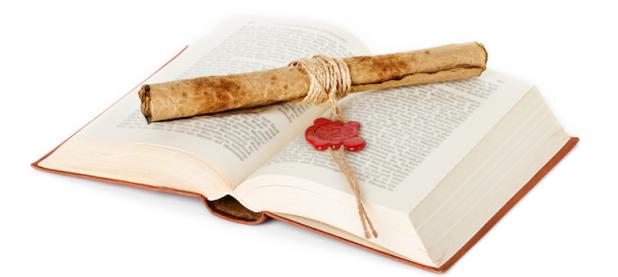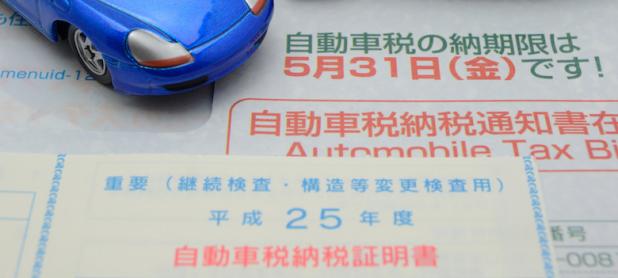同じ会社から別の年に2度退職金を受け取る場合の所得税について
勤続25年で役員へ昇格したことにより、退職金を33年目に受け取り、この度退職となり、35年目の今年、再度退職金を受け取ることとなりました。
33年目には退職共済掛金も受け取っています。
この場合、所得税、住民税はいくらからかかるのでしょうか。
33年目に受け取った退職金と退職共済金からは税金は引かれていません。
計算方法をご教示お願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
役員に昇格した時の退職金は「打ち切り支給」による退職金であると推察します。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、所得税・住民税ともに源泉徴収・特別徴収となります。
提出がない時には、所得税は退職金の20.42%の所得税が源泉徴収されますのでご注意ください。
「打ち切り支給」がされたため、前回の退職金の勤続年数などは引き継がれませんので。勤続年数は役員就任期間(10年)で「退職所得控除額」が計算されます。
退職所得の税額の計算は
(退職金 - 退職所得控除額)×1/2 = 課税退職所得金額
課税退職所得金額 × 税率 =退職所得にかかる所得金額
課税退職所得金額 × 10% =退職所得にかかる住民税額
「退職所得控除額」の計算は、
勤続年数×40万円で計算されます。
勤続年数は、1年に満たない場合は1年とされますので、役員就任日から役員退任日によって決まります
勤続20年以上の場合は計算式が異なりますが、打ち切り支給があった場合は、改めて勤続年数が計算されます。
「税率」は、課税退職所得金額によって異なりますので、国税庁HPから税率の分かる票を添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
住民税は「早見表」を用いると簡単です。参考にしてください。※1/2する前の金額であてはめてください。(添付は名古屋市の早見表)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000075/75483/hayamihyoH25.1.1.pdf
【打ち切り支給のついて】
本来は、引き続き勤務する者に対する一時金は「退職所得」には該当しませんが、役員昇格時や定年時に「打ち切り支給」することが退職給与規定などで決められている時に、その一時金は「退職所得」になる取扱いがされています。
なお、規定などで打ち切り支給が定まってなく、一時金を支給した場合は「賞与」の税額計算(外部支給の場合は一時所得)となりますので、所得税額が大きくなります。
退職金共済は、33年支払って受け取ったのですが、これは今回の計算に入れなくて良いでしょうか?

米森まつ美
回答します
大変申し訳ございません。「退職金」の支給のタイミングを取り違えていたようです。
勤続25年で役員に昇格し、退職金を受け取ったのは勤続33年目だったのですね。
そして勤続35年目に退職された時に、再度退職金をお受け取るということですね。
そうしますと、勤続33年目に受け取った退職金(共済金を含む)は、使用人兼務役員が、使用人兼務役員にはならない役職となったときに「使用人」部分として支給されたものであると、推察いたします。
※退職共済は、原則役員は加入できませんが、使用人兼務役員の場合は、加入することができます。
また、使用人兼務役員が、兼務役員でなくなったときに支給された退職金は、原則役員賞与となりますが、一定の場合は「役員の昇格時の打ち切り支給の退職金」と同様に退職手当(退職所得)と取り扱われますので、その取扱いをしたと推察しました。
そのように考えますと、今回勤続35年目に支給される退職金は、打ち切り支給後の期間(2年間)の退職金と考えられ「特定役員等勤続期間」の退職金に該当しますので、勤続年数は2年となります。
特定役員用勤続期間の退職所得の計算では、退職所得控除後の金額は1/2されないため
退職所得金額 = 退職金 - 退職所得控除額(2年×40万円)で計算されると考えられます。
勤続年数は、端数計算によって切り上げになる可能性がありますので、実際の期間をお確かめください。
私の説明が悪く申し訳ございません。
役員就任前の退職金を支払って無いことがわかり、勤続33年目に社員時代の25年分の退職金を支払いました。
退職共済を解約したのは33年目です。
今回支払う退職金は役員就任後から、現在までの10年間の退職金を支払います。
社員時代の退職金及び、33年目に解約した共済金から所得税等は取らず、退職金として支給済です。
①今回支払う退職金の所得控除は、35年で今まで貰った全ての金額(25年分と退職共済金、今回支給分)で、計算しなおすのでしょうか。
②打ち切りで、10年の控除額として計算するのでしょう。
③、②の場合、33年目に貰った退職共済金と今回の支給額を合算して所得税等を計算して良いでしょうか。

米森まつ美
本来は、役員就任時(勤続25年)に支払うべき退職金を、8年後(勤続33年の時)に支払われたということですね。
今回の退職金は原則で考えるならば「打ち切り支給」の後の支給であるため、前回支払われた退職金と合算して退職所得の金額を計算する必要はないと考えます。控除額は10年で計算します。
しかし、今回のご質問は、誤った支給をされたようですので、責任ある回答ができません。
事実関係を整理したうえで、個別に共済組合及び税務署の相談されることをお勧めいたします。
【確認が必要な事項】
勤続33年目に支給をうけた、会社からの退職金と共済金の「勤続年数」は何年で計算されていたのでしょうか。25年で計算されたのでしょうか。
また、「共済金」の「退職所得の収入すべき時期」は「イツ」になっていましたでしょうか。(「所得税額が算出されていない」との説明だけでは、判断がつきません)
【理由】
共済金などの「外部拠出」は、会社にて役員就任時に支払うこととなっている時に支払う場合等に「退職所得」となり、それ以外の解約などは「一時所得」とされます。
そのため、共済金の退職一時金と会社からの打ち切り支給の退職手当の「収入すべき時期」は同じであり、かつ、勤続年数は25年で計算されるべき支払いと考えます。
もしも、加入期間の33年で勤続年数(控除額)が計算されている場合はそもそもの退職所得の計算や税額計算が誤りとなります。
本来、会社の打ち切り支給時(役員就任時)の退職手当金と勤続25年までの加入期間の共済金の退職一時金で「退職所得」を計算します。
収入すべき時期(年)は、役員就任時となります。
次に、役員就任から退任までの10年間で、「退職所得」の計算をすることになります。
問題として、
共済の解約が勤続期間33年目の時でしたので、退職一時金は勤続25年目の加入期間で計算され、共済金の勤続25年から33年までの期間は、「誤って掛金を掛けた」として、誤った掛金額を会社が返金を受けるべきだと考えられます。
しかし、解約時の理由をどのように記載したかにより、勤続33年までの掛金で「退職一時金」を共済組合が計算している可能性があります。
この共済組合の補正も必要になるのではないかと考えます。
ご確認下さい。
ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。

米森まつ美
正しい回答ができず申し訳ございませんでした。
事実関係を整理したうえで、税務署等に相談され税額の計算をされるようにお願いいたします。
本投稿は、2023年06月19日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。