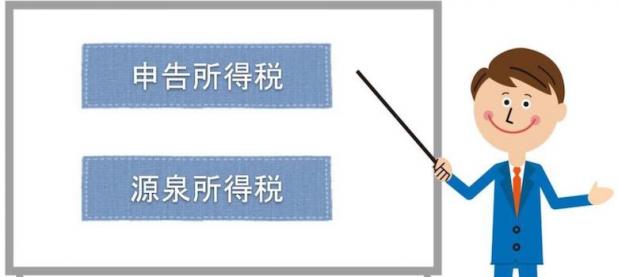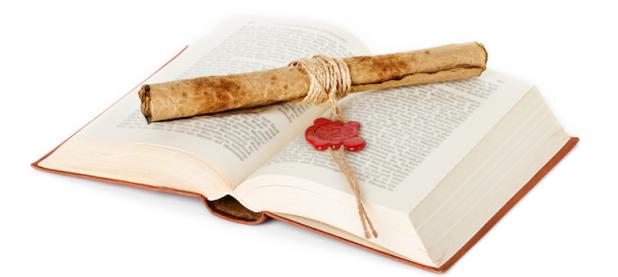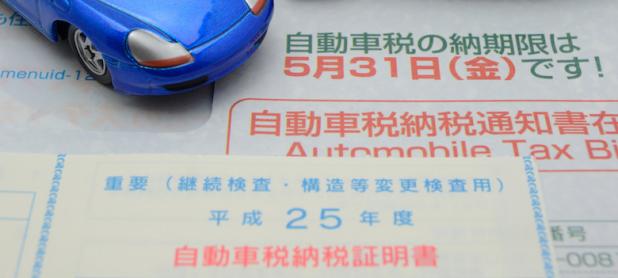不動産を売却したときにかかる税金につきまして
実家の一軒家の売却を考えています。
父母が住んでいました築20年の家ですが、父が施設に入所し、母も私の近居に移住し、空き家になるため賃貸にて貸し出しました。
来年、3月で賃貸契約が満了しますが、借り手より「気に入ったので、このまま購入したい」旨の話がありました。
その場合、税金はどれ位かかるものなのでしょうか。
●現在の父母の収入源は、年金収入と本物件の賃貸収入のみ。
●土地は父が祖父から譲り受け、物件は20年前に4,000万程で父が建てた。
●現在は、土地も建物も父名義。
●売却は、土地建物で2,500万円程になろうかと思います。
私の認識では、購入時よりも価格が下がっていますので、税金はかからず、
翌年、確定申告をすれば所得税の還付が受けられるかと思いましたが
正しいでしょうか?
税理士の回答

2500万×95%×20%=500万弱の税負担でしょうか。
土地は相続による場合、引き継ぐため謄本を取り寄せ、第三から購入された契約書、領収書等で確認。
建物は減価償却していくので、価値は下がっているでしょう。
賃貸せず、売却すればマイホーム30百万控除が利用できたので無税でした。

非業務用資産を業務の用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
上記により、建物の未償却残高が、当初の取得価額の1/3程度のため、売却代金から控除できる取得費が増え、税額は減少すると思います。
ご両親がご自宅にお住まいにならなくなった(空き家になった)のはいつだったのでしょうか。
マイホームを売却したときの特例(3000万円特別控除)は、「住まなくなった日から3年経過日の年末」までに売却すれば適用できます。そして、この特例はその間に建物が存していればよく、建物の用途に制限はありません。従って、ご質問のように賃貸されていても適用可能です。(建物を取り壊して駐車場等としていた場合は該当しません。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご自宅だった土地建物を今年売却予定の場合、2015年までお父様がその建物に住んでいらした場合には3000万円特別控除が適用できます。従って、売却価額が2500万円ほどであれば税金はかからないと考えます。
但し、所定の書類を添付して確定申告を行う必要はありますのでご留意ください。
もし、ご両親がご自宅にお住まいにならなくなった(空き家になった)時期が2014年以前の場合には、上記の特例は適用できませんので、通常通りの譲渡所得の計算が必要になります。
その際の建物の取得費は4000万円ではなく、「自宅として使用した期間」と「貸家として使用した期間」に分けて減価償却費を計算し取得費を算出することになりますのでご留意ください。
皆様
早々のご回答、ありがとうございます。
土地に関しては、長らく祖父名義だったものです。
その土地(更地)に父が1999年に新築。
この時点では、土地=祖父名義、建物=父名義でありましたが、
2010年に土地を父名義に変更しました。
そのため、現在は、土地建物共に父名義になります。
建物については、契約書、領収書等があると思いますが、
土地についての名義変更は無償で行われたかと思います。
(名義変更は、司法書士先生に入って頂いていましたので、
何らかの書面はあるかとは思います)
その後は、下記の通りです。
2011年11月 父施設に入所(母は、一人暮らしに)
2016年4月 母私の近居に引っ越し(空き家に)
2016年6月〜 借り手入居(賃貸に)
現在に至る。

母は生計一。なので、母が住んでいたのは2016/4月から3年以内に該当するので30百万控除が利用できますね。
ただ、申告時に30百万控除の利用を謳い、各種添付資料が必要なため、最寄りの税理士の方に作成いただくのが簡便かとは存じます。
生計一の部分の添付資料必要にあたっての参考として。
(生計を一にする親族の居住の用に供している家屋)
31の3-6 その有する家屋が31の3-2に定めるその居住の用に供している家屋に該当しない場合であっても、次に掲げる要件の全てを満たしているときは、その家屋はその所有者にとって措置法第31条の3第2項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱うことができるものとする。ただし、当該家屋の譲渡、当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡又は災害により滅失(31の3-5に定める取壊しを含む。)をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡が次の(2)の要件を欠くに至った日から1年を経過した日以後に行われた場合には、この限りでない。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(1) 当該家屋は、当該所有者が従来その所有者としてその居住の用に供していた家屋であること。
(2) 当該家屋は、当該所有者が当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後引き続きその生計を一にする親族(所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》に定める親族をいう。以下この項において同じ。)の居住の用に供している家屋であること。
(3) 当該所有者は、当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後において、既に措置法第31条の3、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第36条の2、第36条の5、第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受けていないこと。
(4) 当該所有者の31の3-2に定めるその居住の用に供している家屋は、当該所有者の所有する家屋でないこと。
(注)
1 当該家屋が、上記(1)の当該所有者が従来その居住の用に供していた家屋であるかどうか及び上記(2)の生計を一にする親族がその居住の用に供している家屋であるかどうかは、31の3-2に定めるところに準じて判定する。
2 この取扱いは、当該家屋を譲渡した年分の確定申告書に次に掲げる書類の添付がある場合(当該確定申告書の提出後において当該書類を提出した場合を含む。)に限り適用する。
(1) 当該所有者の戸籍の附票の写し
(2) 当該家屋又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた当該生計を一にする親族の住民票の写し(当該家屋又は当該土地を譲渡した日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)
(3) 当該家屋及び当該所有者の31の3-2に定めるその居住の用に供している家屋の登記事項証明書
ご連絡、並びに詳しい情報をありがとうございます。
① お父様は2011年までご自宅にお母様と共に居住されていた、
② その後、お父様と生計一のお母様が2016年までご自宅に居住されていた、
という事実を基に、居住用財産の譲渡の特例の適用を検討しますと、
まずは、所有者であるお父様が住まなくなってから3年超経過していますので、原則では同特例を適用することはできません。
次に、例外規定の「租税特別措置法31の3-6(生計一親族の居住の用に供している家屋)」の規定を適用する考えがありますが、この規定は生計一親族が住まなくなった日から1年以内に売却することが条件となっています(租税特別措置法31の3-6 本文の但し書き)。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm
つまり、生計一のお母様が転居された2016年4月から1年以内に売却されていれば、居住用財産の譲渡の特例が使えたものと考えられますが、すでに1年超経過した2018年の売却では同特例を適用することは難しいのではないかと思われます。
居住用財産の譲渡の特例は様々な条件をすべて満たす必要があります。当サイトでのやり取りだけですと事実関係と各種条件の確認を見落とす危険性がありますので、関係資料を揃えたうえで専門家(資産税に詳しい税理士)に事前にご相談されることが望ましいと思います。
なお、仮に特例が適用できない場合には、土地は5%の概算取得費を、建物は4000万円を基にした実額の取得費を算定して譲渡所得の計算を行なうことが節税に繋がると考えます。

このサイトでは結論は出ないと思いますので、税務署で、詳細を説明して、確認された方がよいと思います。
本投稿は、2018年07月31日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。