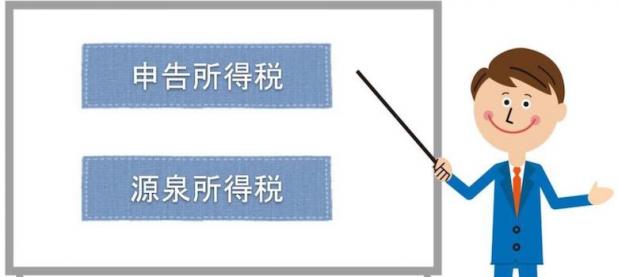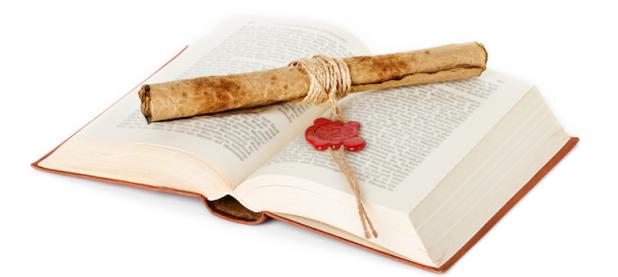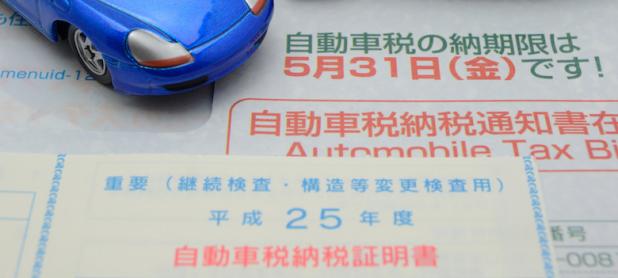サラリーマンの妻は扶養内、個人事業主の場合
103万、130万、150万の壁と言われておりますが
扶養内個人事業主の妻の場合、年収何万以上になるのであれば扶養を外した方が良いのでしょうか?
ネットで調べると給与所得であれば20万と記載がありました。では個人事業主ではいくらになりますでしょうか?
事業所得でその額に行かない場合、アルバイトやパートをして収入を増やしても良いものでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
最初に税務上の「扶養」に関して説明します。
税務上の扶養は、「合計所得金額」が48万円以下の場合、扶養(同一生計配偶者)に該当します。
奥様の収入が事業所得のみの場合、事業所得の金額が、48万円以下の場合は税務上の扶養に該当し、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、48万円超133万円以下の場合は段階的に「配偶者特別控除」が受けられます。
ところで事業所得金額の計算方法は
事業の収入 - 必用経費 = 事業所得金額 となるため、
一概に、収入がいくらまでなら大丈夫かと言えません。
また、事業所得金額が48万円以下である場合、パートやアルバイトを別途されたとしても、扶養の範囲内に収まる可能性はあります。
給与所得に関しては、最低「給与所得控除額」が55万円ありますので、給与所得金額の計算は
給与収入 - 55万円 = 給与所得金額 となります。
そこで、事業所得の金額 + 給与所得金額 = 合計所得金額 が48万円以下の場合は、税務上の扶養に入ることになります。
なお、
103万円とは「税務上の扶養」
130万円とは「社会保険上の扶養」
150万円とは「税務上の配偶者特別控除の金額が減少」
「配偶者等の所得が給与所得」である場合の収入金額の目安して言われています。
給与所得の場合、給与所得控除額が最低55万円ありますので
収入103万円 - 55万円 = 48万円
収入150万円 - 55万円 = 95万円 となるため、
上記の一般的に言われている金額(103万円、150万円)になります。
※ 合計所得金額が95万円から、配偶者特別控除額が徐々に減少します。
社会保険の扶養に関しては、原則収入金額が今後年間130万円以下(見込み)である場合は扶養に含まれます。
ただし、詳細については「社会保険労務士」先生のお仕事の範疇のため詳細な説明ができないことをお許しください。
国税庁HPから、参考箇所をお知らせします。
タックスアンサーNo1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
米森先生
お忙しいところご回答ありがとうございます。
すみません、私の言い方が悪かったのですが、
扶養を外しても損しない額がいくらからというのが知りたかったです。
というのもありがたいことにたくさんお仕事を頂いているので出来るだけそれをお受けしたいと思っていますが、扶養を外した場合何万以上稼がないと損なのか知っていたら、足りない部分はアルバイトかパートで賄えるのではないかと考えているからです。
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

米森まつ美
回答します
申し訳ございません。
『どのぐらい稼いだら「損」をしなか』というご質問の場合、明確な答えを私は持っていません。
目安として、扶養控除や配偶者控除は38万円となります。
ご主人の所得金額にもよりますが、所得税だけを考えたときに奥様が扶養から外れますとご主人の所得税が38万円の5~40%×102.1%分増加します。(「配偶者特別控除」は考えていません。38万円の40%×102.1%は155,100円になります(100円未満切り捨て))
また、当然奥様にも所得税・住民税がかかることになります。
また、奥様の収入が130万円をこえると国民年金や国民健康保険を奥様が支払うことになります。おおよそ、1月あたり3万円の支出になりますので、年間36万円の支出になります。
つまり税務上の扶養から外れる場合は、奥様の収入が130万円以下であれば、ギリギリ損にはならない可能性があります。
そこで、事業所得金額で48万円を超える場合は、全体の収入金額のバランスを考えながら130万円以内に収まるようされるとよろしいかと思います。
そこで私は、『扶養を考えるなら合計所得金額が48万円以内に収まるようにして、少しオーバーするぐらいならむしろ多く稼いだ方が全体としてはとくになる』と説明しています。
このぐらいの説明になり申し訳ございません。
本投稿は、2020年11月24日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。