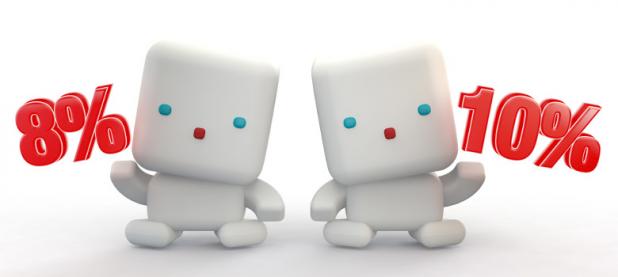インボイスについて
業者A(課税個人事業者インボイス登録あり)とB(免税事業者インボイス登録ナシ)があり、客から一括して料金を頂いてます。
※業者Aが窓口となり一括でお客様から料金を頂く。
客から10000円頂いた場合
業者A5000円売上(内税)
業者B5000円売上(消費税申告ナシ)
これで何か問題ありますか?
税理士の回答
業者Aと業者Bと客の三社間の契約内容によります。
業者Aが客から受け取る業者Bの分が単なる預り金であればご記載の通りです。但し、客がインボイス登録事業者=課税事業者の場合、業者Bの分は仕入税額控除の制限を受けることになります。
業者Bが業者Aの外注等のような形であれば10,000円は業者Aの課税売上、業者Aが業者Bに支払う5,000円は仕入税額控除の制限を受ける課税仕入れになります。
ご記載の内容から回答できるのは上記の通りです。
回答ありがとうございます。
客が課税事業者の場合
業者A(課税事業者インボイス登録あり)
業者B(免税事業者インボイス登録ナシ)
このままだとどのような問題があるのでしょうか?
客が課税事業者の場合
業者A(課税事業者インボイス登録あり)
業者B(免税事業者インボイス登録ナシ)
この状態で客が業者B分の消費税を仕入れ控除とした場合どうなりますか?
先の回答に記載しています。2行目の但し、以下をご確認ください。
実際客は気付かずに仕入れ控除すると思います。
この場合客が税務署から指摘されるのでしょうか?
何故気付かないのでしょう?
ご質問のようにするためには、業者Aが受け取った業者Bの分は便宜上客から預かった単なる預り金である必要があると当初の回答に記載しております。そのためには業者Aと業者Bは客とそれぞれで契約をする必要があります。契約内容によると記載した通りです。
再読してください。
上記のように業者Aが業者Bの分は単なる預り金として処理すると、業者Bは客から求められてもインボイスの発行ができないので、客は業者Bへの支払いは仕入税額控除の制限を受けることになります。、
契約とはどのような契約を指すのでしょうか?
お客さんは特に意識なくお金を払う事が多いと思います。
客はレシートや領収証などにインボイスの登録番号が記載されていなかったら消費税の仕入れの控除は受けられないという解釈で良いでしょうか?
業者Aと客、業者Bと客がそれぞれで契約をし、何度も書いていますが業者Bの収入は便宜上業者Aに一括で振込むことについて三者で合意しているということです。
お客様は業者Bと取引をしていることを知らなければ、業者Aとしか取引していないと認識するのは当然で、業者Aから発行された請求書に基づいて支払う対価は業者Aとの取引の対価としか思わないでしょう。
インボイス制移行後は、支払った事業者(お客様)が受け取る請求書が適格請求書でなければ仕入税額控除の制限を受けます。
当初のご質問の内容からすれば、お客様が10,000円全てについて仕入税額控除を受けるためには、業者Aから5,000円、業者Bから5,000円の適格請求書を受け取らなければできないということです。
もし、上記のような契約がなく当初のご質問が業者Aの受け取る10,000円のうち5,000円を免税事業者である業者Bの報酬として消費税の納税負担を減らそうという主旨であれば脱税です。
形や名目を変えても税は取引の実態で判断します。
業者Bと客との契約や取引実態がなく、客から業者Aに支払われたうちの半分は業者Bのものです、だから業者Aはその半分について消費税の納税義務がありません、と主張しても通らないということです。
お客が課税事業者の場合、
業者A(課税事業者インボイス登録あり)
業者B(免税事業者インボイス登録ナシ)
業者のこの形を変えたくない場合は、
>業者Bが業者Aの外注等のような形であれば10,000円は業者Aの課税売上、業者Aが業者Bに支払う5,000円は仕入税額控除の制限を受ける課税仕入れになります。
上記のよううな形にした上で、
業者Aは10000円分の消費税額を納税
業者Bへ渡す5000円分の消費税分は仕入れ控除できない
と言う事にしないとダメと言う事ですよね?
認識合ってるでしょうか?
お客様が業者Aに支払った10,000円全額について仕入税額控除を受けるためには、ご記載のようにするしかありませんから、ご認識の通りです。
ありがとうございました。
理解できたと思います。
本投稿は、2022年11月26日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。