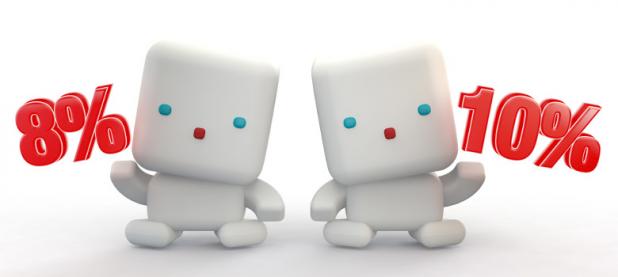インボイス制度で課税事業者に変更する場合、消費税の取り扱い
個人事業主として音楽家(イベント請け合い・講師などもやっています)を営んでいます。現在は売り上げが年間300万円ほどなので免税事業者です。
インボイス制度の導入により、簡易課税者として登録するべきか悩んでおり、まずは以下についてお尋ねしたいです。
【売上側の消費税について】
取引先は企業や個人など幅が広く、企業へは消費税請求をしておりましたが、個人(例えば個人レッスンや指導、謝礼にあたる講演料など)には消費税を請求しておりませんでした。課税事業者になると、こういったものであっても今後は全ての売り上げに対し消費税を請求しなくてはならないのでしょうか?
【源泉徴収税について】
取引先企業から支払われる出演料・講師料などで、源泉税(10.21%)しか課税していない取引が多いのですが、今後は消費税も課税して請求しなければいけないのでしょうか?
【個人への支払いについて】
支払先から5名分の出演料を受け取り、私が他の個人奏者へ出演料を分配する(支払う)場合、個人奏者への支払いに、それぞれの出演料に対する源泉税や消費税額を加算して支払うのでしょうか?
ひとまずは上記についてご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
個人的には、課税事業者になる必要はないのでは?と思いました。
少し長くなり恐縮ですが、ご相談者様が課税事業者であるという前提で回答しますのでご検討ください。
【売上側の消費税について】
企業に対して消費税を請求していたが、個人に対して消費税を請求していないとのことですが、個人に対する売上も消費税の納税義務があります。
例えば、50,000円の演奏料で、ご相談者様のように請求していた場合、次のように考えた上で、消費税は申告納付することになります。
<企業> 50,000円(売上)+5,000円(消費税)=55,000円(税込の売上)
<個人> 45,455円(売上)+4,545円(消費税)=50,000円(税込の売上)
【源泉徴収税について】
仰っていることから察するに、先ほどの例で言えば、5,105円(50,000円×10.21%)を差し引いているので、入金額は49,895円(50,000円+5,000円-5,105円)という意味ですね?
源泉徴収税の金額ですが、税込・税抜はどちらでも良いことになっています(結局、税負担は変わりませんので)。
原則:税込み
例外:税抜き(請求書の中で出演料や講師料と消費税が明確に区分されている場合に出演料や講師料に対して10.21%を乗じても良い)
【個人への支払いについて】
ご相談者様と個人奏者との関係性がわかないところがありますが…ご相談者様と個人奏者は共に個人事業主(雇用のような関係ではなく対等な立場)と考えて一般論でお答えします。
また、(想像ですが)ご相談者様は源泉徴収義務者ではないという前提でお答えします。
上記の50,000円の例で、ご相談者様と個人奏者(1名)の2名で均等に分ける場合を考えます。
受領した消費税はご相談者様が納付しなくてはならないため、足しません。
源泉徴収税はご相談者様の所得税の前払いの性格のため、足しません。
ただし、個人奏者のサービス提供に消費税が掛かります。
つまり、27,500円(25,000円+2,500円)を支払うということになります。
なお、ご相談者様の立場では、受領した消費税と支払った消費税の差額2,500円を納付することになります。
【最後に】
インボイス制度を気にされていたので、最後の例についていくつか捕捉します。
ご相談者様が「免税事業者」であった場合、受領した消費税(5,000円)は納付する必要がありません。一方、支払った得意先は仕入税額控除にすることができません(嫌がりますよね)。
ご相談者様が「課税事業者」で個人奏者の方が「免税事業者」の場合、支払った消費税(2,500円)は仕入税額控除にすることができません(5,000円を納付する必要があります)。
森本先生、こちらからの情報不足にもかかわらず概ねの状況を察していただき、大変感謝しております。
まさにおっしゃるようなやりとり状況ですので、丁寧に記載いただいた計算例、大変参考になりました。
インボイス制度で免税事業者の場合に企業様からは嫌がられる、というのを確かに心配し、簡易課税登録をするべきか迷った中で生じた質問でもございます。
今度は自分が同じ立場になる(仕入れ額控除にすることができない)という事なのだとは全く気付いておりませんでした。
売上高からいっても、このまま免税事業者でよいとのご意見も、とても参考になります。
やはり、もう少しじっくり検討する必要があるのだと痛感致しました。
この度は、必要としている回答を大変分かりやすい例と共にご返答いただき心から感謝申し上げます。
こんにちは。お役に立てて良かったです!
ご相談者様の「売上高からいっても」というのが少し気になりました。
考えるポイントは仕入側です。
インボイス制度の趣旨は益税を排除するためです。
今まで、ご相談者様が受領していた益税がインボイス制度によって実際になくなってしまいます。
つまり、従来は課税事業者と免税事業者とで価格競争を行うと、消費税の益税部分で免税事業者が有利だったが、今後は対等な立場になります。
先の例で考えればわかります。
①課税事業者の税込 55,000円(消費税 5,000円)
②免税事業者の税込 50,000円(消費税 4,545円)
【得意先の立場】
①は5,000円を仕入税額控除できるが、②は4,545円を仕入税額控除できないため、どちらも支出額が50,000円となり、経済的には同じ。
【ご相談者様の立場】
①は5,000円を納税するが、②は4,545円を納税しないため、どちらも手許には50,000円が残ることになり、経済的には同じ。
つまり、課税事業者になって55,000円という価格を維持することと、免税事業者のままで50,000円に値下げすることは同じ価値です。
では、なぜ、免税事業者がこぞって課税事業者になることを検討しているかというと、①の場合に実際に5,000円を納付するのではなく、仕入税額控除を差し引けるからです。
つまり、「私が課税事業者になった場合、どれだけ仕入税額控除があるかな?」が考えるポイントです(当然ながら免税事業者に支払った消費税は控除できません)。
課税事業者になれば結構手間もかかりますし、ご相談者様の周りの個人奏者の方々が免税事業者なのであれば、どこまで意味があるかな~?と思った次第です。
こういう発想で「課税事業者になる必要はないのでは?」と申し上げました。
詳しいアドバイスに感謝いたします。
ありがとうございます!
先生がお察しの様に、私自身は、会場費や雑費・譜面・楽器・・・など、教室やイベント運営に必要な経費が生じた際のみ、購入先に支払う消費税があるくらいで、
毎回発生する支払いは、免税事業者(あるいはお仕事ではない)個人奏者さんへの支払いくらいです。
免税事業者のほうが、奏者への支払いなどに関してもシンプルで済むし損失が少ないのだと改めて理解いたしました。
web情報で「得意先の立場としては免税事業者への支払いは仕入税額控除ができないため、今後は課税事業者との取引が優先される」と見聞きし、「免税事業者が廃業の危機」という通説が周辺にも起こっており、危機感を感じておりました。
が、
先生のご回答を見ると、確かに①も②も得意先様の支払額に変わりが無いことが分かりました。
ということは、「免税事業者との取引は損をする」という通説は関係ない、、、ということで良いでしょうか?
また、私が免税事業者として請求書を出す場合、インボイス開始後は、わざわざ消費税の内訳を明記した合計50000円の請求書ではなく、
50000円(税込)だけで良い、ということでしょうか?
こんにちは。
文字だけでちゃんと伝わるか不安なのですが…
ご相談者様は少し混乱されてますね(わかりにくくてごめんなさい)。
私が申し上げたのは【インボイス制度導入後の課税事業者と免税事業者の違い】です。
ご相談者様が心配されているのは【インボイス制度導入前と導入後の違い】ですね。
インボイス制度の導入によって、確かに益税がなくなってしまうんです。
先の例で言えば、インボイス制度導入前は経済的には次のようになっていました。
得意先:支払額 50,000円(課税事業者なので消費税 5,000円は仕入税額控除できる)
ご相談者様:受取額 55,000円(免税事業者なので消費税5,000円はポケットに)
念のためですが、ご相談者様がポケットに入れていた5,000円のことが益税と呼ばれています。
では、インボイス制度導入後はどうなるか、ですね。
インボイス制度導入後も免税事業者だった場合を考えてみてください。
【得意先の立場】
仕入税額控除ができなくなるため、従来と同じ支出額にしたいと考えます(50,000円(税込)にして欲しい)。
もし、ご相談者様が値引きに応じてくれず、55,000円(税込)で取引したいと言った場合、同じ金額なら課税事業者を選ぶという判断をすることになります。
【ご相談者様の立場】
手元に残るお金を従来と同じにしたいなら値引きに応じたくないですね?
でも、それでは得意先がいなくなってしまうので、値引きしたとします。
そうすると、当然、ご相談様の手元に残るお金が減ることになります。
導入前:55,000円(50,000円+5,000円)
導入後:50,000円
従来は免税事業者はポケットに入れていた益税がなくなってしまうため、「これは大変だ!」と危機感を感じることは正しい感覚です。
ただ、今後は益税がなくなってしまうので、誰かが負担をしないとダメなんです。
そして話は戻りますが、インボイス制度導入後は課税事業者であっても免税事業者であっても益税がなくなってしまうことに変わりはありません。
今後、どちらを選択すべきなのか、という意味では、ご相談者様が「手間」と「どれだけ仕入税額控除があるか」ということを念頭に判断すべきです、という回答になったわけです。
最後に、実際の請求書のお話をされていますが、インボイス制度導入後も免税事業者のままであれば、従来と同じもので構いません。
本投稿は、2021年11月03日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。