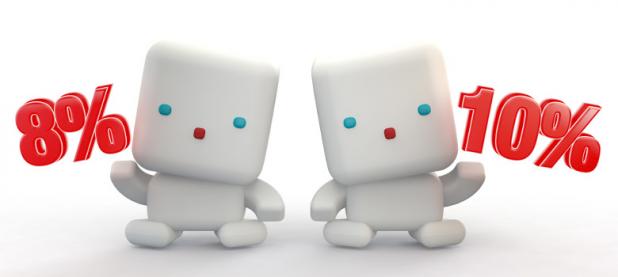インボイスの端数処理1回のルールについて
【消費税額の計算は、上記税率ごとの合計額から算出します(端数処理は一の適格簡易請求書につき税率ごとに 1 回である必要があります)。】
とあります。
税率ごとの対象金額や税額を記載しなければいけないので
各売上の内税額を抜いた本体価格をだすときに、それぞれで端数がでてしまいますが
端数処理は1回しか認められないません。
どのように計算したらよいのでしょうか?
例えば
①100円(税抜)
②115円(税込)
③115円(税込)
の取引を合算して請求書をつくるとき
①は税抜き100円 税額10円
②③は税抜き104.55円 税額10.45円
になりますが、それぞれ四捨五入して
②③は税抜き105円 税額10円
として小計で
消費税対象額310円 消費税20円
とすると、複数回端数処理をしたことになりませんか?
最終的な消費税の計算のときに端数がでるとさらに端数処理が増えてしまいそうです
税理士の回答

土師弘之
請求する消費税を計算する場合、1品ごとに計算するのではなく、1取引ごと(請求ごと)に計算する必要があります。さらに、1取引のうちに複数の税率のある場合には、同一税率ごとにグルーピングして計算することになります。
したがって、上記の場合、
①100円
②104.55円(又は104円)
③104.55円(又は104円)
を合計し、
合計309.1円(又は308円)に消費税率10%を乗じて端数処理をするため、端数処理回数は1回となります。
「一の適格簡易請求書につき」「税率ごとに」「 1 回である必要があります」とは、
「1品ごとに」計算するのではなく、「1取引(1請求書)ごとに」計算するということを言っているのです。
回答有り難うございます
少し考えてみて、計算が複雑にならない方法を検討してみました
請求内容が
①100円(税抜)
②115円(税込)
③115円(税込)
それぞれ税込み額を計算して
①110
②115
③115
合計340円
これが合計請求金額
340÷1.1=309.1円
四捨五入して309円
が税抜き合計(消費税対象額)
340-309=31円
が消費税
という計算と個別に税込み額を計算して(②104.55円(又は104円)
③104.55円(又は104円))それらを足すのとでは
どちらが正しい(一般的)な方法でそうか?
計算が苦手なので判断できないのですが順序が違うだけで結果は全く同じになるでしょうか?
請求額などはすべて四捨五入で計算しています

土師弘之
事業者が不特定かつ多数のもの(一般消費者)に対してあらかじめ表示する価格は「総額表示」が義務づけられていますので、税込価額・税抜価額が混在することはありません。
事業者間であれば総額表示でなくてもいいことになっていますし、消費税の端数処理(切上げ・切捨て・四捨五入)は両社間で合意すればいいことになっています。したがって、どれが正しいということはないということになります。
本投稿は、2022年06月23日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。