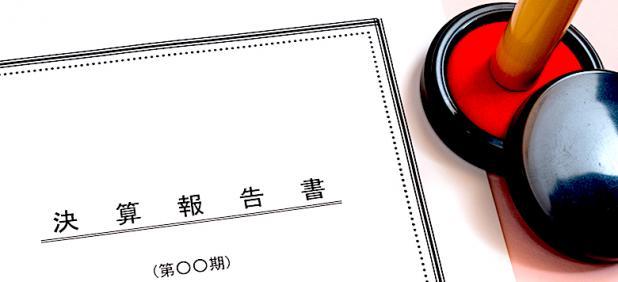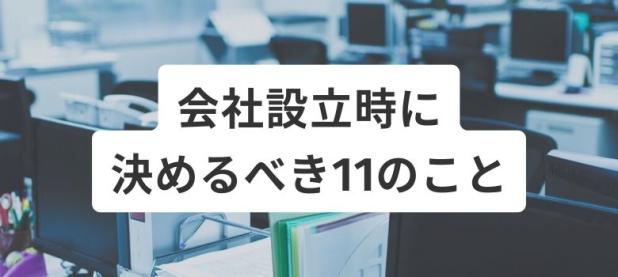海外法人の日本向けサービスにおいて国内の個人や法人が日本円決済を代理で行うこと
こんにちは。
現在ドイツ在住で、日本人向けにIT関連の情報提供をフリーランスとして行っています。具体的には、有料メディア、有料レポートの提供を日本国内の個人や法人に対して一人で行っています。事業拡大のためパートナーを一人増やし、法人化を予定しています。
日本国内で株式会社や合同会社を作ることも選択肢に入れてはいますが、印鑑証明や実印の用意、銀行口座開設にかかる手間、会計にかかるコストや、私自身が日本に住んでおらず日本に事務所等もないため両親の家くらいしか住所登録する場所がなく、且つその住所を特定商取引法に従って公開しなければならない点を懸念しております。
エストニア等のデジタルのみで法人設立と銀行口座の開設ができ、税務会計も明瞭である地域での法人登録が好ましいと思っています。当面日本に帰る予定がなく、ヨーロッパでの事業拡大も考慮に入れているため(提供するサービスは国を選ばないので多言語化して全世界向けに情報発信を行う予定です)、ドイツと同じEU圏にあるエストニアが魅力的だと感じています。
エストニアでの法人設立と銀行開設が実現可能であることは確認済みです。そこでネックとなるのが日本円決済です。Stripeは為替手数料は高くないのですがエストニア未対応、Transferwise borderless accountはエストニア対応ですが日本円未対応です。Revolutも同様。
①決済自体はPaypal等を使いますが、Paypal内で円からユーロに両替するコストが非常に高いため、日本円を日本国内の(私か協力者の)個人の銀行口座に引き出し、それをユーロ送金することは法的に問題がありますでしょうか?
②その場合、この個人に税金がかかったり、税務署からお尋ねが来たりしますでしょうか?
③あるいはこの個人を販売代理店として扱い、利益のごく一部を売上として計上し、それ以外をエストニアの法人口座に海外送金することは法的に問題ないでしょうか?
ちなみに節税が目的なのではなく、時間や手間を含むイニシャルコストやランニングコストを低く抑え、快適にビジネスに集中することを目的としています(もちろん節税できるに越したことはないのですが)。なので国内源泉所得扱いで、日本での課税になっても構いません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

電子化が進んだエストニアを利用されるのですね。実際に日本人で利用される方がいるのですね。驚きました。
さて、①については、単に引き出し時、貸付金になって、それが返済されるだけなので、特に支障はありません。ただ、エストニアにおける税務において、日本と異なる取り決めが無いかの確認は必要ですね。
日本では、役員等に対する貸付については、外部借り入れがあれば紐づく利率以上の利率の設定が求められます。これがエストニアに無いか。
②日本国内の口座からの資金移動については、昨年より口座情報の自動提供が国際間で適用されていますので、お尋ね書は来る前提で、説明できるようにしておけばよろしいのかと存じます。来なければそれはそれでよいですし。
③手数料を払う、ということですね。ご自身が受けるのであれば、居住国における事業所得になるでしょうから、居住国における所得税的な扱いを確認、実施する必要があります。
エストニアにおいては、売上と手数料を両建てして処理しておけば支障はないでしょう。
といった、それぞれの国における税についての扱いがおそらくブラックボックスになってしまうと思いますので、顕在化したときには、お尋ね等に回答することが事実上不可能な状態になってしまうのではないか、というのが気がかりです。ここが自ら解決できるのであればよいのではないでしょうか。
相田先生ありがとうございます。はい、私の知人も既にエストニアに法人設立済みで、実際に利益をあげております。ただ取引が国境を超える場合、専門家を含めて相談できる方がまだ少ないようです。
①Paypalを使って個人口座に引き出す場合、Paypalの登録アカウントそのものをその個人のアカウントとして開設する必要がある(エストニア法人の場合、ユーロでしかおそらく引き出せません)のですが、そうするとサービスの売上自体がPaypalの個人アカウントに一旦入金され、それを個人口座に引き出し、海外送金をしてようやく法人口座に入金されることになります。この場合でも単なる貸付金として処理できるのでしょうか?
②この場合、個人の口座に数百万レベルの入金があり、それをその都度海外送金することになりますが、この個人は何らかの方法でこの入金が自身の所得ではないことを証明、もしくは報告できるのでしょうか?何も報告しなければ税務署はこのお金の流れをこの個人の所得として解釈すると思います。
③ちなみに貸付金というのは法人から個人への貸付という理解でよろしいでしょうか?役員等に対する貸付については調べてみます。追加の情報ありがとうございます。
④手数料を払わない場合、「この個人が自分の口座を法人に使わせる理由がない」という理由で不自然かなと思い、売上の一部をこの個人に提供するのが自然かと思いました。払わなくても良いなら全額横流しが会計的には楽なのでベターです。
はい、問題が起こってからでないと結果が分からないのが若干怖いですね…(大企業であれば会計士を雇って徹底的に調べるのでしょうが)。
⑤ちなみに国内源泉所得に該当するのであれば日本国内で税金を収めたいのですが、個人や法人に対するレポート(イメージとしては有料会員のみが閲覧できるネットメディアやオンラインサロン、M&A情報のレポートをファンドに直接有料配信するリサーチ会社が近いです)の提供で利益を上げた場合(提供は海外法人、従業員(私)は海外在住、顧客は日本、決済も国内で日本円)、国内源泉所得に該当しますでしょうか?

①日本の税務署であれば、それは説明できますね。実態ベースで説明すればよいので。法人口座へは速やかに移動する。それが遅れれば法人から個人への経済的利益の供与(※利子分)が生じるためそれを計上しておけば良い。
ただ、エストニアの取り扱いは不明です。
②問い合わせがある可能性は、日本、エストニア、及び、居住している国から問われる恐れがあります。なので、それぞれの国の税法、租税条約等を確認の上、どう説明すればよいのか、そもそも、それぞれの国において所得に該当しないのかといった検討が必要ですね。
日本では、実態を説明すれば問題はありませんが、他国の取り扱いは不明です。日本では、全体のスキーム図を作成し、説明、根拠としてサンプルとなる取引の入金、出金情報等に基づいた整理、異なるフロー等あればそれについても説明、影響額の試算等、実態に即した説明を準備しておけば良いのですが。
③法人から個人への貸付ですね。意図的にでも、意図しなくても、個人の口座に入り、それが滞留していれば、その間、個人は自由に利用できます。この経済的利得(利子)について所得を認識しなければ、法人が外部から借り入れ、利息を払い、経費にする。
他方、個人は利息を払うことなく、実質的に外部から借り入れをゼロ%の利息で利用することができる。これは法人と個人の所得の付け替えに過ぎませんから。
結果論ではなく、悪意の場合を想定し、日本の税法では設定されています。
他国ではわかりませんが。
④手数料は支払う必要もないでしょう。仮に設定すると幾らにするかが論点となります。日本では、役員報酬は、原則月額同額でないと経費になりません。この手数料で月次で上下させてしまえばその縛りを形骸化させることも出来るでしょう。それは恣意的ではないと設計から、実行、事後的な検証も必要となる作業を組み込む必要がありませんから。
他国ではどうかわかりませんが。
⑤これは、設立国と日本の間での租税条約次第ですね。さらに、アメリカ等の一部州で設立された法人は、日本における法人格を有していないとしてパススルー課税されるか否か、といった裁判が続いています。エストニアにおける法人は、日本の法人税において法人格を有するか否か不明ですが、仮に、法人格を有しない場合、個人の所得として、出資者の方の国と、日本の間での租税条約における扱いが適用される恐れもありますね。
ですので、事前の検討としては、上記の読み込みが必要です。
踏まえて、他国で設立する場合、それら税務的な対応等の負担が生じる恐れがあるため、各国の税法等把握し、各国の税務当局と代理で折衝いただける代理人等を事前に確保しておかないと収拾が付かなくなるのではないかと存じます。いずれの国で会社を設立されても、その国での申告等は、その国の税理士、会計士等に任せることになろうかと存じますが。いずれの方も、そのほかの国の税務当局からの問い合わせについては、対応できないか、対応されるとしても外部の支援等受けることになり、多額の報酬が発生するか、対応不可とされ、ご自身での解決が求められることもあるでしょう。
それらを承知の上、されるのでしょうか。原発のような隠れ債務が生じてしまうのではないか、といった懸念は感じますね。

現実的な選択肢としては、居住されている国で法人を立ち上げ、その国で申告すること。
或いは、日本で立ち上げ、親族に代表になっていただき、お二方は非居住者として役員、或いは、社員として報酬をもらう。日本における申告、納税等は日本に居住する親族の方が代表者として責任をもって担う、といったものになろうかと存じます。
第三の道は、税務リスクは顕在化しないとして何でもありとする。確認できなかった、分かりませんと顕在化した際には手を挙げる。
第三の道は、継続的な事業運営をされるのであれば、慎重に検討されるのがよろしいのかと存じます。
相田先生、ご丁寧な返答ありがとうございました。
そうですね、一応エストニアでの法人設立も視野に入れますが、直近のプロジェクトに関しては日本で登記することを前提に話を勧めたいと思います。税務上、特に問題がなさそうな顧客に対してはEU圏内の法人で対応し、日本円決済を前提とするものは日本で処理するシンプルな形をとりあえずは目指そうと思います。
素早くご丁寧な回答に感謝致します。

EU圏内の国の中においても、おそらく、各国に税法があり、大まかには共通している部分があるでしょうが、国を超えた場合、それぞれ毎に租税条約を確認した上で、何時、何の税を、どこの国で源泉、納付し、申告時、改めて全体を統合して申告、二重納付等を避けるためにどのような書類が必要。
といった整理をされることになろうかと存じます。
サービスをスタートする前に、エストニアで企業された知人の方にお話を伺い、事前に税の処理等煩雑にならないサービスの提供の仕方等検討する必要があるか確認しておくのもよろしいのかと存じます。
勿論、金額的に重要なものになりそうなところから優先して、一定のリスクは含んでおけばよろしいのかと存じますが、そもそもどんなリスクがあるのか、といった全体像は把握されておかれてもよろしいのかと存じます。
日本法人を作成した場合もそれは同様で、具体的なサービス内容等を基に、より具体的な税務リスクの洗い出し等は同様に影響額として○万の影響がありそうだ、といったものでイメージしておかれるのも一案です。
>>事前に税の処理等煩雑にならないサービスの提供の仕方等検討
今回の件ではこれを痛感致しました。法律を変えられない以上、それに沿って事業の組み方を考えていくというやり方がスマートですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月30日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。