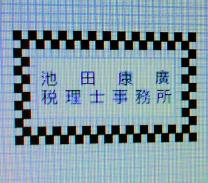共働き、住宅購入に際しての登記割合・贈与税・住宅ローン控除について
おせわになっております。
標題について自己で調べている中で分からなくなったので、ここで相談させて頂きたくご回答の程宜しくお願い致します。
新築物件を購入予定です。
土地建物諸費用込み:4,500万円
ここで、登記による持分割合を夫婦で1:1にしようと考えております。
私(夫)の父から500万円の支援金があり、4,000万円でローン支払いをしていきます。
夫:主債務者、妻:連帯債務者
年収:夫400、妻500
連帯債務の割合も1:1の予定です。
この場合
夫:2,250-500=1,750万の住宅ローン控除
妻:2,250万の住宅ローン控除
となるで間違いないでしょうか?贈与税等問題はないでしょうか。
もし、登記による持分割合を夫:妻=5/9,4/9にした場合
夫:2,500-500=2,000万の住宅ローン控除
妻:2,000万の住宅ローン控除
となるかと思いますが、ここで贈与税等問題はありますでしょうか。
出来れば贈与税が発生しない方向で考えております。
アドバイスの程宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご主人のお父様から贈与を受ける500万円はご主人が贈与を受ければ、贈与税の住宅取得資金の特例を受けることができます。
連帯債務の負担割合を1:1とするとのことですので、各人の出資額はご主人500万円+4,000万円×1/2=2,500万円、奥様4,000万円×1/2=2,000万円となります。したがって登記持分をご主人2,500万円/4,500万円=5/9、奥様2,000万円/4,500万円=4/9とする必要があります。
ご主人の親御さんから贈与を受けた500万円については「住宅取得資金の特例」を適用して、申告すれば非課税となります。
なお、返済割合と登記の持分との差1/2-4/9=1/18について、年間返済額を乗じた金額が奥様からご主人への贈与となりますが、贈与税の基礎控除額が年間110万ありますので、これを超えなければ贈与税は課税されません。
池田様
早々のご回答有難うございました。
質問なのですが、返済割合と登記の持分割合の差1/18とは具体的にいいますと「2,000-2,000=0」という意味でしょうか。?
また、返済割合=登記の持分割合を5/9、4/9にした場合の贈与税は支払いが終わるまでは0円になるという意味でしょうか。?
お手数お掛けしますがご回答の程宜しくお願い致します。
年間のローンの返済額がいくらか不明ですが、仮にお二人の年間返済額が、180万円とすると、負担割合は50%ずつのの各人90万円ずつですが、登記の持分割合が5/9と4/9ですので、ご主人は本来であれば、年間180万円×5/9=100万円を返済しなければなりませんが、返済割合は各人1/2で90万円を返済することになり、差額の10万円、つまり年間返済額180万円×1/18(1/2-4/9のこと)=10万円は奥様が返済することになります。その分ご主人は返済義務が軽減されるので、奥様からの贈与となります。しかし、先に述べたとおり、贈与税の基礎控除が 110万円ですので、課税とはなりません。
池田康廣税理士事務所
池田様
早々のご回答有難うございました。
年間返済額は約140万円の予定です。
そういう意味なのですね。理解致しました。
追記で申し訳御座いませんが、
妻の両親より150万の支援金の話もありまして、この場合住宅所得資金の特例(一般住宅500万まで)を受ける事は出来ますでしょうか?
私の認識では、妻は債務者の一人なので受贈者1人として考えてもいいと思っています。
因みに、今回の新築住宅はZEHや省エネ住宅適用外の一般住宅になります。
特例が受けれる場合:
ローン金額:4,500-500-150=3,850万円
連帯責務の割合1:1=3,850/2=1,925万/一人当たり
<出資額>
夫:支援金500万+1,925万=2,425万円
妻:支援金150万+1,925万=2,075万円
<登記による持分割合>
夫:2,425/4,500=97/180
妻:2,075/4,500=83/180
<妻から夫への贈与>
1/2-83/180=7/180
ローンの年間返済額140万として、140×7/180=5.44万円/年間
大変お手数お掛けしますが、御回答の程宜しくお願い致します。
奥様も贈与税の住宅取得資金の特例を適用できます。一般住宅であれば、受贈者ひとりあたり500万円までの受贈額であれば非課税となります。住宅取得資金を受贈した年の翌年の3月15日までに新築、登記、入居しることが条件ですが、未完成・未登記・未入居であっても、同日までに上棟の状態であれば、適用できますが、申告時に「完成後、速やかに登記、入居する旨の確約書」及び建築業者の棟上げ以降の状況である旨の証明を贈与税申告書に添付することが要件です。様式については国税庁ホームページをご覧ください。
計算については、お尋ねのとおりです。
池田康廣税理士事務所
池田様
早々のご回答有難うございました。
妻も非課税に出来るのですね。
理解致しました。
すごく勉強になりました。
誠に有難う御座いました。
今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年11月29日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。