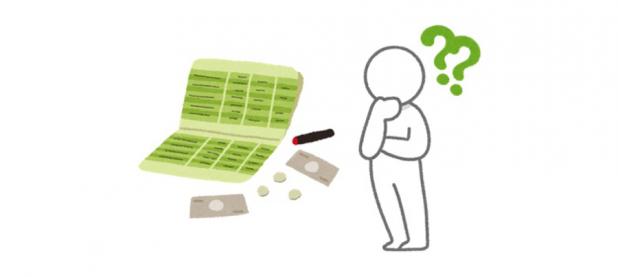相続税 生前贈与 持ち戻し
生前贈与が持ち戻し7年と厳しくなりましたが、
相続税の節税対策に生前贈与を行う場合。
義父からの生前贈与。
相続人(夫)は持ち戻し対象になるため、夫の配偶者(妻)に生前贈与を毎年行う場合は相続人ではない為持ち戻し対象外。
定期贈与にみなされないために、毎年贈与時期と金額を変えて義父から振り込み、贈与契約書を交わす。
こちらで問題ないでしょうか?
毎年少しずつ生前贈与を行いたいと言われましたがこのやり方で大丈夫でしょうか?
孫も持ち戻し対象外ですが、未成年のため口座は親の名義預金とみなされる為、結局は持ち戻し対象になってしまうのでしょうか?
孫に生前贈与は結局は意味ないでしょうか?
相続税の節税でアドバイス頂けたら嬉しいです。
税理士の回答

義父からの生前贈与。
相続人(夫)は持ち戻し対象になるため、夫の配偶者(妻)に生前贈与を毎年行う場合は相続人ではない為持ち戻し対象外。
定期贈与にみなされないために、毎年贈与時期と金額を変えて義父から振り込み、贈与契約書を交わす。
こちらで問題ないでしょうか?
⇒ 1年間に110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されませんし、もちろん、相続人でない方への贈与は、持ち戻しの対象にもなりません。
ただし、相続人でなくても、遺言により財産の贈与を受けたり、死亡保険金の受取人になった方に対する贈与は、持ち戻しの対象です。
孫も持ち戻し対象外ですが、未成年のため口座は親の名義預金とみなされる為、結局は持ち戻し対象になってしまうのでしょうか?
⇒ 相続人以外の贈与は持ち戻し対象外です。
真にお孫様への贈与であり、親がその預金を使用することがなければ、必ずしも名義預金と判断されることはないと思います。

三嶋政美
ご提示の方法は一定の合理性があります。ただし細部に注意が必要です。まず、義父から相続人である夫への贈与は7年以内であれば持ち戻し対象ですが、夫の配偶者である妻への贈与は直系卑属ではなく相続人でもないため、原則として持ち戻しの対象外となります。したがって毎年贈与時期・金額を変え、贈与契約書を取り交わし、都度振込する形を取れば定期贈与と認定されるリスクは低下します。ただし税務当局は「形式」よりも「実態」を重視するため、生活実態や贈与の継続意図が読み取れると否認される可能性も残ります。また、孫への贈与については未成年の場合、管理が親に委ねられるため「名義預金」とみなされるリスクが高く、結果的に祖父から親への贈与と評価されかねません。実効性を持たせるには、親権者の管理を離れた信託や教育資金非課税制度等の活用を検討の余地はあります。節税対策としては「贈与」単独では不安定さが残るため、資産承継全体の設計を含めた総合的な検討が肝要です。
相続税の生前贈与加算(持ち戻し)の対象者は、相続や遺贈で財産を取得する者です。
相続人でも財産を取得しない者は対象外です。
なお、ご主人への贈与が年間110万円以内であれば、相続時精算課税の選択も有効です。
制度改正があり、現状は110万円の基礎控除があります。
相続時精算課税の110万円までは、加算の対象外です。
本投稿は、2025年10月04日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。