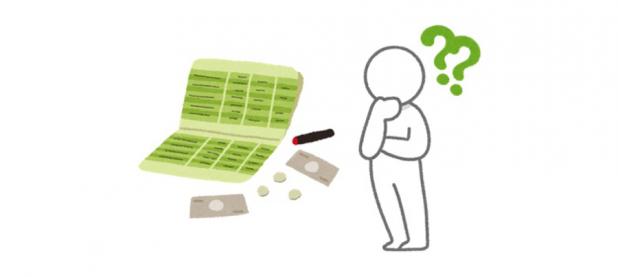教育資金贈与が余りそうな時に毎年目的外で100万円程度出金して減らせるか?
教育資金贈与を祖父から息子に対して行ってもらい、現在残額が900万円あり、息子は16歳です。
思っていたよりも私の年収が減ったために昨今の高等教育の無償化の対象になれる可能性があります。その場合は大学四年間で使い切ることができずに余らせることになりそうです。余らせて放置した場合は息子が30歳時点で贈与税計算になるという理解です。
まとまった金額を残してしまうと贈与税負担が大きいので、たとえば余ることが確定した時点で毎年教育資金目的外で100万円程度を引き出したいと思っています。(銀行によるとは思いますが、現在契約の銀行では引き出しは可能です)
この100万円を、生活費で費消してしまうか、息子に渡すことで実質的に暦年贈与として扱えるように思うのですが、こういった手法は可能でしょうか。
なお、こういった処理を行う際には他の暦年贈与は中止します。
税理士の回答

目的外で引き出しは出来ない、という認識なのですが、これが可能なのでしょうか?それが可能であれば、引き出した時点で残額、全額が贈与税の対象となりますが。非課税は打ち切りとして。

教育資金一括贈与で課税される金額は、受贈者が30歳になった時の口座の残高ではなく、教育資金として精算されなかった残高になります。
つまり、口座から引き出しができたとしても教育資金として銀行で精算されなかった金額は贈与税の課税対象になります。
引き出した金銭を生活費として使用した場合には教育資金としての使用(精算)にはなりませんのでご留意ください。

引出は可能ですが、教育資金支出額にならないため、最後(受贈者が30歳または契約終了時)に贈与税がかかります。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
ご回答有難うございました。
ルール面の理解が進みましたので、対応策としては細かいところ含めて対応となりうる支払いは丁寧に拾って申請し、残額を減らすしかないですね。
ご丁寧な回答有難うございました。

引き出しは以下の方法の選択ですので、教育資金用として引き出し、それを事後的に領収書を提示していない状態、ということでしょうか。意図的にそもそも領収書云々出ない場合の取り扱いは、まだ、顕在化していないので問題となっていないだけで、そもそもの非課税枠贈与自体、どういった対応となるのかの検討はまだ、分かりません。取扱金融機関毎にそのような意図的な対応を知ったときに、どのような反応があるか、それに応じて税務上どのようなこととなるのかといったリスクを抱えることにはなろうかとは存じますが。
3 教育資金の払出し及び教育資金の支払
「教育資金の非課税」の特例の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録を含みます。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るものを除きます。以下「領収書等」といいます。)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(1)又は(2)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければなりません。ただし、1(2)のイ又はロに掲げる事由により教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供していない領収書等については、次の(1)又は(2)の提出期限ではなく、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に対して提出又は提供しなければなりません。
(1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座からの払出方法として選択した場合
⇒ 領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を教育資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
⇒ 領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
(注)
1 上記(2)の場合で、その年中に払い出した金銭の合計額が、金融機関等に提出又は提供された領収書等で教育資金の支払に充てたことを金融機関等が確認した金額の合計額を下回るときは、金融機関等が教育資金支出額として記録する金額は、その払い出した金銭の合計額が限度となります。
2 上記本文又は(注)1の領収書等には、「教育資金の非課税の特例」の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものや1(2)のイ又はロに掲げる事由により教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものは含まれません。
3 上記(1)又は(2)の選択をした後は、その後において選択の変更はできません。

意味不明な回答は、ご相談者を困惑させるだけなので、慎むべと思います。
本投稿は、2018年06月30日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。