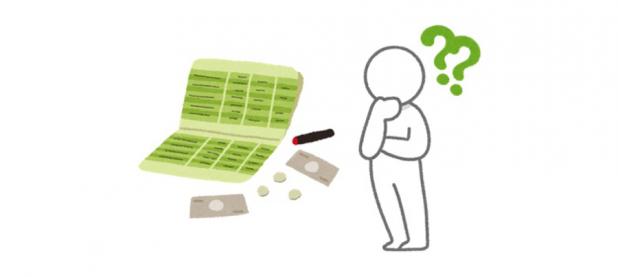相続税や贈与税がかからない財産のもらい方
私には90歳前後の離れて暮らす祖父母がいて、結婚して姓は変わっています。現在、0歳と4歳の子どもと旦那がいます。
最近、金額にして1000万円近くのお金を生前に渡してくれる話を祖父母からもらいました。
ただ、可能であれば節税したくて調べている所であります。
そこで質問がございます。
①110万円であれば贈与税がかからないとのことですので、私と息子たち2人分の口座にそれぞれ110万円ずつ入金してもらおうと思いますが、幼い年齢でも可能でしょうか?ちなみに現金での手渡しを避けた方が良いと聞きましたが、何故ですか?
②教育資金の一括贈与の特例に関しては、今は持病なく認知も良好な祖父母ですが高齢であるため、息子が小学生になるかならないかで亡くなる可能性が高いことから利用を考えていません。
そこで、息子の幼稚園に必要な費用をその都度もらう事にし、3~4ヶ月分ずつまとめて振り込みしてもらうか、現金でもらうかを考えています。
また、通常考えられる額の範囲なら、生活費もその都度であれば贈与税がかからずもらえると知りました。
上記の110万円の贈与と併用して、その都度もらう教育費と生活費を贈与税が発生せずに貰う事はできますか?
③祖父母が残り数年は生きてると想定した時、1000万円くらいのお金をもらい受けるために節税効果が高い方法は他に考えられるでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありませんが、よろしくお願いできると幸いです。
税理士の回答

① 幼い子供さんでも、その子供さんの親権者(両親)が贈与に関して同意していれば贈与することは可能です。「親権者が同意している」ことを立証できることが重要になりますので、親権者が同意していることを明記した贈与契約書を作成して保存しておくようにしてください。
贈与する場合には現金手渡しでは贈与した事実が形で残りませんので、口座振り込みで実行して頂くのが望ましいです。
② 祖父母と孫は直系血族ですので、お互いに扶養義務者に該当します。そして、扶養義務者相互間において必要な時に必要な金額の生活費や教育費を贈与する場合には、贈与税が非課税とされています。従って、非課税に該当する生活費や教育費の贈与と、贈与税の基礎控除額(年110万円)以下の贈与は併用して行っても問題ありません。
③ ご主人も含めた4人に贈与して頂く、110万円にこだわらず少々贈与税を納める位の金額の贈与をして頂く(120万円の贈与で贈与税は1万円、130万円の贈与で贈与税は2万円です)、生活費や教育費の非課税の贈与を上手に活用する、といった方法が考えられます。
服部先生
ご丁寧な教示をいただき、感謝を申し上げます。
おこがましいですが、追加で質問させていただきたいです。
①110万円を貰う時に、贈与税はかからないのに贈与契約書を作成しておくべきなのは何故ですか?
②110万円や教育費、生活費の贈与において祖父母から現金で貰う場合、現金で受け取ってから私たちの口座に入れる形では贈与されたという事実は残りにくいでしょうか?
③そもそも非課税の範囲内であっても、「贈与」という形を残さないと後々にどんなデメリットがありますか?
④必要な生活費や教育費用をその都度 貰う贈与の場合も、それぞれ贈与契約書を作成するべきでしょうか?
⑤贈与契約書は、祖父母が原本を私がコピー分をもって保存するのが一般的でしょうか?
あつかましいお願いになりますが、ご回答いただけると幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
① 贈与は「あげる人の意思」と「もらう人の受諾」の両者の合意があって初めて成立するものになります。もらう人が受諾(認識)していない状況での資金移動は贈与とはみなされず、名義預金と認定される危険性があります。あげる人の意思ともらう人の意思を明確にするためにも贈与契約書を作成しておくことが実務上は重要になります。
② 預金からの引出しと預け入れが、同日に同額で行われていれば分かりやすいかもしれませんね。いずれにしても、現金のままでの保管ではなく、口座に預け入れるなどして、資金の移動があったことを明らかにできる方法が望ましいと考えます。
③ 上記①の「名義預金」と疑われるデメリットが考えられます。
④ 生活費や教育費のその都度贈与の場合は契約書までは必要ないと思います。
⑤ お考えの方法でも宜しいと思いますが、できれば両者で保存しておかれるのが望ましいと考えます。
服部先生
見ず知らずの私に、ここまで詳しくご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
今まで医療関係の仕事と家事をやってきたのみで、身近なところにある税については無知です。この育児休暇中に知識を得たくて、税法を読んだり本で勉強してますが、解釈の仕方に曖昧さがあったり、突っ込んで知りたい内容までは書かれてないため行き止まります。なので、こうして教えてくださる服部先生には感謝しております。
重ね重ねの質問になりますが、よろしいでしょうか?
①現在、93歳の祖父と88歳の祖母は運転してますが、この先は出来るだけ控えたいとの方針から預貯金を引き出して自宅管理に切り替え始めたそうです。田舎に住んでおり、最寄りの銀行がある街まで車で片道30分はかかるので、確かにそろそろ運転は怖いかと思います。
そこで、贈与を受けるとしたら現金になり、私が自身の口座に振り込みする形が現実的ですが、その事情を税務署に話せば理解してくださるでしょうか?口座間でのやり取りがベストなのは分かりましたが…やはり守ってた方がいいのはいいのですよね。
②教育費と生活費を現金で貰うために3ヶ月に一度、祖父母の家に行こうと考えています。教育費と生活費を合わせて3ヶ月分で60万の贈与を現金で受けた後に、自身の口座に振り込みする計画でいます。金額的に常識の範囲内でしょうか?
もちろん全額を使い切るつもりです。

詳細なご事情をお聞かせ頂きありがとうございます。
追加のご質問につきまして回答いたします。
① 現金を引き出して自宅管理される状況ですと、ご高齢のご両親がわざわざ遠くの銀行に行って振込するのは難しくなりますね。そのような状況であれば、まずは贈与契約書をしっかりと作成し、贈与された現金をそのまま受贈者の口座に預け入れて頂く方法で宜しいと思います。贈与された現金が貰った人の口座に入金された履歴を残しておくことで、現金贈与の事実の証明材料になると考えます。
② 教育費や生活費の資金の非課税贈与につきましては、受け取る人にその需要(必要性)があり、基本的には必要な時に必要な金額を受け取って、教育費や生活費に直接充てられる場合が該当しますので、こちらについては相談者様の口座にわざわざ振込されなくても宜しいと思います。家計簿等(ノートなどのメモでも結構です)に受け取った日と金額を記録し、その全額が日々の生活費等で消費し、預貯金等に残っていない状況になっていれば宜しいと考えます。
服部先生
数回にわたり、誠に分かりやすく教えていただきありがとうございました。
これから贈与契約書の書き方について勉強しようと思います。
ありがとうございました。
服部先生
生活費や教育費の資金の非課税贈与の件で、数日前に相談させていただいた者です。
何度もお尋ねしていてお手数かけています。
生活費や教育費の非課税贈与を受けるには、生活費等に困窮してる収入状況である事が前提が必要でしょうか?
今のところ、旦那の稼ぎと私の育児休暇中の手当てを合わせたら家計はやり繰りできる収入は有難いことにあります。こういう条件下でも、贈与を受ける事は可能でしょうか?
給料をいくらか貯蓄に回しても大丈夫なものですか?
以上、いろいろ調べても回答を見つけられないので、教えていただけると幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
非常に難しい判断になりますね。
本件に関しては贈与の内容を分けて考えることが必要かと思います。
まず、「祖父母から孫に対する教育費や生活費の贈与」を前提とした場合、祖父母と孫との親族関係は直系血族の関係(扶養義務者)に該当しますので、その教育費や生活費の贈与が必要な都度・必要な金額の贈与で、直接教育費や生活費に充てられているものであれば贈与税の課税対象にはなりません。このことは、受贈者(孫)の親(本件の場合は相談者様やご主人)に収入が有るか無いかに関わりはないものと考えます。
なお、子供さんが例えば無職の学生で一人暮らしをしているようなケースであれば、祖父母が授業料を支払ったり孫に仕送りをすることで、教育費や生活費の贈与の実態が説明しやすいですが、本件のように0歳と4歳ですと、保育園や幼稚園などの教育費の支払いは実態の説明が可能かもしれませんが、生活費の贈与は線引きが難しいかもしれませんね。衣類や遊具等を買ってあげるといった具体性があるとよいかもしれません。
次に、「ご両親から相談者様への生活費の贈与」を前提とした場合、こちらも親と子の直系血族の関係(扶養義務者)に該当しますので、生活費の贈与が必要な都度・必要な金額の贈与で、それが直接生活費に充てられているものであれば贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、この場合には生計の状況も判断材料に加わるものと思われます。
つまり、同居(生計一)の家族の場合には、所得税法のコンメンタールでは「同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているもの」と解説されているため、生活費を誰が出しても特に問題となることはありませんが、本件のように親子が別生計である場合、日常生活の資を共通にしていないわけですから、相手方が収入面で生活が困難である等の特別の事情がない限り生活費を融通するといった事態は想定できないと考えます。そのため、生計別の親族に対し生活費として贈与するものについては、受贈者の収入状況によっては非課税となる贈与には当たらないと認定されるリスクは考えられます。
この点につきましては事実認定の問題になると思いますのでご留意頂ければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部先生
微妙な解釈を踏まえた貴重なアドバイスをいただきまして、感謝を申し上げます。
理解を深めるために何度も読み返しました。
無難に、幼稚園代と通信教育費代のみ贈与してもらうように決めました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月20日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。