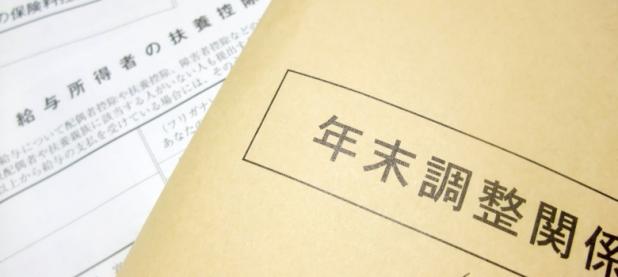定額減税の対象になるのか分からない
お世話になります。定額減税について質問させていただきます。
私は個人事業主で妻を青色専従者とし給与を支払っています。
自分のパターンが、定額減税や調整給付の対象となるのかどうかが分からず困惑しています。
令和5年度は以下のような形になり、2人とも給付金の10万円を受け取っております。
自分→所得税:非課税/住民税:均等割のみ課税
妻→所得税:非課税/住民税:非課税
所得税の定額減税は令和6年度の収入及び所得が対象、住民税の定額減税は令和5年度の収入及び所得が対象と認識しております。
そこで、以下の質問です。
「1」令和6年度の所得も同じような状況であれば2人とも「定額減税」の対象にはならず、自分の確定申告や毎月の妻への給与支払・年末調整時の定額給付の事務処理などは発生しないという考え方で合っていますでしょうか?
「2」令和6年度の収入が急激に増えて、所得税が課税される形になった場合は所得税のみ定額減税の処理が発生するということでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどお願いいたします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
ご質問者様と青色専従者の配偶者様の方の定額減税に関する状況について、ご質問の内容を踏まえて回答いたします。
現状の確認
令和5年度の状況:
•ご本人:所得税非課税、住民税均等割のみ課税
•配偶者様(青色専従者):所得税非課税、住民税非課税
•両者とも10万円の給付金を受給
質問1への回答
令和6年度も同様の状況であれば、以下のようになります:
•ご本人:所得税の定額減税は対象外、住民税の定額減税も対象外
•配偶者様(青色専従者):所得税の定額減税は対象外、住民税の定額減税も対象外
したがって、ご認識の通り、定額減税に関する事務処理は発生しません。ただし、令和6年度の収入状況によっては、新たに設けられる「不足額給付」の対象となる可能性があります。
質問2への回答
令和6年度の収入が増加し、所得税が課税される状況になった場合:
•所得税の定額減税:対象となる可能性があります。確定申告時に定額減税の適用を受けることになります。
•住民税の定額減税:令和5年度の所得に基づいて判断されるため、対象外となります。
この場合、確定申告時に所得税の定額減税の処理が必要となります。
追加の注意点
1.青色専従者の給与に関して:
•年収103万円以下の青色専従者は、原則として定額減税の対象外となります。
•ただし、年収が100万円を超える場合は住民税の所得割がかかり、住民税のみ定額減税を受けられる可能性があります。
2.不足額給付について:
•定額減税の恩恵を受けられない低所得者向けに、新たに「不足額給付」が設けられています。
•青色専従者等で「所得税及び個人住民税の税額が0円」、「扶養親族に該当しない」、「低所得世帯向け給付の対象外」といった条件を満たす場合、原則4万円が支給される可能性があります。
3.収入増加の影響:
•令和6年度の収入が増加した場合、翌年度の住民税にも影響が出る可能性があります。将来的な税負担の変化も考慮に入れる必要があります。
以上の点を踏まえ、収入状況の変化や制度の詳細な適用条件については、最新の情報を確認し、必要に応じて税務署や自治体に相談することをお勧めします。
参考の資料(URL)までお送りいただき、ご丁寧な回答に感謝いたします。
「不足額給付」についても存じ上げなかったため、勉強になりました。
現在は、理由あって夫婦で別世帯となっており、妻の世帯は非課税世帯となっているため「低所得世帯向け給付の対象外」という条件がクリアできないのではと思っております。
度々の質問で恐れ入りますが、こちらの「不足額給付」は年末調整や確定申告の手続きとは別で、自治体などで対象者に給付されるものだと認識しておりますが、私の認識で間違いないでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、お手すきの際にご確認いただけますと幸いです。

ご質問ありがとうございます。
詳細については自治体に応じて取扱いが違うのですが、以下に説明を記載いたします。
不足額給付の概要
「不足額給付」は、主に2つのタイプがあります:
・不足額給付I:
当初の調整給付金の算定後、実際の令和6年分所得税額や定額減税額が確定し、不足が生じた場合に追加で給付されるものです。
不足額給付II:
定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しない方向けの給付金です。
給付の手続き
・不足額給付は、年末調整や確定申告の手続きとは別に行われます。
・自治体が主体となって対象者を把握し、給付を行います。
・多くの場合、対象者に対して自治体から通知や案内が送られる予定です。
給付の時期
・不足額給付は、令和7年度(2025年度)以降に実施される予定です。
・具体的な給付時期や手続きの詳細は、現時点では未定の自治体が多いようです。
ご質問の事例について
ご夫婦別世帯で配偶者様の世帯が非課税世帯の場合、確かに不足額給付IIの対象とならない可能性が高いです。
ただし、不足額給付Iについては、ご自身の所得状況や定額減税の適用状況によって対象となる可能性があります。
参考リンク
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/t_fkyuuhu.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/seikatsufukushika/2_2/44605.html
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shiminze/choseikyufuqa.html
https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kyufukin/19804.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2630/2024kyuhukin/chosei_kyuhu.html
早速のご回答ありがとうございます。
不足額給付Iについては対象になる可能性があるとのこと、細かくご説明いただきましてありがとうございます。
私が住んでいる自治体でもまだ情報が掲載されていないようなので、今後掲載される情報を確認したいと思います。
この度はご丁寧に対応いただきましてありがとうございます。
寒さの厳しい日が続いておりますが、どうぞお体には十分お気をつけいただき、ご自愛くださいませ。

ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年01月05日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。