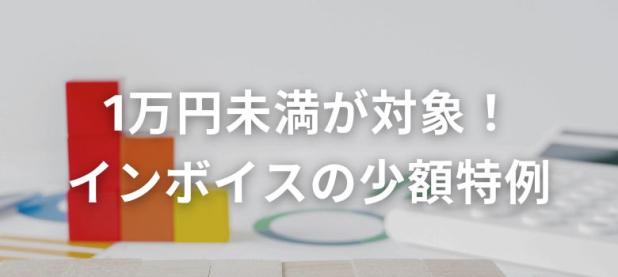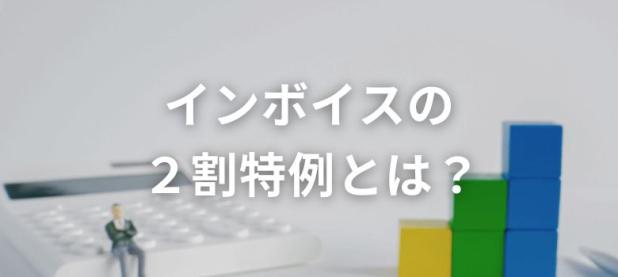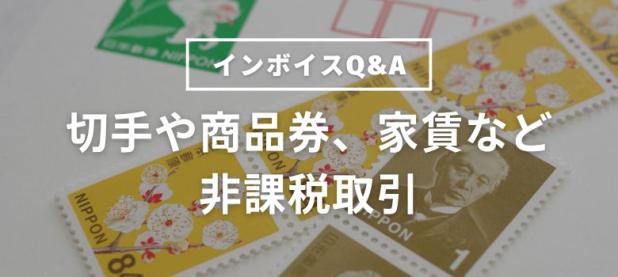福利厚生で支給する補助に対してのアドバイスをいただきたいです
会社の福利厚生でマッサージ補助金があり、制度設計をしています。
社員が施術を受け、事後申請してもらい、月1回、上限5000円までで、給与のタイミングで支給といった内容です。
インボイス非対応店舗でもOKとする予定ですが、これに対してデメリットや懸念点などあったらご教示いただきたいです。
また、保険適用の施術に対して、支給するのは問題あるかどうかもあわせてご教示頂けますと幸いです
税理士の回答

1. インボイス非対応店舗を認める場合のデメリット・懸念点
- 経費精算時の不備
インボイス非対応店舗の場合、消費税仕入税額控除が受けられません。
- 仕入税額控除を前提に福利厚生費を計上すると、消費税の納税額が増加します。
- 課税事業者の場合、控除ができない分、コストが増える可能性があります。
- 管理の煩雑さ
インボイス対応・非対応の店舗が混在すると、会計処理や管理が複雑になります。経理担当者の業務負担が増加するリスクがあります。
-税務調査時の指摘
福利厚生費として認められるかどうかの判断が厳しくなる可能性があります。具体的な利用実態や社内規定に基づいて明確に証拠書類を整備する必要があります。
2. 保険適用の施術に対する支給の問題点
- 二重補助のリスク
健康保険が適用される施術(例: 整骨院での施術)は、社会保険制度によりすでに一部負担金が軽減されています。その費用に対して会社がさらに補助を出すと、福利厚生費としての正当性が問われる場合があります。
- 福利厚生費の認定可否
税務上、福利厚生費として認められるかどうかは「全社員に公平に提供されるか」が基準です。保険適用の施術が対象になると、通常の福利厚生として認められない可能性があります。
- 対策: 社内規定で「保険適用外の自費診療のみ対象」とすることで、福利厚生費としての適正性を確保できます。
- 公序良俗違反の可能性
健康保険は公的制度ですので、保険適用の治療費を福利厚生として支給することは、制度の趣旨に反するとの指摘を受ける可能性があります。
改善策とアドバイス
1. インボイス非対応店舗に関する対策
- 福利厚生費として「インボイス非対応店舗も認めるが、消費税控除はしない」と明確に社内でルールを定める。
- 会計処理を簡素化するために、補助金の利用状況や店舗区分をシステムで管理する。
2. 保険適用の施術に関する対策
- 「自費診療(保険適用外)」に限定することで税務リスクを回避する。
- 社内規定を明確にし、申請時に領収書の確認を必須とする。
- 「医療行為を除くリラクゼーション施術」と範囲を限定するのも有効です。
3. 福利厚生の正当性の確保
- 補助制度が「全社員を対象」とし、公平に適用されることを文書化する。
- 上限金額(5,000円/月)や利用回数(月1回)のルールは維持し、乱用を防ぐ。
まとめ
- インボイス非対応店舗を認めることは可能ですが、仕入税額控除ができない点や管理の煩雑さがデメリットです。
- 保険適用の施術への支給は避ける方が無難です。税務上のリスク回避のためにも「保険適用外の自費施術のみ対象」とするのが適切です。
- 明確な社内ルールと領収書確認を徹底することで、制度設計の透明性と税務リスクの軽減が可能です。
それぞれ懸念点やデメリットの記載ありがとうございます。
マッサージ店については、インボイス非対応店舗も多くあると思うので、対象とするかは検討していきたいと思います。
保険適用の施術については、対象外にしたほうがよさそうだなと感じました。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年12月17日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。