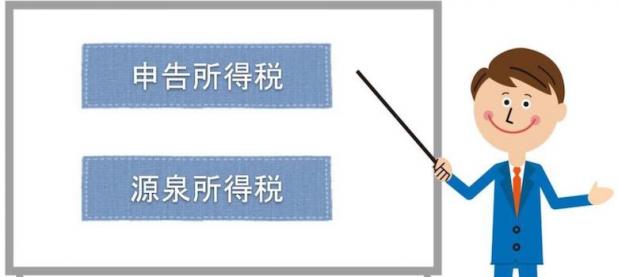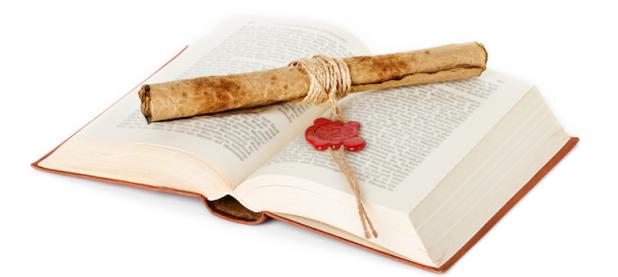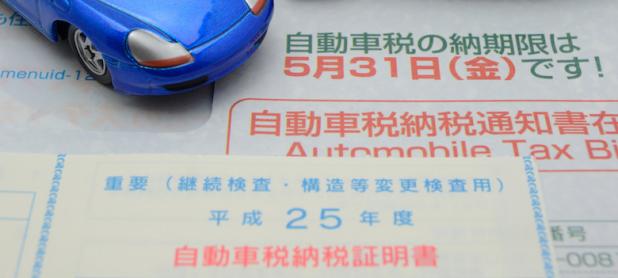非居住者の国内源泉所得となる範囲について
アメリカ在住の「非居住者」ですが、先月日本の企業と業務委託契約し、翻訳の仕事を始めました。
私の場合は日本国内に住居やオフィスを所有しておらず、業務はすべてアメリカ国内で行っているので国内源泉所得はなく日本企業からの源泉徴収も発生しないと考えるのですが、日本企業側としては私の業務内容が翻訳のため著作権の使用料として源泉徴収を行うと伝えられました。
翻訳業務の場合、「著作物の使用・譲渡」となるのは理解できますが、その「著作物の使用」を日本国内ではなくアメリカ国内のみで行い、しかもその著作物を用いた翻訳業務をすべてアメリカ国内で行い得た報酬でも源泉徴収の対象となるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「国内法」によれば、著作権の使用料は「使用地主義=著作権の使用地が国内の場合、国内源泉となる」になっています。
日米租税条約においても同様な規定となっています。
なお、租税条約で国内法と異なる規定がある場合は租税条約が優先され、多くの国との租税条約では支払者の所在地が日本にある場合は国内源泉とされている(債務者主義)ので、日本の企業はそのように誤解しているのではないでしょうか。
若しくは、翻訳した著作物は日本で複製等をされるのであれば、「国内使用=国内源泉」となりますので、その点を持って企業が説明されているのではないでしょうか。
ただし、仮に「国内使用」であったとしても、日米租税条約上「著作権の使用料」は免税とされているため「特典条項租税条約の届出書」(「租税条約の届出書」と「特典条約の付表」、居住者証明書を提示しコピーを交付)を提出することにより免税となります。
企業の方ともう一度お話になることをお勧めします。
日米租税条約第12条をご確認ください。
※外務省のHPからの資料のため読みづらいですが、P34がその箇所になります
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_1a.pdf
租税条約の届出書 ・ 特典条項の付表 を 参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf

米森まつ美
一部訂正します
日米租税条約が「使用地主義」なのではなく、規定がないため「国内法=使用地主義」になっています。
申し訳けございませんでした。
早速のご回答ありがとうございました。
念のため再度確認させていただきたいのですが、私がアメリカの居住者で、日本企業から委託されている著作物を用いた翻訳の業務をすべてアメリカ国内で行い得た報酬は、「著作権の使用料」については日米租税条約で規定がないため、国内法の「使用地主義」が適用され、(日本で複製等される場合を除き) 国内源泉所得とはならず、源泉徴収もない という解釈でよろしいでしょうか?

米森まつ美
回答します
非居住者課税に関して少し整理して改めて説明します。(ほぼご理解のとおりとなります)
1 国内法による「著作権等の使用料」
著作権等の使用(複製権等)が日本国内で行われた場合「国内源泉所得」として、その「使用料」に関して源泉徴収による課税が行われます。
そこで、「翻訳の業務を全てアメリカで行った」ことにより、その報酬(使用料)が「国内源泉所得」にならないのではなく、その著作物を日本国内で複製等を行うことを前提とした報酬(使用料)は「著作権の使用」に対する使用料として、「国内源泉所得」に該当し源泉徴収による課税が行われます。
2 日米租税条約上の「使用料」の取扱い
日米租税条約第12条により、著作権等の使用料は「免税」とされています。
日米租税条約に規定がないのではなく、使用地主義・債務者主義の規定がないため、国内法で解釈されるということになります。
3 租税条約の適用を受けるための手続き
各国との租税条約により、国内法と別な取り決めがされている場合は、租税条約の取扱いが優先されます。
そして、税率の減免等の取扱いを受けるには「租税条約の届出書」をその報酬や使用料が支払われる前に、支払者を通じて支払者の所轄税務署に「租税条約の届出書」を正副2部を提出することになっています。
また、当該租税条約が「特典条項」が付記されている条約の場合には「特典条項条約の届出書」を提出することになってます。
具体的には(書類としては)「租税条約の届出書」に「特典条項の付表」と「居住者証明書」を添付して提出することになります。
そこで、整理しますと
① 著作権の使用地(複製などを行う地域)やその著作権の行使に伴う著作物が日本で販売(使用)されることが前提となっている場合・・・・国内源泉所得として課税の対象となる源泉徴収される。
著作権の使用地等が国外の場合・・・国内源泉所得にそもそも該当せず、源泉徴収はない。
② 「①」により、国内源泉所得に該当したとしても、日米租税条約の適用により、「特典条項条約の届出書」を正副2部提出することにより、免税の措置が取られ、源泉徴収はない。
※提出者はあくまでも貴方になります。「支払者を通じて(経由して)」提出することになります。
このような考え方になります。説明が分かりずらくて申し訳けございませんでした。
租税条約の届出書(特典条項条約届出書含む)に関する、国税庁HPの箇所を参考に添付いたします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
大変詳しいご説明ありがとうございました!
あと一点だけ質問させていただきたいのですが、
前回ご教示頂いた
「著作物を日本国内で複製等を行うことを前提とした報酬(使用料)は「著作権の使用」に対する使用料として、「国内源泉所得」に該当し源泉徴収による課税が行われる」
というのは、企業側が私がアメリカ国内で翻訳した著作物を日本で複製・販売したら私の報酬が「国内源泉所得」になるという意味なのか、
もしくは、私本人が著作物を日本で複製または販売したら「国内源泉所得」になるということなのか、どちらでしょうか?

米森まつ美
回答します
「企業側が、私がアメリカ国内で翻訳した著作物を、日本で複製・販売したら私の報酬「国内源泉所得」になるという意味か」
⇒ そのようなご理解となります。
著作権の使用料とは、「著作物を作成した報酬」ではなく、著作権を使用許諾に対する対価となります。
翻訳を行った「行為」の報酬というよりも、翻訳した(これも実は著作権の「翻訳権」の行使になります)著作物に含まれる複製権などの著作権の行使(使用)に対する「許諾」を受けることを前提とした、対価とみらえれまする。
労働の対価ではなく、権利の許諾に対する対価(使用料)といえば分かりやすいでしょうか。
なお、貴方自身が複製を行い「著作物」を販売する行為は、ご自身が「著作権を行使した」ことになります。
これらの、著作物を販売する行為による所得(売上等)は「著作権等の使用料」ではなく、「事業所得」に該当し原則として「国内源泉所得」には該当しません。
物の売買は、著作権等の使用料とは異なります。
国内源泉所得の範囲について、国税庁HPから参考になる箇所を添付します。
「源泉所得税のあらまし」の7枚目(P270)が分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
本投稿は、2020年09月17日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。