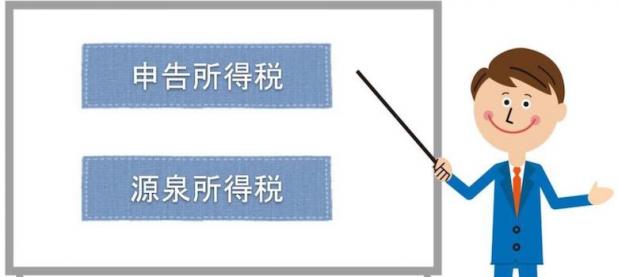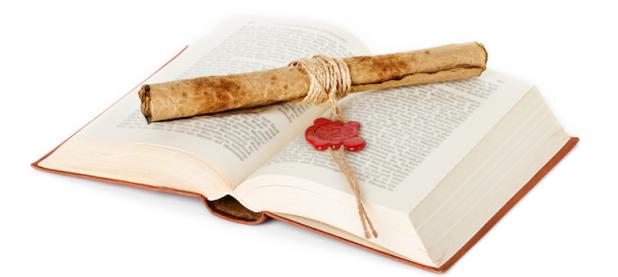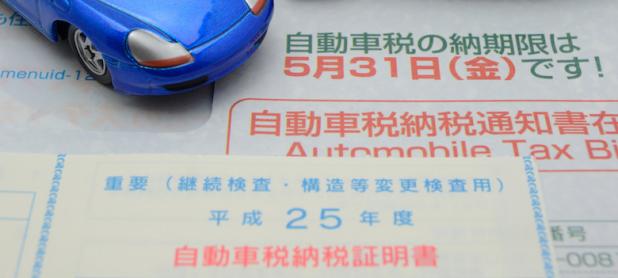けがで半身不随になってしまった父の農業の所得を自分の方へ移動できませんでしょうか?
父の不動産業(農地)の事業所得を自分の所得へ移動できませんでしょうか?
父の事業は田んぼを近所の人、親戚の人へ貸して作ってもらっていてその小作料を収入にしている状態です。
昨年、父が実家で転倒し、後頭部を強く打ってしまい、硬膜下血腫で左手と左足が動かなくなってしまい、現在入院中で、特別養護老人ホームへの移動を検討しています。
昨年は医療費が多く掛かったため、所得がない状態となり、今年から介護保険の限度額が下がり、何とか助かりました。
ただ、医療費が下がり、もしまた所得が発生してとなると来年の負担額が苦しくなってしまうかもしれません。
所得無しなら特別養護老人ホームの月当たりが7~8万円前後でなんとかなるのですが、所得が発生すると一気に月当たり19~20万円の負担になり、やっていけなくなってしまいます。
おかしな制度だと思っていますが、現状はこの制度のため、なんとか対応しないといけません。
実家の田んぼの農地は売るに売れない状態で、年65万円の土地改良費や固定資産税は払わなければいけません。そこでその費用を何とか捻出するために田んぼは近所の人や親戚の人に作ってもらっています。
その不動産収入で父に所得が発生すると、発生する所得以上に医療費や特別養護老人ホームの負担が大きくなってしまう状態です。
そこで、父の事業の所得を自分へ移せないかと検討しています。
自分は会社員で自分の所得は会社からの給与、副業での収入になります。
このような相談ができるところがあり、とても助かります。
急な相談で申し訳ないですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
不動産収入は、不動産が、お父さんの所有でしょうから、うつすことはできません。
同情はしますが・・・法体系です。
よろしくお願いします。
すぐの回答、どうもありがとうございます。
とても助かります。
ただ目的は父の所得を発生させないようにすることなので、他の方法はありませんでしょうか?
(自分へ給与を払っていることにするとか手数料を発生させていることにするとか等々。)

竹中公剛
一緒に住んでいる場合には、専従者給与は、支払えます。
一緒に住んでいない場合には、契約で、管理の手数料は、頂けますが・・・そんなに多くは、頂けません。不動産収入の3%か5%くらいでしょう。
またすぐに回答をいただけるとは、本当にどうもありがとうございます。
と、すると専従者給与の条件を詳しく知りたいです。
一緒に住んでいる条件とは父が入院中でも住民票が同じ住所であれば大丈夫でしょうか?
もし父が特別擁護老人ホームの住所になると一緒には住んでいないことになってしまいますか?

竹中公剛
下記を参照して、ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
[令和2年4月1日現在法令等]
1 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
2 青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
このページの先頭へ
3 事業専従者控除
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。 (1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。 イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
(所法2、56、57、所令164、165、所規36の4)
回答、どうもありがとうございました。
この方法では厳しそうです。
何か別の方法を検討してみます。
本投稿は、2020年09月22日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。