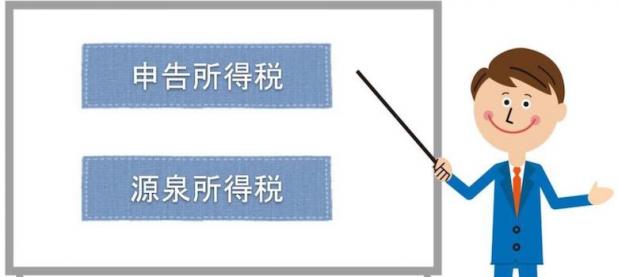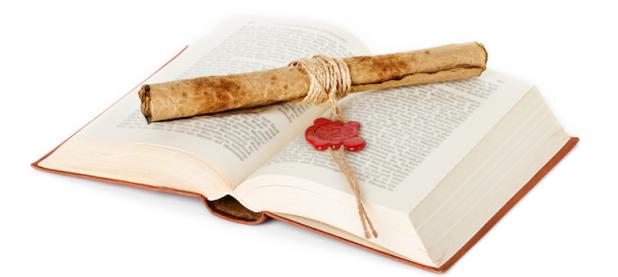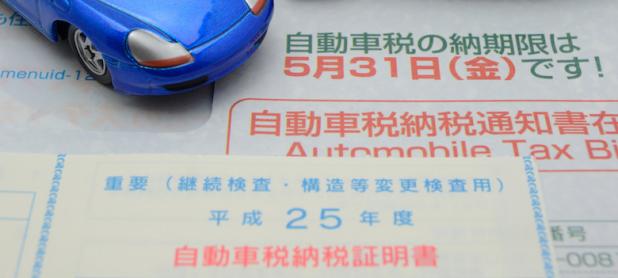会社清算時の法人税
お尋ねします。
会社を清算し、会社の土地を個人(株主)に移そうと思います。
会社の資産は土地のみです。
簿価4億円、時価(≒公示価格)は路線価から算出すると約2億5千万円です。
土地を株主(家族)へ現物分配をしようとする場合、会社に税金はかかりますか、
かかるとすればどの部分にどれくらいかかるでしょうか。
資本金は1千万円。債務はありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
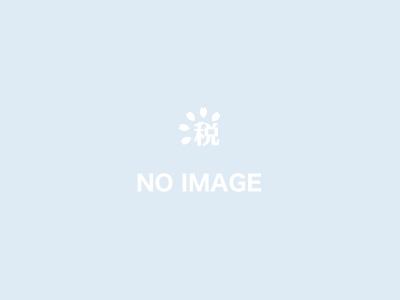
安島秀樹
土地の評価損が1億5000万あるのですが、土地の簿価と資本金の差の3億9000万が利益剰余金なら、評価損をいれても税金はかかるのではないでしょうか。個別に税理士さんに相談したほうがいいと思います。
有難うございます。
利益剰余金に対する税金に土地の評価損はどう絡むのでしょうか。
それとも評価損があることは影響しないのでしょうか。
平成22年度改正で、清算所得(残余財産-資本金等の額+利益剰余金)課税は廃止されています。
株主が個人のようですから、ご記載の残余財産の分配は非適格現物分配に該当し、会社側は時価で譲渡したものとされますので譲渡損が生じるのあれば、会社の残余財産確定事業年度の確定申告では法人税は生じないことになります。
なお、残余財産分配時の税務仕訳は、(借方)資本金等の額1千万円、譲渡損失1億5,000万円、利益積立金(みなし配当・貸借差額)2億4,000万円/(貸方)土地4億円 になりますが、上記の譲渡損失は残余財産確定事業年度の損金の額に算入するとされているからです。(法人税法第62条の5第2項)
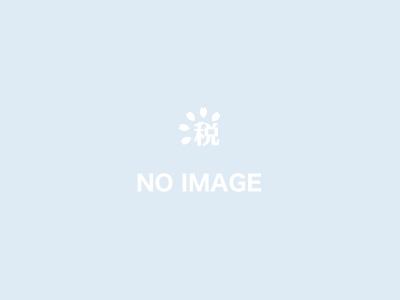
安島秀樹
税金は配当金にかかる個人の税金のことです。
法人税はかからないというのは、前田さんの言う通りです。
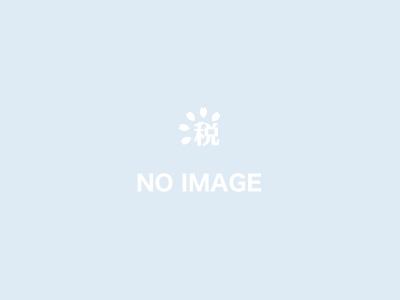
安島秀樹
配当金の源泉税は現金で用意しないといけないので、増資などしないと、清算もできないように思います。
前田先生
大変明快なご回答有難うございます。
残余財産、利益剰余金には課税されないのですね。
現物分配を受けた株主への課税のみということが分かり、大変助かりました。
ありがとうございました。
安島先生
補足、有難うございます。
確かに不動産の分配に対しての源泉徴収とはどんな形になるのかよくわかりませんが、
ご指摘、助かりました。
現金分配を受けた株主への課税のみというのが株主に対するみなし配当課税のことであれば、それは違います。
現物(土地)分配でもみなし配当課税は生じます。
当初のご質問は法人に対する課税でしたので、先の回答をしました。
残余財産分配に係る源泉所得税の徴収納付義務は会社にありますが、残余財産確定時に会社に現金がないのであれば、分配を受けた株主からみなし配当×20.42%を徴収して納付すれば済みます。
有難うございます。
現金分配を受けた株主への課税のみというのが株主に対するみなし配当課税のことであれば、それは違います。
現物(土地)分配でもみなし配当課税は生じます。
この部分がよく理解できないのですが、現物分配を受けた株主へは最終的に総合課税としての所得税が
課されると考えてましたので、会社に対しての課税のみお聞きしました。
会社には課税されない、株主にはみなし配当課税、引いて、所得税が課されていくという理解で
間違ってますでしょうか。
非上場株式の払戻しに係るみなし配当は、ご記載のように最終的には総合課税ですが、追加質問への回答の通り現物分配でも源泉徴収納付義務はありますので、会社は源泉徴収をしなければいけません。
現物であれば源泉税の納付が出来ないので、払い戻しを受けた株主から源泉税相当額を徴収して会社が納付しなければいけません。
会社の課税と株主の課税は別モノです。
会社には課税されず、株主にはみなし配当課税がされますが、みなし配当課税を引いて所得税が課されていくのではなく、会社が源泉徴収して納付したみなし配当に係る所得税は、株主が確定申告において源泉徴収された所得税額として最終的に控除して申告することで精算される形になります。
前田先生、何度も丁重なご回答を感謝いたします。
素人の悲しさ、正確な表現記述ができておらず申し訳ありませんでした。
よくわかりました。
現物分配への源泉徴収の方法についても教えて頂きありがとうございます。
これに懲りずまた宜しくお願い致します。
税理士の専門外ですが、解散登記後の株式発行による増資は可能とはなっています。
ただ、残余財産確定まで行きついてから、源泉徴収税額を確保するためにわざわざ増資をするというのは現実的ではないと思いますので、分配を受ける株主から徴収して会社が納付する形になろうと思います。
有難うございます。
株主から徴収できるのが可能であればそれがシンプルで簡潔と思います。
清算に際しての税額が見えてきました。
重ね重ね有難うございました。
本投稿は、2021年12月19日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。