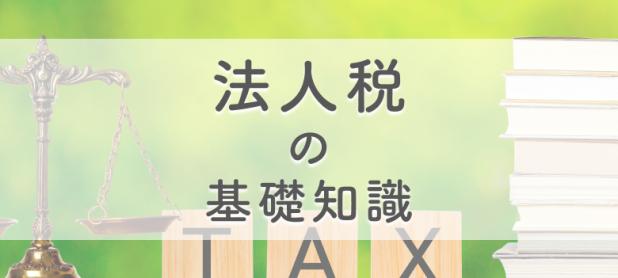無償減資と均等割について
このたび税制改正で、無償減資で損失と相殺すれば、法人均等割が安くなると話をききました。
税理士先生が提案してくれないのでこちらに質問させていただきます。
当社は過去の損失が大きく残っておる一方で資本金が5,000万円と比較的多額です。そこで
この規定を使えればと思っているのですが、例えば次のような状況の場合どのように扱われるのでしょうか?
<当社の状況>
繰り越し損失 △5,000万円
資本金 5,000万円(資本準備金はありません)
この状態で、4500万円の無償の減資をして損失と相殺したいと考えています。
すると、損失は△500万円、資本金も500万円となりますので、均等割は一番低い区分に
変更されると思います。(処々の手続きは司法書士先生にきっちりしていただきます)
<質問>
当社現状毎期600万円程度利益が生じています。すると来期は繰り越しの損失はなくなり
反対に繰越利益100万円と単純計算するとなります。この場合においてもいったん問題なく無償減資により下がった均等割は、増資等しない限り、そのままずっと下がったままでしょうか?
また、これによる青色欠損金の残高には影響はないでしょうか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
川崎市のHPがよくまとまっていますのでご紹介します。
http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000066948.html
おっしゃるとおり、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人の住民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が変更となりました。
平成27年4月1日以後に開始した事業年度から「資本金等の額」の計算上、ただし、無償増資、無償減資等による欠損てん補などを行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となりました。
これはご質問にあるような繰越欠損がなくなることにより影響を受けるものではなく、「資本金等の額」に変更がなければ、そのままです。
また「これによる青色欠損金の残高には影響は」ありません。
ただし適用を受けるために無償増資、無償減資等による欠損塡補の事実・金額を証する書類の提出が必要です。何が必要かは各都道府県・市町村に確認してください。
以上です。
及川先生ありがとうございます。
ということは、いったんきちんと認められた均等割りは法人税の別表5の資本金等の金額欄に増資等
により増額変動がなければずっと下がったままという認識ですね。承知しました。
頂戴した川崎市のHPで、H18.5月以降の減資の場合、剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る)を減算します。
とありますが、これは、会計処理上で繰越損失と資本金を相殺する前に、例えば6月2日にいったん資本金を資本剰余金に振り替えて、6月5日に繰越損失と資本剰余金を相殺すれば認められるという認識でよろしいでしょうか?
「以前1年間」とあるのが気になりまして、1年も空けないといけないのであれば今期は間に合わないのかと思いまして。
会社法上は無償減資と欠損填補は別の手続きなので通常は一度の株主総会で「無償減資及び欠損填補」を決議します。
会計上は
(借方)資本金 (貸方)その他資本剰余金
(借方)その他資本剰余金 (貸方)繰越利益剰余金
と処理します。
「損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る」というのは、資本金又は資本準備金を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失の填補に充てた金額に限るということであり、「無償減資及び欠損填補」を同時にすることはこの要件を満たすことになります。
適用外になるのは、無償減資をして資本剰余金としてから1年を超した後に欠損填補をする場合です。
及川先生
よくわかりました。ありがとうございました
本投稿は、2016年06月02日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。