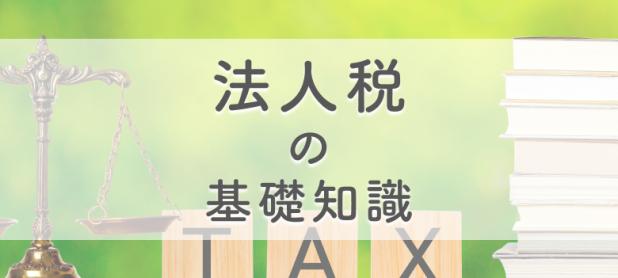電子取引における電子データの保存について
国税庁のQ&Aやネット記事などを読むと、電子取引で受領した電子データを出力し、書面で保存することが認められていましたが、2022年1月1日からは廃止されて、電子データで保存しなければならないとあります。
(消費税法では引続き、出力書面による保存が可能)
電子取引で受領した電子データは、電子データで保存するのが義務となるのでしょうか?
国税局電話相談センターに問い合せたところ、義務ではなく、任意との回答を受けて、義務・任意どちらが正しいのか悩んでいます。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
令和3年の改正により、令和4年1月1日以降について、電子取引で受領した電子データは、電子データで保存することが義務となりました。(電子帳簿保存法第7条)
書類に出力したものついては、税法上の保存書類として扱わないため、信憑性が低いデータという位置になります。
義務上の電子データを選択するか、補助的資料としての書類データを選択するか、はご質問者様の判断次第となりますので、任意という言葉が出てきたと推測いたします。
田村先生ご回答ありがとうございます。
義務上の電子データを選択するか、補助的資料としての書類データを選択するか
上記についてですが、下記の解釈で合っていますでしょうか?
①電子取引で受領した電子データは、電子データで保存するのが義務。
②青色申告の承認取消しになる可能性がありますが、書面出力(紙)が可能。
①②どちらを選択するかは事業者の判断。
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

田村真希
こんにちは。
追加質問の件、ご理解のとおりとなります。
書面で保存したことが、直ちに青色申告の取り消しとなるのではなく、
状況を勘案して判断する、そうです。
曖昧で使い勝手が良くないので、来年以降また改正になると思います。
ご回答ありがとうございます。
事業者としては手間でしかありませんが、受領した電子データの保存が義務化されるのであれば、ソフトウェアの導入または事務処理規程を定めて対応したいと思います。
大変勉強になりました。
本投稿は、2021年08月26日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。