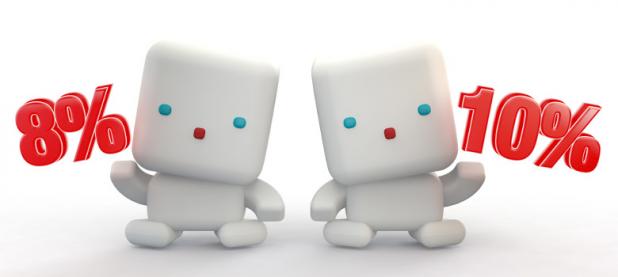学会の団体の判断と税の扱いについて
・医療系学会の都道府県支部学術集会を、毎回その都道府県内の異なる病院が開催当番病院となって開催しています。学術集会名には「第○回」という文言が入り、学術集会会長は当番病院の病院長または管理者が担当します。
・学術集会の名称に「〇〇都道府県支部」の文言が付くものの、決算・税務処理は都道府県支部とは切り離して処理することになっています。
・開催前に、学術集会運営のためのお金(開催準備金)として、前回学術集会の余剰金が前回当番病院から振り込まれます。
・学術集会が終われば、余剰金を開催準備金として次回当番病院へ振り込む予定です。
・学術集会の予算規模は収入・支出とも1,000万円未満であるとします。
・通常は年に1回の開催のため、当番病院が運営資金を管理するのは約1年間ですが、今回コロナの影響で学術集会が延期となったため、1年を越えて管理することとします。
Q1.上記の場合、今回開催する学術集会は、前回・前々回等、過去に開催した学術集会とは別団体として扱われ、消費税の課税対象にはならないということで合っていますでしょうか?
Q2.上記において、前回当番病院の余剰金が開催準備金として振り込まれた場合、消費税や法人税等、いかなる税の課税対象にもならないという認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
あくまでも私の個人的考えによるものですが、回答いたします。
質問1の関係ですが、過去に開催した学術集会とは別団体として扱われることは無いと思います。基本的に回数は一つ増えた回数が表示されるのですよね。そうであれば、別団体ではないと思います。消費税の課税対象か否かについては、今まで開催されたものについても課税されていないと思われます。
その根拠は、消費税の課税要件が、日本国内において、事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等ということになっておりますので、事業として認められるのかどうかだと思います。
ご質問のケースでは、継続反復が行われているとは言い難いと思われ、課税要件の「事業として」を満たさないと思われます。
質問2
前回当番病院の余剰金が開催準備金として振り込まれた場合、消費税や法人税等、いかなる税の課税対象にもならないという認識で合っていますか?
上記については、消費税の課税対象からは外されると思いますが、法人税はそう簡単ではありません。
参加する法人が会費を負担した結果、余剰金が発生したことになりますので、過大な会費を徴収したこととなり、余剰金を、その負担した法人数で除した結果出てくる数字を法人別表4と5で調整する必要があります。
この点は、よく税務調査で問題になるケースだと思います。
ここに記載した内容は、あくまでも私の個人的見解です。ほかの先生方によれば、違った考え方をされる先生もいるのではないかと思われます。
何れにしましても、団体について今一つ明確ではありません。
この団体について、しっかりとどのような組織なのかを検討する必要もあると思われます。
参考になるのかどうか分かりませんが、検討をお願いいたします。
ありがとうございます。
>参加する法人が会費を負担した結果、余剰金が発生したことになりますので、過大な会費を徴収したこととなり、余剰金を、その負担した法人数で除した結果出てくる数字を法人別表4と5で調整する必要があります。
ここでいう、参加する法人とはどういう意味でしょう?
ちなみに、学術集会の収入は
・参加費
・企業からの寄附金
・企業からの広告掲載費(参加者に無料で配る抄録集への広告掲載)
・ランチョンセミナー費(web開催時は共催セミナー費:参加者は無料、企業がセミナー費をスポンサーとして支払い、講演者の選出や講演料の支払いもスポンサー企業が直接行う)
・(コロナでない場合)企業ブース展示
といった具合です。
余剰金は次の当番病院が開催準備に充てられるよう、一定額残しています。その病院の経費を充てることはできませんので。
このような状況ですが、やはり同一の団体とみなされるのでしょうか?
その場合、過去の開催当番病院が行った決算処理も、税務調査の対象になりますか?

新木淳彦
こんにちは。
言葉足らずで済みませんでした。
参加する法人とは、開催される学会に参加する法人(医療法人等)又は個人(個人開業医等)の事をいいます。従いまして、寄付や広告等の協賛法人等は含みません。
同一の団体とみなされるのかとの質問ですが、あくまでも開催の主催者は、医療の都道府県支部になるのではないのでしょうか?
私の認識違いがあれば別の話ですが、例えばあまり良い例ではありませんが、開催された学会で何らかの事故が発生したと仮定した場合、その事故の解決を図るための中心団体は何処になるのでしょうか?
その中心団体が、本来の開催団体になるのではないでしょうか?今回のケースで考えますと、都道府県内の異なる病院が開催当番病院となっているだけで、最終的な責任を負うのは、都道府県支部ではないでしょうか。そうなりますと、都道府県支部の主催で当番病院が毎年変わるだけということになると思います。であれば、同一の団体ということになると私は考えます。加えて、この学術集会の会計報告はどの様になされるのでしょうか。例えば、当番病院が都道府県支部に行う。あるいは、都道府県支部が各病院に会計報告をして承認を得る。その実態によっても主催者を特定することは出来ると思います。
過去の開催当番病院が行った決算処理も税務調査の対象になるかとの質問ですが、その可能性はあります。ただし、調査=修正とは限りません。法人企業の場合、剰余金が発生していた場合には、直前年度の申告書で調整することが可能です。ですから、ここで正しく決算調整なり申告調整なりを各法人が行えば問題にはならないでしょう。
これはテクニックの問題になりますので、顧問税理士に確認して頂ければ理解できると思います。
ありがとうございます。
開催する学術集会の参加費については、個人単位(病院や開業医ではなく、一個人)が参加登録して負担するようです。学会会員と非会員とで参加費が違う設定になっています。個人単位ですが所属する病院などからの"出張"扱いで、病院が参加費を持つことになるケースが多いと思いますが…。
>その中心団体が、本来の開催団体になるのではないでしょうか?
ご指摘の通り、都道府県支部の代議員会または世話人会といった意思決定機関により、どの病院が開催当番となるかが決まります。
会計報告は、当番病院が都道府県支部に行い、支部の監査を受けると思います。もしかしたら全国本部の監査も受けるかもしれません。
前回学術集会の決算書の元データは引継ぎなどでもらうことができますが、学術集会会長印が押された決算書は支部が持っているようです。
最初の質問でお伝えしたとおり、都道府県支部と学術集会とは税務処理は別々で行うことになっています。また、全国本部は法人格を持っていますが、学術集会は法人格を持っていませんし、都道県支部も法人格を持っていないと思われます。

新木淳彦
こんにちは。
都道府県支部と学術集会は別会計ということですね。理解が出来なくてすみませんでした。
そうなりますと、学術集会の開催スパンが通常でも年に1回程度ですから任意団体による開催であり事業とは呼べないでしょう。
本来からすれば、学術集会に関する規約が整備されるべきかと思います。その規約の中で、一回ごとに会計報告をして解散すること。
開催の時期は強制されることなく任意に定めることが出来ること。
収益を目的とせず、会員の知識の研鑽に寄与すること。
学術集会の会費の在り方、徴収方法について定めること。
以上のほかにもあるでしょうが、規約を定めることで、より明確化されれば税務上の問題は解決されると思います。
ただし、会員が個人負担をした場合を除いて、所属する医療法人等がその会費を負担した場合には、剰余金を会員数で除した金額を通知して、医療法人等で会計処理又は法人別表調整が必要になると思いますので注意して下さい。
所属する医療法人等がその会費を負担した場合には、剰余金を会員数で除した金額を通知して、医療法人等で会計処理又は法人別表調整が必要になる…
これは、学会会員の年会費のような類のことでしょうか? それについては全国本部が担当しているかと思います。
学術集会としては、イベントの参加費として料金を徴収しており、学会員と非会員とでは金額に差をつけています。個人単位で参加申し込みがあっても、医療機関から振り込まれる場合、参加者が立替振り込みして後で所属機関が参加者に支払う場合、参加者の自己負担の場合と3パターンあるかと思いますが、医療機関から振り込まれる場合を除いて、参加費を所属機関が負担したかどうかは、学術集会側では把握できないですね。
あと、収入は参加費だけでなく、企業からの寄附金や広告掲載費(参加者等に無料で配ったり、パスワード付きでホームページ公開する抄録集に載せる)、預金の利息、前回当番病院からリレーされたお金、などもあります。余った金額は次回開催当番病院に送りますし、もし次年度開催がないとすれば都道府県支部に渡すことになるかと思います。
その余った金額を計算して団体に通知するという意味でしょうか?

新木淳彦
こんにちは。
確かにおっしゃる通り、難しそうですね。
学会員と非会員とで金額に差が生じるのであれば複雑さは増大しますしね。
しかしながら、税法はその処理が複雑だから免除するとかしないかの忖度は致しません。税法は税法なのです。特定の事案に対して特別の対応をするということはありません。
ですから、法律論で来られると困ってしまう可能性があることを理解ください。
ではどうするか、基本的には、剰余金が出ない環境あるいは出ても僅少な金額に抑えることが肝心だと思われます。
仮に剰余金の累積が20万円の場合、50万円の場合、100万円の場合では、その取扱いに違いが出てくることは想像できると思います。
税務当局から問題視されないようにするには、累積剰余金の額を僅少な額に抑えることが肝心だと思われます。
ここがクリアされれば、法人税も消費税も問題になることはないでしょう。
実態としまして、本件が問題になる可能性があるとすれば、それは税務調査による場合だと思います。
税務調査は調査官の力量にもよるところが大きいです。
いずれにしましても、累積剰余金の額をあまり高額にならないように会費等で調整されることが必要でしょう。
本投稿は、2021年07月23日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。