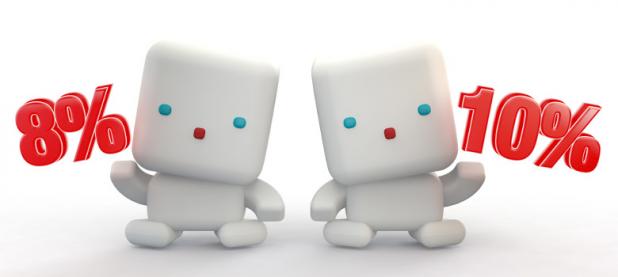インボイス制度について
インボイス制度について教えて頂きたいのですが、主人が塗装業を営んでおります。
一応個人差事業主なんですが主人の親の会社から、1日17000円で外注扱いで働いてます。
この場合でも消費税を支払う義務があるのでしょうか?
ご返答頂ければ幸いです、宜しくお願い致します
税理士の回答
消費税の納税義務の発生要因はいくつかありますが、インボイス登録をして、インボイスを発行すると、事業規模にかかわらず消費税の申告納税義務が生じます。
ご返答ありがとうございます。
インボイスを登録しないとどうなりますか?
それは、発注会社との関係によって変わると思いますが、一般的にいわれていることは、取引価格について、そのままか、値下されるか、あるいは、インボイス登録を要求されるか、のいずれかです。
朝から丁寧なご返答ありがとうございました。

米森まつ美
回答します
ご主人が「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」の登録申請をした場合は、消費税の申告・納税をする義務が生じます。
【消費税の考え方】
ご主人が「外注費」としていただく報酬には、別途請求する(税抜き)、しない(税込み)に関わらず、消費税の課税対象として消費税額が含まれていることになります。
また消費税の申告・納税は、基準期間(前々年)の課税売上げ高が1000万円超の場合、課税事業者となり消費税の申告納税の義務が生じます。
ただし、免税事業者(消費税の申告納税義務のない事業者)であってもその売上が非課税などの対象物でない限り「課税取引」として消費税が含まれている考え方となっています。
なお、消費税の納税は、簡単に説明しますと
課税売上に係る消費税額 ー 課税仕入れにかかる消費税額(仕入税額控除)= 消費税の納税額
となっています。
現在の法令では、仕入税額控除は、相手先(仕入先や外注先)が免税事業者であっても控除の態様とすることができます。
【インボイス制度】
インボイス制度とは、「仕入税額控除」は原則インボイスに記載された消費税額のみとなっています。
令和5年10月1日からスタートする「インボイス制度」とはこのような制度となります。
インボイス(適格請求書)は、インボイス発行事業者の登録申請をした者以外は発行できません。
またインボイスには、インボイス番号を付番しますが、これもインボイス発行事業者になりませんと付番することはできません。(個人事業者の場合は税務署から番号を通知されます)
なお、課税事業者であっても、インボイス登録申請をしませんと「インボイス発行事業者」に慣れませんが、「インボイス発行事業者」は必ず課税事業者になります。
そこで、インボイス制度が開始しますと、売上先(親会社)などは、自社の消費税の申告時に「仕入税額控除」を行うため、仕入先や外注先から「インボイス」を求めることになると思います。
免税事業者であっても、「インボイス発行事業者」の登録申請を行うことができますが、登録後は必ず消費税の申告・納税義務が生じることになります。
そこで、現在ご主人が免税事業者であるならば、インボイス発行事業者となるか否か、検討が必要になります。
なお、令和5年10月1日のインボイス制度スタート時からインボイス発行事業者になるには、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
国税庁HPに「インボイス特設ページ」がありますので、そのアドレスをご案内いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
なお、インボイス制度の適用によって、影響を受ける会社は、支払い元の会社が、一般課税により消費税を申告納税している場合です。
一方、簡易課税により消費税を申告納税している場合は、事実上、影響はないとされてます。
親御さんの会社の消費税の計算方法をご確認してみてください。
細かいご説明ありがとうございます。
主人の年収は、450万円前後で、1日17000円×日数のみで材料費等の経費は何もありません。
この様な場合でもインボイス登録必要ですか?
親御さんの会社から、別にしなくていいと言われれば、しなくていいと思います。
義親に確認してみます。
長々とありがとうございました。
そうですね、まずは、確認されることをおすすめします。
本投稿は、2022年06月02日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。