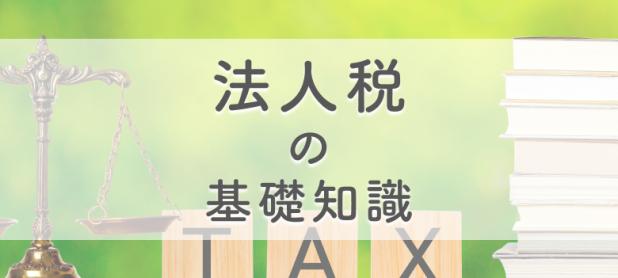相続による建物増築分の固定資産税未算入の判明について
相続した工場の登記簿と固定資産税納付通知書を見比べたところ増築されたであろう建物分の固定資産税が入っていませんでした。
(工場は賃貸に出しています。)
地震による損傷補修のため検証をしたところ判明しました。(詳しい見積りはまだなのですが建物補修で、数百万円かかると言われています。)
増築した年は定かではありませんが4〜50年前に遡ります。
最初の建築年は昭和40年代です。
加入していなかった火災保険の加入も考えています。
相続は2019年8月です。
質問1
この場合、今後どうしたら良いでしょうか?
質問2
この状態で火災保険に入るにはどうしたら良いですか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
質問の趣旨をまず整理します。確認したいことは下記の事項で宜しいでしょうか。
1.工場の登記簿謄本による面積と市町村の名寄せ台帳(固定資産税課税明細書)の面積に不一致が生じているが、どうしたらよいのか?
2.現況の状態で火災保険に加入できるのか?
上記の2点で宜しいでしょうか。
まず1.の回答です。
実際に登記簿謄本と固定資産課税台帳との面積誤差がどのくらいあるのか不明ですが、実際のところ、誤差が生じていることに、そんなに違和感はありません。誤差があって当たり前という側面もあります。
確認する方法としましては、工場の所在地を所轄する市町村役場において、固定資産の名寄せ台帳の写しを申請し取得して下さい。
そこには、工場の情報が出ております。登記簿謄本が存在するのですから、登記はなされておりますので、登記簿謄本の面積が名寄せ台帳の工場の欄に登記面積として記載されております。名寄せ台帳に記載されたその登記面積が、登記簿謄本の登記面積と一致していれば、整合性は採れておりますので問題ありません。
よってこの場合には、特に何もすることはなく、火災保険の手続きに入ってもらって結構です。
もし、仮に違っていた場合には、市町村の固定資産税課に直接確認をして下さい。その結果、誤差があることに説明がつかない場合は、後日、固定資産税課担当が家屋(工場)の調査に行くと思います。日程につきましては、火災保険の加入を考えているので早めに調査して欲しいと依頼して下さい。
調査の結果、誤差が判明すれば、課税台帳等を正確なものに修正してくれます。
以上が、1.に対する回答になります。
2.の火災保険への加入ですが、お付き合いのある損害保険会社があれば、事前にお話をしておくのがベストだと思います。
火災保険の場合、その種類もたくさんありますので、どの保険にするかでも迷います。また火災保険の場合、保険事故が発生したときに、再建築価格を基本に保険金額を設定することになっているはずです。
今回問題になるのは、面積ですから、その面積だけ一旦保留にして、例えば登記簿謄本に記載された面積と固定資産課税台帳に記載された面積のうち大きい面積を採用して見積もりを貰うこともできると思います。
また、保険に未加入である場合は、一旦保険に加入だけしておいて、面積の関係(1.)の解決が出来た時点で火災保険の修正を依頼することもできるのではないかと思われます。
以上が、今回の回答になります。
ご検討をお願いいたします。
ご回答大変ありがとうございます。
すみません、書き方がわかりにくかったのですが、登記簿謄本による面積と固定資産税課税明細書の間の誤差ではなく、それらはほぼ一致しているのですが、実際の建物の床面積の間に200平方メートル程の増築分の差があることが分かりました。質問1,2につきまして再度ご回答いただければありがたいです。
宜しくお願い致します。
追記します。
いつ、増築したかを知っている父は亡くなっており、増築した年月日は不明です。(増築してから最大4〜50年)
市町村の固定資産税課に事情を説明し、調査を依頼すると登記簿謄本を修正することになるかと思います。そうすると今までの未納分(200平方メートル増)の固定資産税を遡って納めなくてはいけないと思うのですが4〜50年ともなると大変な額になると思います。調べたところ固定資産税の時効は5年の様ですがその金額で済むものなのでしょうか?(勿論、知らなかっただけで故意に払わなかった訳ではないのですが2019年〜)追徴課税はどんな形になるのでしょうか?
また、罰金とか、懲罰の対象にあたったりしませんか?

新木淳彦
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
つまり、市町村と法務局との間には誤差は殆ど無いということで宜しいですよね。
つまり、増築したのはいつか解らないけど、増築したときに登記しなかったから、市町村も気が付かなかったということですね(相談者様も想像の範囲ですが)。
この場合にどうするかですが、
1.土地家屋調査士に依頼して、正確な建物図面と面積を確定してもらい、それをもって法務局で登記し、後は、市町村に任せる方法。
2.土地家屋調査士に依頼するのはお金がかかる話になるので、依頼はせずに、市町村の固定資産税課に出向き、現地調査をしてもらい課税台帳を正しく直す方法。
3.このまま何もせず、現状のまま放置してしまう方法。
特に2.の場合ですが、質問文にもありますとおり、時効は5年となっております。私の住む市では、このような場合には遡ることはせずに、次年度からの正しい納税に向けての調整となっているようです。
もしも心配でしたら、市町村が現地調査した後、課税する前までに納税者としての意思をお伝えしておけば宜しいのではないでしょうか?
確かではありませんが、私の経験では仮に正しく補正されたとしても次年度からで、遡ったという経験はありません。
ただし、地方税法では時効を定めており遡及は出来る仕組みになっておりますので、何とも言えません。
火災保険につきましては、その建物の構造と床面積、工場の仕事内容によって料率が決まってきます。その時に正確な床面積を提出するということもなく保険会社で対応はしてくれると思います。

新木淳彦
済みません。追加です。
もしも私が相談者様の立場だったらどうするかですが、細かい資料は持たずに、市町村の固定資産税課に出向きます。
そこで、次の質問を投げかけ相談という形をとります。
「ちょっと機会がありまして、固定資産税の方税通知書を調べておりましたところ、固定資産税に記載された建物の床面積が実情とあっていないような気がしております。この場合において、正しくするには現地調査をお願いすることだと思いますが、その場合、遡って追徴課税されてしまうのですか?それとも今後の納税額を正しくするだけで済むのですか」
「現状でははっきりと分かっていないので、もしも今後のところだけに影響させるということであれば、現地調査してもらおうかとも思っておりますが、遡りされるのであれば、このまま放置しようかと思っています」
こんな感じで聞いてもらえば宜しいのではないでしょうか。
追加として、建物自体はかなり古いことも伝えて下さい。
参考にさせて頂きます。
ご丁寧に色々とアドバイス頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年10月12日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。